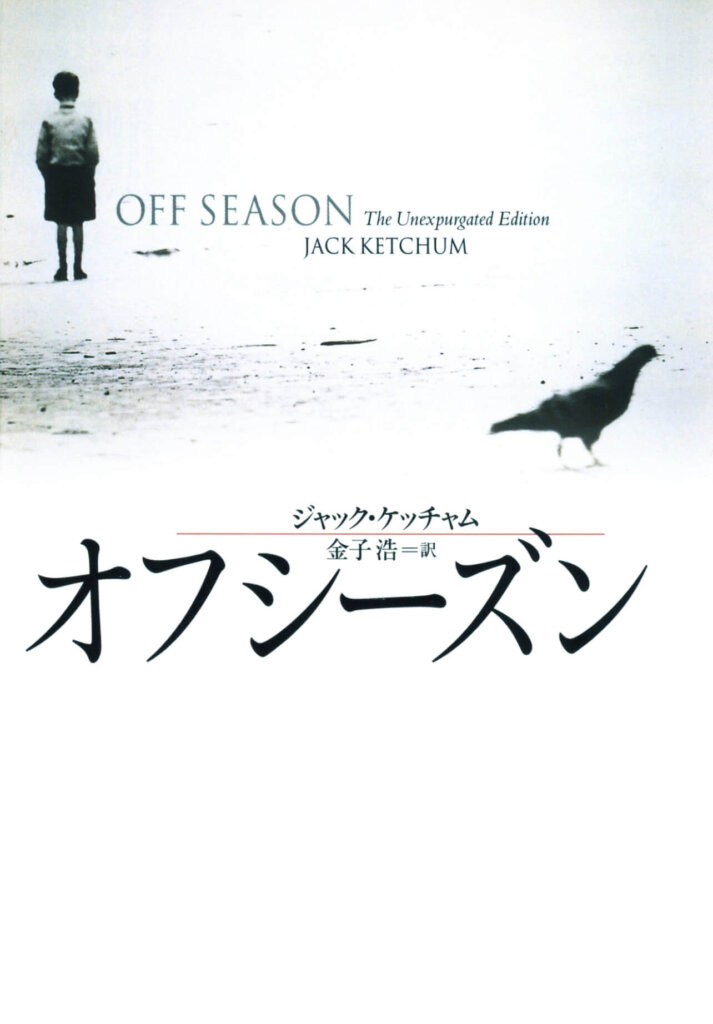
作品の概要と感想(ネタバレあり)
タイトル:オフシーズン(原題:Off Season)
著者:ジャック・ケッチャム
出版社:扶桑社
発売日:2020年2月4日(単行本:2000年9月、原作:1981年)
避暑客が去り冷たい秋風が吹き始めた9月のメイン州の避暑地。
ニューヨークから6人の男女が休暇をとって当地にやって来る。
最初に到着したのは書箱編集者のカーラ。
すこし遅れて、彼女の現在のボーイフレンドのジム、彼女の妹のマージーとそのボーイフレンドのダン、そしてカーラのかつてのボーイフレンドのニックとそのガールフレンドのローラが到着した。
6人全員が到着した晩に事件は勃発した。
当地に住む”食人族”が6人に襲い掛かったのだ──。
残虐非道な鬼畜系作品を数多く生み出してきたことで有名なジャック・ケッチャムのデビュー作。
ケッチャム作品で読んだのは『隣の家の少女』『冬の子』に続く3作目で、ようやく読めました。
『隣の家の少女』と『オフシーズン』が特にグロくて胸糞で面白くて有名というのは知っていたのですが、最初タイトルを聞いたときには、こんな食人族が出てくる話だなんて想像もつきませんでした。
いやぁ、とにかくほんともう容赦ないですね。
現実における救いのなさを突きつけてくるような無情な展開。
それなのに、いや、だからこそ引き込まれました。
1981年の作品ですが、今でもまったく色褪せません。
やはり田舎を舞台にしている作品は、科学の発展の影響を受けづらいこともあってか、普遍的な作品が多いイメージ。
本作もスマホがあったらまた全然違ったのでしょうが、電波が届かないとかで工夫もできそうですし。
展開としては、シンプルな「田舎に行ったら襲われた」系。
ただ、今だからこそシンプルなのであって、1981年当時としてはまだまだ斬新さもあったでしょう。
序文やあとがき、解説でも言及されている通り、「田舎に行ったら襲われた系」の古典である『悪魔のいけにえ』などと近い時代の作品。
そもそも「スプラッタ・ムービー」というジャンル名ができたのも1980年代(それ以前はゴア・ムービーなどと呼ばれていた)のようです。
小説としては、パイオニア作品の一つになるのでしょうか。
自分が観た映画の中では、『悪魔のいけにえ』『ヒルズ・ハブ・アイズ』(『サランドラ』のリメイク)『グリーン・インフェルノ』あたりを思い出しました。
映画だと直接的な視覚的描写が強烈ですが、小説は小説で無限に勝手にイメージできてしまうので、それぞれのエグさがあります。
時代的にもけっこうな検閲がなされたというのは仕方ないのかもしれませんが、それでもまぁそこを削ったら作品の魅力を削るのと同義ですよね、とは思ってしまいます。
作者あとがきで、ここぞとばかりに溜め込んでいた愚痴や不満をぶちまけているのが笑ってしまいました。
内容は、これもシンプルに、扶桑社が謳っている「”食人族”対”都会族”」でほぼすべて説明できます。
ちなみに、扶桑社における単行本版の内容説明は「六人の男女を襲う、避暑地の怪異復元無削除版!」で、超端的で潔くもこれだけだと絶妙に意味がわかりません。
細かい解説や分析は序文や解説でなされていますし、心理学な考察でどうこうという作品でもないので、以下は簡単に感想のみ。
まずはとにかく、救いのなさが圧倒的でした。
『隣の家の少女』とはまた大きく異なる、何とも言えない読後感。
作者あとがきで述べられている「読者にへつらってどうする?」という言葉、かっこよすぎます。
一番衝撃だったのは、主人公と思われたカーラが早々に退場したところでした。
メインキャラが次々入れ替わるのは海外作品では珍しくありませんが、それにしても登場人物一覧の最初に名前が挙がっていたキャラがこんなにあっさり退場するとは。
しかもあんな扱いを受けるとは。
その後も、ダンの活躍を経てニックやマージ―に視点が移ったところも、先の読めなさを助長させます。
ニックも決して、真の主人公というわけでもありません。
食人族側もけっこう描かれますし、誰が主人公というわけでもない。
そのあたりもまた、序文などで分析されているような「善と悪などの境界が曖昧になる」感覚を抱かせました。
そう、食人族も、決して悪な存在ではないのです。
科学的な人間社会では脅威ですが、彼らもまた彼らの生き方で生きているだけ。
獲物に対して残虐な行為も見せますが、それもまた「恐怖を与えるほど肉が柔らかくなる」という信念に基づいている部分もあったところが巧み。
しかしこの点、実際はどうなのでしょう。
恐怖を与えると肉は硬くなりそうな気がします。
牛とかもストレスを与えると味が落ちるとも言いますし。
本作を怖がりながら平然と牛や豚を食べる我々も、牛や豚にとっては、本作における食人族と同じような存在なのかもしれません。
それにしても、食人族というのは同じ人間でありながらタブーを犯している異質感が非常に強く、恐ろしさを感じます。
サメ映画などの感想でも書いていますが、人間が捕食されるというのは、日常ではほぼあり得ないので強烈な嫌悪や恐怖を感じます。
最近はクマ被害も多いですが、他にもたとえば動物園などで飼育員がライオンに襲われるような事故があったときも、通常の死亡事故とはまた異なる独特の恐怖感を抱きます。
そしてそれを同じ人間が行うというところが、圧倒的タブー。
共食いというのもまた、種の繁栄とは矛盾して感じられるので(実際はそれが合理的な生物もいるようですが)、抵抗を感じます。
さらには、本来共食いは遺伝子レベルで嫌悪感を抱くようにできていそうなところが、食人族の異質性を高めます。
日頃、平然と殺し合っているのが人間という愚かな生き物ではありますが、食べ合うとなるとさらに一歩踏み出してしまったように感じられます。
ただ、それもそれでエゴというか、今や捕食される側にはなり得ないという驕りが影響しているのかもしれません。
ちなみに、食人族というのは実在はしたようですが、かなり限定的。
ほとんどが、好んで食人を行っていたというわけではなく、食料困難だったり古来の風習によるものです。
一応、ソニー・ビーン一族という食人一族がスコットランドに実在したとされ、本作や上述した映画『ヒルズ・ハブ・アイズ』(『カサンドラ』)などのモデルにもなっているようです。
ただ、ソニー・ビーン一族については、エピソードはやや盛られていて都市伝説化している、という説もあります。
いずれにせよ、人肉大好き!な食人族がいたとしても、食人はコストが高い(同じ知能や能力を持つ人間を狩るのはハイリスク、かつ食用部や栄養が少ないのでローリターン)、同種族だと感染症が100%うつる(クール―病が有名)、といった要因から絶滅していると考えられます。
などと、何だか食人行為に対する考察めいてきてしまったので、一旦この話はここまで。
『オフシーズン』に話を戻すと、とにかく食人族が不気味でした。
特に子どもが躊躇なく襲ってくるところが、より野性味を感じさせて大人より恐ろしかったです。
本作における食人族のルーツは、マージーが読んでいた書籍に出てきた島の灯台の話のようでした。
食人族の男が「老婆がアグネスで、老人が夜ごと、おおいなる“明かり”をともしに出かけていた時期があった」と回想していましたが、アグネス・クックというのが1858年に行方不明になった灯台守の娘でした。
パートナーとなる男性が、のちに同じく行方不明になった別の灯台主の息子だったのでしょう。
おそらくはこの2人を起源として、子どもが増えていった一族。
起源の2人は血縁関係にはありませんが、その後は必然的に近親相姦が繰り返されることになり、障害など持つ子どもも増えていきそう。
この一族は、最初から食人の風習を持っていたわけでありませんでした。
無人となった島にひっそり住んでいましたが、島にボートで来た男性を“狩った”ことで島を追われることとなります。
島で生活していた頃は釣りなどで食料を確保しており、いつから食人に手を出したのかはわかりませんが、このボートの男性なりそれ以前の誰かなり、島に来た人間を手にかけてからだったのでしょう。
おそらく最初は、衣服や所持品を強奪することから始まったのではないかな、というのが勝手な想像。
強盗殺人のついでにもったいないから食べてみたら美味しかった、ということかと予想します。
いずれにせよ、食人の歴史、それ以前にそもそも一族の歴史も比較的短いようでした。
とはいえ、こんな生活で100年以上というのは、なかなか長いのかな。
島を追われたのは、ピーターズの回想も合わせるとせいぜい数年前からだったようです。
アグネスは10歳で行方不明になっているので、食人には抵抗がありそう。
ただ、食人の歴史が浅いとすると、アグネスの死後に始まった可能性の方が高そうです。
子孫たちは一族以外とはほぼ接することがなかったはずなので、抵抗は少なめだったかもしれません。
彼らはそれなりに知能は有していますが、それほど高くはなさそうでした。
基本的に、こういった作品では脅威となる側は知能が低めで「科学的な都会人 vs. 野蛮な食人族」といった構図がほとんど。
あまり高すぎると「野蛮な食人」というよりは「美食家のカニバリズム」みたいな感じになり、頭脳戦のようになってしまうからでしょうか。
「話が通じない」「自分たちの常識が通じない」という要素によって、恐怖が高まるという理由もあるのでしょう。
子どもが犠牲になる容赦のなさも、こういったフィクションであれば評価ポイントです。
本作のように、現実における救いのなさを描く作品においては、中途半端な手加減はマイナスに感じてしまいます。
そういった点も「読者にへつらっていない」からこそ、これだけの評価を得ているのでしょう。
こういったスプラッタ系の作品では、単独行動をしたりして1人ずつ孤立しては犠牲になっていく、というパターンが多いですが、最初から総力戦かつ籠城戦というのは珍しかったように思います。
そのため犠牲者の愚かさが目立たず、それがさらに絶望感を引き立てていました。
死に方で言えば、主要登場人物の中ではローラが一番悲惨でした。
選択肢が死ぬしかないなら、やはりジムのようなあっさりが一番良いです。
死後の扱いまで含めると、調理シーンまで描かれたカーラが最もインパクトがありました。
『グリーン・インフェルノ』を観ていなかったら、さらなる衝撃を受けていたかもしれません。
ローラは最後まで自分の中でキャラが固まらず、終盤なんてなぜかけっこう年配のイメージになってしまっていました。
早々に正気を失ってしまったからかな。
マージーを救いに行ったニックは、偉すぎましたね。
惚れていた上に一刻を争うとはいえ、自分だったら「1人で無茶をするより、警察に伝えることを優先した方が結果として良い」と自分に言い訳しそうです。
バターを沸騰させて頭上からぶちまける作戦は新鮮でしたが、そんな沸騰させてぶちまけるほどバターがあるところが海外なのでしょうか。
自分としては、油の方が量があるように思います。
どうでもいいポイントにも触れておくと、まずはやはり海外小説あるあるですが、名前、というよりどれが誰だかなかなか覚えられませんでした。
基本的に6人しか出てこないのに、ダンだのジムだのカーラだのローラだの、みんな年齢が近いことや元恋人同士など関係性が入り乱れていることもあって、何回も登場人物一覧を見直してしまいました。
あとは、海外特有の言い回し。
比喩というか、直接的ではない表現がたまにわかりづらかったです。
それ自体は全然良いのですが、盛り上がっているシーンでそういった表現になると「ん?」と止まってしまうのが難点。
本作でいえば、
部屋が爆発した。こなごなになった。
カーラがまだ見あげているうちに、ナイフがいったん下げられ、ふたたび振りあげられた。
そこでニックは、両手をまえへ突きだし、武器を持っていないことを示そうとして振りながら、口を開いて、 違う、 ぼくは連中の仲間じゃない、と叫ぼうとしたが、太った男の目を見たとたん、その言葉を喉で詰まらせて横へ身を躍らせ、結局、銃声すら聞かなかった。
といったあたり。
続きを読めばもちろんわかるのですが、勢いが大事なシーンで「え、何?どういうこと?」と一瞬失速してしまいました。
翻訳の都合もあるのでしょうが。
表現の話を続けると、その後の展開がわかってしまうような表現が先に来てしまうのも、もったいなく感じてしまいました。
具体的には、
のちにピーターズは、あの女もおれたちと同じくらい驚いたんだろうな、と推測した。
のちにピーターズは、少年に対してもっとも深い──あの女性がニックと呼んだ男性よりも深い──罪悪感を覚えた。
あたり。
あ、シアリング死ぬんだな、あ、少年死ぬんだな、というのがこの時点でわかってしまいます。
もちろん、これは英語での表現だったり文化的なものだったりもするでしょうし、良い悪いという話ではありませんが。
すらすら読めるほどの英語力がないので翻訳はありがたさしかありませんが、やはり表現方法が異なりますし、著者それぞれに癖のある文体も含めて作品の魅力なので、できれば原文で読めるようになりたいな……と思います。
それが理由で、海外の小説は読みたいと思いながらもあまり読めないままでいるのですが、それももったいない話なので、英語も勉強しつつ、感謝しながら翻訳本もたくさん読んでいきたいな、と改めて思わされた1作でした。
続編『襲撃者の夜』『ザ・ウーマン』も読んでいきます。
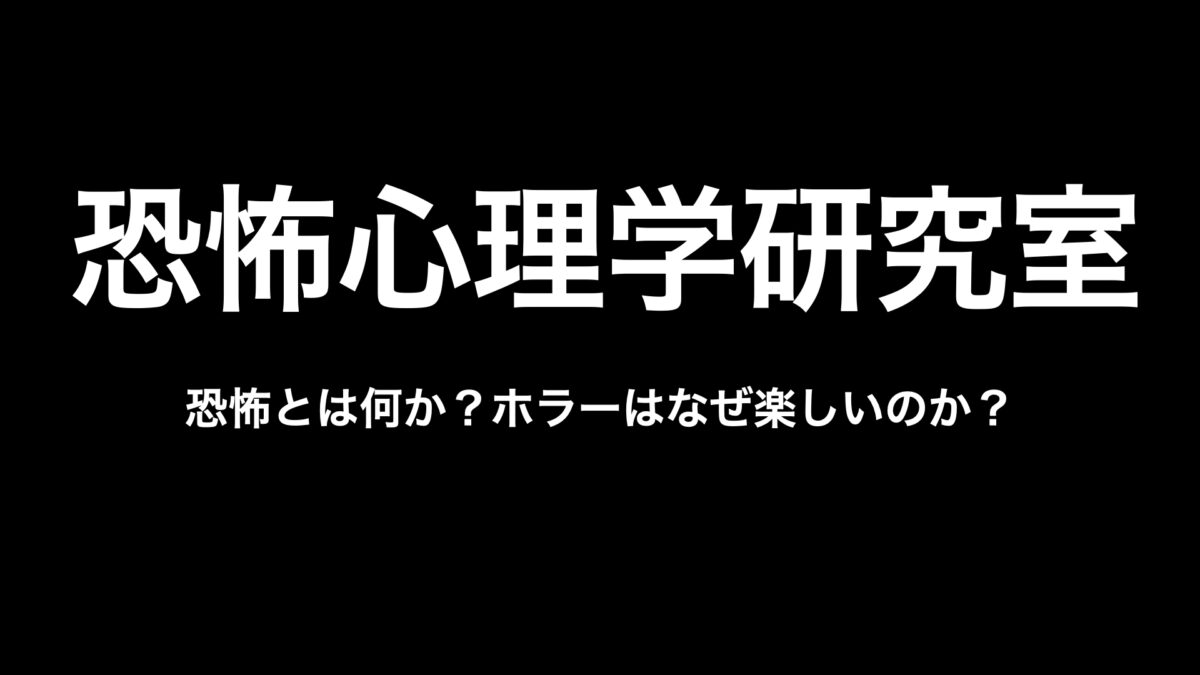
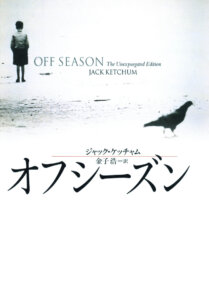
コメント