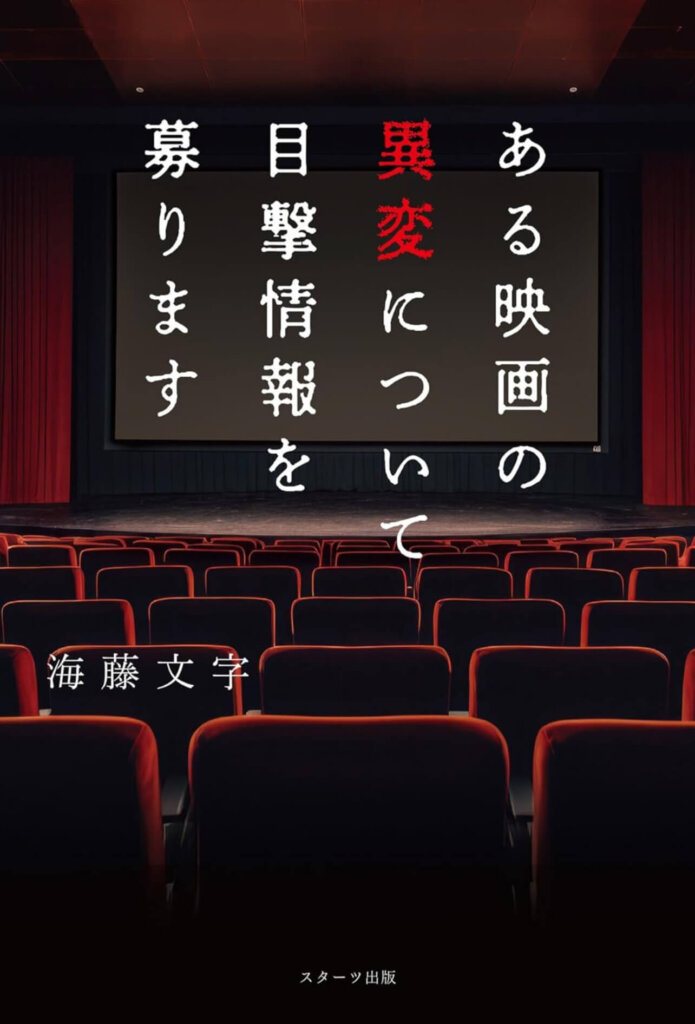
作品の概要と感想(ネタバレあり)
タイトル:ある映画の異変について目撃情報を募ります
著者:海藤文字
出版社:スターツ出版
発売日:2025年7月18日
山奥の廃村を舞台にした低予算ホラー映画『ファウンド・フッテージ』を観た映画ブロガーのMOJIは、画面の隅に説明のつかない“何か”を見つける。
やがて“それ”は他の映画にも現れ、関係者が次々と不可解な死を遂げていく。
「観たら死ぬ」という噂に怯えた仲間を追って、MOJIは映画のロケ地となった“消えた村”へ向かう。
誰もいないはずの村で、待っていたものとは──。
モキュメンタリーホラー小説コンテスト大賞受賞作品。
同コンテストは、2024年末~2025年頭にかけて小説投稿サイト「ノベマ!」において実施されたコンテストのようです。
いわゆるモキュメンタリーホラー小説ブームに乗っかったであろうコンテストではありますが、その大賞だけあり、しっかりと楽しめる1作でした。
雨穴『変な家』や背筋『近畿地方のある場所について』の大ヒット以降、特にネット発のモキュメンタリーホラー小説が雨後の筍のように乱立している昨今ですが、その中でも安定感のある1作としておすすめできます。
ちなみに、元々の題名は『ファウンド・フッテージ 観てはいけない映画のレビュー』でしたが、出版にあたり『ある映画の異変について目撃情報を募ります』に改題されたようです。
「ある~情報を募ります」だったり「異変」だったりと、既視感のある用語で構成されているタイトルは商業的な狙いが透けて見え、出版社の意向での改題かな、と穿った見方。
とはいえ「ファウンド・フッテージ」も一般的に通じるとは言い難い用語だと思うので、キャッチーなタイトルは無難とも言えるでしょうか。
個人的には、ちょっと個性が乏しめには感じてしまいました。
「モキュメンタリー」という用語は、映画や映像作品において定着していた用語で、フェイクドキュメンタリー、つまりは実際のドキュメンタリーかのように作られたフィクション作品を指します。
小説に適用されるようになったのは本当に最近で、定着したのは『変な家』や芦花公園『ほねがらみ』を経ての『近畿地方のある場所について』以降ぐらいだと個人的には認識しています。
小説では「メタフィクション」など呼ばれていたことが多いかと思いますが、「モキュメンタリー」が使用されるようになってから一気に増え、ブームの様相を呈しています。
何でモキュメンタリーホラー小説がこんなに流行っているのか、についてはいつかまとめてみたいとも思っているのでここでは端折るとして、モキュメンタリーは非常に制限が多い形態だと思っています。
作家の梨は「モキュメンタリーはジャンルではなく『見せ方』や『作り方』、つまりは方法論のひとつである」と述べていますが、ここまで来ると「その方法を用いた作品群」として一つのジャンルと化していると言っても過言ではないでしょう。
また、梨はトークイベントにおいて「方法論であるが故に、パターンのバリエーションに限界がある」といったような点にも言及していました。
つまり「現実っぽくないといけない」ので、構成や展開、そして終わらせ方が限られてしまうのです。
そういった中でも、本作の特徴は、それこそ「モキュメンタリー」の元祖である映画を題材としていることでしょう。
メタ的な視点でリアリティを出すというのは常套手段ですが、「モキュメンタリーホラー映画のモキュメンタリーホラー小説」というのが面白い。
このあたりはもう、最初にやったもん勝ちです。
他にも思いついたり先に書いた人がいるかもしれませんが、これだけの完成度で脚光を浴びているのは本作が初と言って差し支えないはず。
自分もこのように映画や小説の感想ブログを書いているわけなので、他人事ではない面白さも感じました。
ホラー映画も小説も好きな身としては、こんな小説も書ける才能には羨望も抱きます。
ちなみに、本作にも出てくる「MOJIの映画レビュー」というブログは実在していました。
そのあたりの抜かりなさも憎い。
ただ、残念ながら作中に出てきた『ファウンド・フッテージ』という映画のレビュー記事などは実在しませんでした。
そのあたりを実在させておいてもさらに虚実入り乱れて面白そうでしたが、実際の映画レビューサイトとして機能しているブログに実在しない作品の記事があったら、それはそれでブログだけ読んでいる人が混乱しますかね。
全体的に、ブログやメールの文章だけで進んでいくので読みやすく、このタイプのモキュメンタリーホラーはすべてそうですが、普段小説など読まない層にも取っつきやすいでしょう。
「白痩神」などオリジナルの概念も、設定がそこまで深掘りされているわけではありませんが、とてもわかりやすく楽しめました。
一方、これは仕方ありませんが、ホラー小説やモキュメンタリーに多く触れていると、物足りなさは否めません。
上述した通りモキュメンタリーの自由度は限られているので、多く読んでいたらマンネリ化してくるのは必然で、読者側の問題です。
小説好きは放っておいても勝手に読むので、間口の広い作品はとても大事だと思っています。
全体的に読みやすく先が気になるのですが、肝心の後半、竹垣村に行ってからの緊張感がいまいちだった点が、もったいない失速感を抱いてしまいました。
映像だとダイレクトに臨場感を感じやすいですが、文章のモキュメンタリ―でライブ感ある恐怖を演出する難しさを痛感させられます。
メッセージのやり取りというのはリアルタイム感を演出するには良いのですが、いかんせん丁寧な説明口調感が強すぎて、ほとんど緊迫を感じられませんでした。
「白痩神と死人たちが境内を近づいてきます。砂利を踏む、ガチャガチャという音が聞こえます。どうやらもう、逃げ場はなさそうです」あたりなんてもう、そんな砂利の音まで説明している場合じゃないだろう感が半端じゃありません。
しかし、このあたりは映画でも「切迫した状況にもかかわらず撮影を止めない問題」としてありますし、モキュメンタリーの難しいところでもあり、突っ込むのは野暮なポイントでもあります。
ホラー小説でもラヴクラフトの「窓に!窓に!」を例として「そんな状況で書き続けるか?」という指摘は古来なされており、もはや様式美として受け入れるのが当たり前ではありますが、それでもさすがに必要以上に丁寧すぎる文章が、危機感を削いでしまっているように感じられてしまいました。
とはいえ、リアルさ重視だったら(そもそも逐一メールなんて送ってる場合じゃないというのは一旦置いておいて)「準備できた!やります!」ぐらいになりそうですが、あまり端折りすぎても状況がいまいちわからなくなりますし、バランスがとても難しそう。
ただ、こういうアーカイブ系のモキュメンタリーでライブ感ある怖さを演出しようというチャレンジは、非常に好印象でした。
最後の「実はSUZUさんが男子中学生だった」という小ネタは、無理やりミステリィ要素をねじ込んだような感じがあり、個人的にはちょっと蛇足に感じてしまいました。
性別誤認はX(Twitter)なんかをやっているとあるあるですが、まぁ「SUZU」の名前で一人称が「私」、かつあの文章だったら、女性でイメージされるのは自然なようにも。
「無理やり」と感じてしまったのは、男子中学生だったというトリックの必要性があまりなかったからです。
「身体が軽かったので助けられた」という救出シーンには活かされましたし、別に必要性なくこういった要素を織り交ぜること自体は全然良いのですが、男子中学生であることによって逆にやや引っ掛かるポイントが増えてしまっていたのが気になりました。
3月14日はまだ春休み前の平日だろうけれど学校どうしたんだろうとか、中学生が1人で4時間かけて他県の廃村に行くかなとか。
まぁこのあたりは、不登校だったのかもしれないとか、寛容な親だったのかもしれないとか、命が懸かっていたので何でもするだろうとか、矛盾とまでは言えません。
ただ、中学生を連れ回したら同意の上でも未成年誘拐になり得るので、送り届けたMOJIさんが無事だったことを祈ります(無事でしたが)。
終盤も思ったよりあっさり儀式が成功してハッピーエンドで、登場人物たちの切り替えも早かったので、少々拍子抜けかつ置いてけぼりでした。
あれだけの大立ち回りをしておいて「SUZUさんを家まで送り届けてから、NOBODY Inc. へ向かおうと思います。もしよかったら、ビールでも一杯飲みましょう」というMOJIさん、逞しすぎます。
名古屋に着くの、深夜になりそうなのに。
そもそも「臭い汁」とか浴びまくったり、髪の毛に蛆虫がついたりしてたのに。
終わり方は、まぁあれしかないですよねという終わり方で、そこがモキュメンタリーの苦しさでしょうか。
予想を上回る展開はありませんでしたが、良くも悪くも堅実丁寧で、気軽に楽しめる1作でした。
考察:『ファウンド・フッテージ』は何だったのか?(ネタバレあり)
モキュメンタリーというのは、細かく詰めれば詰めるほど野暮にしかなりません。
本作は特に、考察する余白や深みのある作品ではありませんが、それを承知の上で、細かいポイントを少しだけ検討してみたいと思います。
『ファウンド・フッテージ』は何だったのか?
呪われた映画『ファウンド・フッテージ』。
そもそもこの作品の設定自体面白かったですが、もちろん架空の作品です。
この作品は結局、プロデューサーの大森昇と監督の北原満が企画したプロジェクトで間違いないでしょう。
大森昇は「知人から託された。自分は何も知らない」と言って公開していましたが、大森も制作段階からプロデューサーとして携わっていたことが、出演者の小川悠生の証言で明かされていました。
出演者名も変えて徹底したモキュメンタリーホラーとして売り出そうとしていた、完全なるフィクションです。
では、この作品に白痩神が映り込んでしまっていたのはなぜかといえば、撮影時に竹垣神社の祭壇を冒涜したからだと考えられます。
つまり、愚か者が神聖な場所を侵害したために呪われてしまったという、コテコテのパターンなのでした。
もちろん、大森昇と北原満以外の出演者の人たちは知らなかったと思うので、かわいそうでしかありません。
白痩神あれこれ
死体の神格化である白痩神は「見るなの禁(タブー)」に基づいており、白痩神を見る=認識する=認識されることによって呪われてしまうようです。
そこからは「だるまさんが転んだ」システムで、見つめていれば止まりますが、目を背けると近づかれて死の世界へと連れ込まれてしまうようでした。
ちょっと乙一『シライサン』に似てるかも。
この白痩神の設定もなかなか面白く、映画を観る際に「白い男が見えたら嫌だな」とちらっとでも思わせる時点で勝っているでしょう。
たとえ白痩神じゃなくても、白い全裸男性が見えたら嫌すぎます。
それはさておき、通常「見るなのタブー」は、「見てはいけない」と言われたのに見てしまったときに発動します。
その点『ファウンド・フッテージ』に出てくる白瘦神は、どちらかと言うと自分から姿を現しておいて「おい、俺のこと見ただろ!見たよな!」と言いがかりをつけて呪ってくる当たり屋体質で、タチが悪い神であると言えるでしょう。
というのはちょっと冗談で、観客にとっては当たり屋によるもらい事故としか感じられませんが、そもそもが北原満らが白痩神の聖域を侵し、映画が依代と化したことに起因しています。
しっかり報いは受けましたが、罪深きはやはり大森昇と北原満なのでした。
呪いの発動条件ははっきりしませんでしたが、「白痩神を見てしまったら」であった可能性が高いでしょうか。
一度目撃してしまえば、その後は気がつかなくても「目を背けている」扱いで近づかれてしまうようでした。
最初のときに「見えていたはずなのに気づかなかった」パターン、つまりは『ファウンド・フッテージ』を観たけれど白痩神を目撃していない人たちはどうなのかは、わかりません。
そもそも、見落としただけなのか、一部の人にしか見えない存在だったのかも不明。
後者だとしたら、少なくとも本作で描かれている限りでは見えてしまう条件などはなさそうだったので、かわいそうでもありました。
そして、『ファウンド・フッテージ2』へ……
『ファウンド・フッテージ』により解放された白痩神と黄泉の国は、MOJIとSUZUの行動力と運の良さによって再び封印されました。
しかし、MOJIのあからさまに思わせぶりな「ビデオカメラ落としたけどまぁいいよね」という発言の伏線が見事に回収され、『ファウンド・フッテージ2』が公開へ……。
1作目となる『ファウンド・フッテージ』が呪われていた、というより白痩神の依代と化していたのは、撮影隊が聖域を侵し白痩神を冒涜したからだろうと上述しました。
しかし今回は、決して白痩神を冒涜して撮影された映像ではありません。
それなのに、今回もまた白痩神の解放を許してしまったようです。
考えられるのは、封印前に撮影していたわけなので、白痩神が映ってしまっていたことに起因しているのでしょうか。
映り込んだというか、撃退するためにがっつりカメラのレンズを向けていましたからね。
つまり、また白痩神が映っている映像を観た人がいるから、白痩神が当たり屋のごとく再来したことになります。
儀式の直後でしたが、しっかりとした儀式ではなかったので、封印の力も弱かったのでしょうか。
封印されたと思った途端解放されたわけなので、白痩神も「マジかよラッキー」と歓喜したことでしょう。
思えば、白痩神を映したビデオカメラ映像が再び依代となる可能性は、十分に予測できたはずです。
疲れ切っていて気が進まなかったのはとてもよくわかりますが、取りに戻らなかったことですべての努力が無駄になってしまったので、MOJIの大きな落ち度となってしまいました。
MOJIとSUZUが助かったという意味では、無駄とは言い切れないかもしれません。
しかし、たとえMOJIとSUZUが『ファウンド・フッテージ2』を観なかったとしても、以前狙われていた2人がまだターゲットである可能性も否定できません。
そうなると、それこそすべてが無に帰します。
殺人鬼にトドメを刺さず窮地に陥るのがスラッシャーホラーの定番ですが、本作もまた、最後の詰めが甘いというホラー登場人物あるあるを踏襲しているのでした。
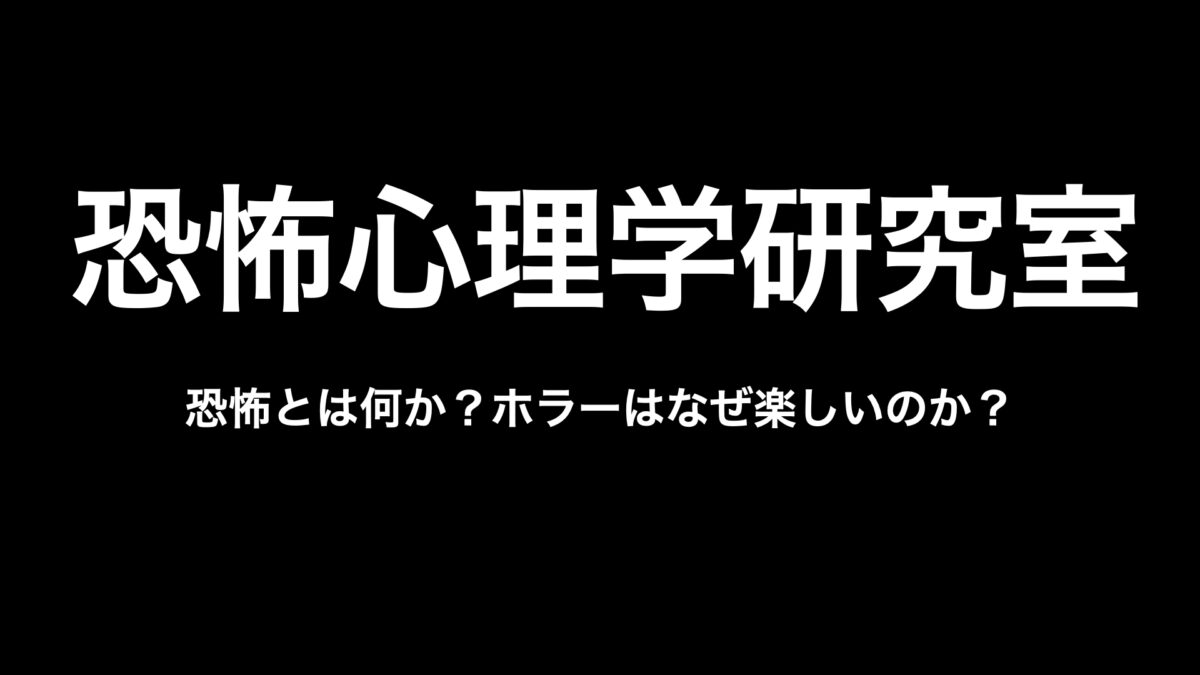

コメント