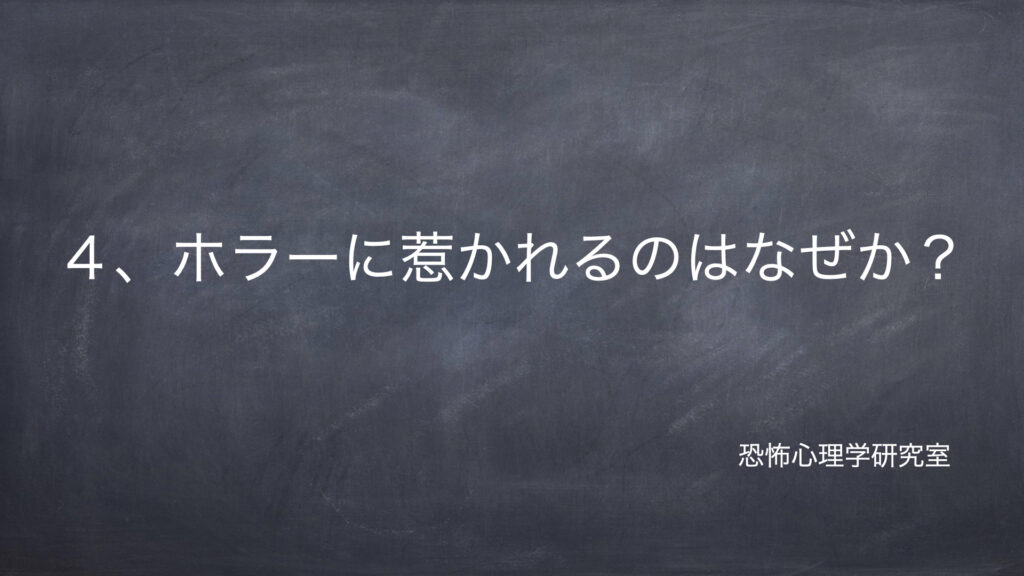
前回までは主に「恐怖とは何か?」という定義的なテーマを軸に進めてきましたが、何だが堅苦しくなってきた気がするので、今回は早くも「ホラーに惹かれるのはなぜか?」という興味深い、しかし大きなテーマを考えてみたいと思います。
恐怖という感情は、基本的には好ましくなく、回避したいものであるはずです。
それなのになぜ、わざわざ恐怖を感じるホラー映画やホラー小説、ホラーゲーム、あるいはお化け屋敷などに人は惹かれるのでしょうか。
結論から言えば「恐怖自体を楽しんでいる」ということになるのですが、そのメカニズムを見ていきましょう。
ホラーのパラドクス
「恐怖が忌避されるものであるならば、なぜホラーフィクションを鑑賞する人が絶えないのか」という矛盾について、アメリカの哲学者であるノエル・キャロル(Noël Carrol)は『ホラーの哲学――フィクションと感情をめぐるパラドックス』(2022年, 原著は1990年)という著作において「ホラーのパラドクス」と名づけました。
有名な名著ながら古めの書籍であるため詳細は省きますが、キャロルの大雑把な結論は「ホラーフィクションにおけるプロットの快が、恐怖や嫌悪を上回る」というものです。
つまり、無事に生き延びたり、怪異の正体を明らかにしたり、モンスターを打ち倒したりすることによることによって、恐怖を上回る認知的な快が得られると述べます。
当然ながら、このシンプルな説は批判にも晒されます。
そういうパターンもあるでしょうが、それだけですべて説明できるものでもありません。
どれだけプロットが見事でも、「話は面白かったけれど、怖くなかったからホラーとしてはイマイチ」といった批評はあり得ます。
その場合、明らかに求められているものは「恐怖」です。
とはいえ、この「ホラーのパラドクス」という問題提起がその後の議論を生んだので、重要な著作であると言えるでしょう。
同時活性化モデル
その後、様々な議論や説が生まれますが、それらをまとめ、新たに重要な説を発見・提唱したのが、消費者心理を研究するAndrade & Cohen(2007)です。
彼らは、以下の3つのモデルにまとめています。
①強度モデル(intensity models)
これはZuckerman(1994)による理論がベースで、簡単に言えば「恐怖の感じ方には個人差がある」ということです。
怖がりな人もいれば、怖がらない人もいる。
この前提は当たり前といえば当たり前ですが、その上で、「怖がらない人たちは恐怖などのネガティブな刺激がポジティブに解釈されるため、刺激を求める」と説明されます。
逆に言えば、ネガティブな刺激への耐性が低い人たちはホラーを避けるということになります。
ただ、この説も、「怖くないなら何が刺激となって求めているのか?」という穴があります。
②余波モデル(aftermath models)
これはZillman(1971)やSolomon(1980)らの研究をまとめたモデルで、「恐怖が生じたあとに楽しさが遅れて発生する」という説です。
緊張の糸が張りつめた本編を観終わったあとのカタルシスや安心感を求めて、ホラーフィクションを求める、と説明します。
キャロルの説もここに含まれるでしょう。
この説では、怖がりな人ほど観終わったあとの安堵感も強くなるのでホラーを求める傾向も強くなるはず、ということになりますが、実際は極度に怖がりな人はホラーフィクションも好まない、という矛盾が生じます。
また、人々がホラーを求める理由として「カタルシスが得られるから」という説をよく見かけますが、個人的にはこの解釈は微妙です。
ただ自分が実感できないから、というだけかもしれませんが、潜在的にでも、ホラーでカタルシスを感じた!というのはあまり聞かないような。
カタルシスであれば、爽快なアクションやどんでん返しのミステリィなどの方がよほど強いように感じます。
③同時活性化モデル(coactivation-based model)
以上の2つのモデルは「恐怖と楽しみは同時に発生しない」という前提のモデルで、長らくこの前提をもとに議論が重ねられてきました。
しかし、Andrade & Cohenはこのスタンスを批判し、彼らが明らかにしたのは「恐怖と楽しさは同時に発生する」という事実でした。
彼らの実験においては、ホラー映画好きは怖さを感じていないのではなくちゃんと怖がっていた上、作品の中で恐怖を感じるシーンほど楽しさを感じていました。
シンプルに、恐怖こそが楽しみとなっているのです。
怖いから楽しいのです。
これによってホラーのパラドクスも解消され、現在でも幅広く支持されているモデルです。
また、この楽しさを伴う恐怖のことを「娯楽的恐怖(Recreational Fear)」と言います。
なぜ恐怖とともに楽しさが生まれるのか?
ホラーのパラドクスは解消されました。
ああだこうだと言うまでもなく、怖さそのものが楽しいのです。
そうなると次の疑問は、「ではなぜ恐怖と楽しさが同時に発生するのか?」というものでしょう。
この点は、脳のメカニズムが影響していると考えられます。
恐怖を感じたときには、アドレナリンやエンドルフィン、ドーパミンといった神経伝達物質が放出されることが明らかになっています。
どれも何となく聞いたことがある方が多いかと思いますが、アドレナリンは元気になるやつです(超雑)。
ストレスがかかるとアドレナリンが放出され、闘争・逃走反応(Fight-or-Flight Response)を引き起こします。
身体が活性化し、心拍数や血圧の上昇などにより、戦うか逃げるか、といったモードになるのです。
痛みも感じづらくなります。
エンドルフィンは、モルヒネにも似て「脳内麻薬」とも呼ばれるほど、多幸感をもたらす神経伝達物質です。
恐怖を感じたときになぜエンドルフィンが放出されるかといえば、痛みを感じにくくさせたり、恐怖心を消し去るためです。
恐怖の感情は生存のために必要ですが、怖くて動けなくなってしまっては元も子もありません。
逃げるにせよ戦うにせよ、問題に対処するためにエンドルフィンやアドレナリンが放出されるのです。
よく耳にするであろうドーパミンも同じで、幸せホルモンとも呼ばれるドーパミンは、主に報酬系に関連しています。
成功したり達成感を得た際にドバドバでるやつですね(超雑)。
恐怖反応の調節や恐怖記憶の形成に関与すると言われています。
このように、脳が恐怖を感じた際には、カウンターとして「快」の神経も活動しているのです。
これが恐怖と同時に楽しさを感じるメカニズムであると考えられます。
保護フレーム
ただ、それだけであれば、人間はみな喜んで恐怖を求めるということになってしまいます。
しかし実際は、現実の恐怖はやはり忌避したいものですし、フィクションであってもホラーが嫌いな人も少なくありません。
それはなぜでしょうか。
上述した通り、「恐怖に対する耐性には個人差がある」というのが理由の一つとして考えられます。
ストレスに強い人弱い人、痛みに強い人弱い人がいるように、恐怖への耐性が高い人低い人がいるのです。
プラスして、Apter(1992, 2007)が提唱した「保護フレーム」という概念があります。
これは、本来はネガティブな感情を引き起こすはずの行為を受け入れることができるようになる認知的なメカニズムです。
つまり、「捉え方によっては、本来は嫌なことも受け入れられるようになる」ということです。
これも大きくは3つのフレームがあり、それぞれ①自信フレーム、②安全フレーム、③分離フレームと呼ばれています。
以下、それぞれを見ていきましょう。
①自信フレーム
自信フレームは、危険に直面したときに「対処できる」という自信があると強まります。
ライオンを目の前にすれば恐怖ですが、ねじ伏せられるはずだと思うほど腕力に自信があったり、銃などの武器を持っていれば恐怖は薄まります。
破産する恐れのあるギャンブルだったり、危険な行為に挑む際にも、自分ならできるという自信が強ければ、恐怖心は薄まりスリルを楽しむことができるのです。
②安全フレーム
このフレームは、「危険から十分な距離を置いている」という意識があると強まります。
ライオンが檻の中にいれば恐怖心は薄まるでしょう。
しっかりとしたルールのある格闘技であったり、安全が確保されているバンジージャンプやジェットコースターなどを楽しめるのは、安全フレームによるものです。
③分離フレーム
これは現実世界から自分の認識を分離することで「保護されている」という認識の枠組みが生じるものです。
これがまさに「フィクションであるからこそホラーを楽しめる」フレームとなりますが、細かくはさらに3つの下位分類があります。
a、自己代用
これは「危険に陥っているのは自分ではない」と誤魔化すような心理です。
ライオンが目の前にいて襲い掛かってきたら絶望しかありませんが、最後の手段として笑って誤魔化すようなものです。
虐待されている自分をまるで他人事のように客観的に眺めるようになるのも、自己代用が働いて自分を守ろうとしているのだと考えられます。
b、空想
これは「危険は架空のものだという認識の枠組み」です。
テレビの中のライオンは怖くありません。
同様に、実際に自分の目の前で包丁を持った人が暴れているのと、ホラー映画の中で殺人鬼が暴れているのとでは、恐怖の度合いは異なります。
「フィクションだから恐怖心が低下する」というのがまさにこれです。
c、追憶
これは「危険は過去に生じたものだという認識の枠組み」です。
ライオンが襲って来ずに立ち去り、無事に帰ってから恐怖心が薄れ、武勇伝のように語ったりするようなものです。
保護フレームまとめ
以上のように、恐怖を感じる状況に対して、保護フレームが1つあるいは複数働くと、恐怖心が薄れて、恐怖に伴う快を楽しむ余裕が生まれます。
ホラーフィクションに関しては、やはり「フィクションであることを理解している」という分離フレームの影響が大きいでしょう。
ホラー映画よりもお化け屋敷の方が怖く感じるのは、実際に自分が直面する分、分離フレームが弱まるからであると考えられます。
逆に、本物のように感じるモキュメンタリーホラー映画の方がお化け屋敷より怖ければ、リアルさによって分離フレームが弱まっていたり、お化け屋敷に対して「所詮作り物だろ」と自信フレームや安全フレームが強まっていることが考えられます。
このように、何に対してどのように保護フレームが働くかどうかも、個人によって異なってきます。
ホラーフィクションを楽しめるのは、分離フレームの機能だけとは限りません。
吉岡(2023)は、子どもたちが学校の怪談を楽しんでいる現象を取り上げて、作り話とは断言できない=分離フレームが弱かったとしても、怪異が生じる場所や時間帯を避けたり(安全フレーム)、「~~と3回唱えれば助かる」といったような対処法を知っていること(自信フレーム)等によって楽しめるようになっている可能性を指摘しています。
まとめ:およびその他の要因
ここまでをまとめると、まず基本的な人間のメカニズムとして、恐怖と同時に快感情も湧き上がるようになっています。
ここに保護フレームが加わり、恐怖心が薄まることによって、恐怖に伴う快の部分を楽しむことができるようになるのです。
それは「怖くない」ということではなく、「楽しめる怖さ」になるということです。
ホラーフィクションであれば、あくまでも「フィクションである」という事実を意識的にも無意識的にも認識しているという前提が大切になってきます。
フィクションの中で起こっていることが現実として自分の身に降りかかれば、やはり恐怖しか感じないでしょう。
ただし、恐怖の耐性には個人差がありますし、個人の信念によっても変わってきます。
フィクションとわかっていても恐怖が上回る人もいますし、幽霊の存在を信じて常に恐れていれば、たとえフィクションでも恐怖度は高まります。
当然ながら、ホラーが好きだからといって、常に恐怖による楽しさだけを求めているとは限りません。
グロいシーンが好きだったり、個性溢れる殺人鬼に魅了されていたり、ストーリーに引き込まれていたりすることもあります。
ただシンプルに、ごちゃごちゃ理由をつけなくとも、怖いから楽しいということがあり得るのです。
八坂(2025)は構成主義的情動理論という理論に基づいて、キャロルの議論を捉え直しています。
構成主義的情動理論の詳細は省きますが、八坂は、現実の恐怖とフィクションの恐怖を分け、フィクションの恐怖に対しては、快を伴った学習がなされてきた人がいることを指摘しています。
つまり、上述した神経伝達物質以外にも、ホラーを観て「楽しかった!」という体験や、すっきりするようなポジティブな体験が積み重なれば、ホラーそのものにプラスの価値を見出すようになっていきます。
好きだから自分から求めてさらに好きになっていく、というスパイラルが生まれます。
いわゆる「ホラー好き」の状態ですね。
逆に、怖いだけで全然楽しめず、観終わったあとも怖すぎてびくびくしてまうような体験しか得られなければ、ホラー嫌いになっていくでしょう。
他に「怖いものに惹かれる」要素としては、人間の好奇心も影響していると考えられます。
いわゆる「怖いもの見たさ」ですが、人間の脳はポジティブな情報よりもネガティブな情報により反応するようにできています。
これは、情報を仕入れて安全を確保するためです。
大きな地震や事件、パンデミックなどがあると、ついついニュースやSNSばかり見てしまうような経験をされた方も多いでしょう。
怖いと思いながら惹かれるのも、同じく好奇心や探求心のような「知りたい、理解したい」という心理も影響しているはずです。
そこに、保護フレームが加わることによって恐怖心が低下し、フィクションとしてのエンタメを楽しめる余地が生まれ、その楽しさを学習した状態が、ホラーを楽しみ求めるメカニズムであると考えられます。
他にホラーが好きな理由としては、「生きている実感が得られる」といった言葉もよく聞きます。
現実に対して不全感を抱いている方が多い印象ですが、このような場合は、スリルを求めて危険なことをするタイプに近いでしょう。
上述した通り、恐怖を感じると快楽物質も放出されます。
日常生活ではあまり刺激や楽しさを感じられなくなっていると、非日常に刺激を求めるようになっていくのです。
やや不健康でいわゆる「病んでいる」状態とも言えますが、そのような人たちを癒す効果も、ホラーフィクションは包含しているのです。
馴化:怖さへの慣れ
ただし、「ホラーに非日常や生きている実感を求める」という傾向が極端になりすぎると、依存に近いような状態となります。
そうなれば、必然的に副作用が生じてきてしまいます。
SNSなどでたまに「ホラー不感症になってしまった」などの表現を見かけることがあります(この表現はあまり好きではないですが)。
「ホラーを観すぎて怖さを感じなくなってしまっている状態」を指すようです。
怖さに対して「慣れ」「麻痺」してしまった状態です。
この現象は、心理学用語では「馴化」と言います。
脳は、同じ刺激が繰り返されると慣れが生じ、反応が徐々に弱くなっていくのです。
このような状態になると、ホラー映画を観たりしてもあまり怖く感じなくなってしまいます。
ホラー映画の楽しさが恐怖にあるとすれば、「怖さを感じない=楽しさも感じなくなってしまう」ということになります。
もちろん、馴化したからと言ってホラーフィクションが即つまらなくなるわけではありません。
上述した通り、怖さ以外にも魅力的な要素はたくさんあるからです。
ただ、本質的な魅力は半減してしまうと言えるでしょう。
それでもなぜ、ホラーを観続ける人がいるのか?
それも要因は多々あるでしょうが、「自分はホラーが好きだから」という認識の影響は意外と大きいような気がします。
「自分が好きなもの」というのは、自分のアイデンティティを形成する一部となります。
「好きだから観なければいけない」とまで言うのは大袈裟にしても、似たような状態になっている方も少なくはないのではないでしょうか。
あるいは、SNSなどに感想をアップしていると、それ自体が目的と化してしまうようなこともあります。
ホラー好きアカウントを自認しているので、観なきゃいけない、読まなきゃいけない。
そしてそれをアップしないといけない。
半ば義務化しているような状態です。
馴化から脱却するには、一旦は刺激から離れることが必要です。
「最近のホラーはつまらない」と文句ばかり言っているような人は、もしかするとホラーばかり観すぎて自身の感覚が馴化してしまっているのかもしれません。
おそらくホラー好きな場合、もともと恐怖をほとんど感じない人はあまりいないはずです。
元来恐怖を感じないのであれば、そもそもホラーに魅力を感じないはず。
なので、少なくとも幼少期は怖がりだった方が多いはずなので、たまには距離を置いてみると、改めてホラーの魅力を思い出すことができるかもしれません。
余談:脳の仕組みとミステリィとの相性
最後に少し余談ですが、脳の仕組みと、ホラーとミステリィの相性について。
近年、特にホラー小説界ではモキュメンタリーホラーブームとも言われていますが、ホラーフィクション作品を観たり読んだりしている最中にあまりに考えることが多すぎると、恐怖心が低下してしまう可能性もあります。
理性的に考えすぎると、恐怖は薄まっていくのです。
これは、脳の仕組みにも関連しています。
恐怖の情動を司るのは偏桃体という、脳の原始的な部分である大脳辺縁系に位置する部位です。
一方、理性や思考を司るのは、一番外側の大脳皮質という部分。
大脳皮質は、大脳辺縁系を抑制するために生まれてきました。
それによって、人間は恐怖心を抑え込んで冷静に対処することができるようになったのです。
そのため、理性的に考える方にリソースを割くと、当然ながら恐怖心は低下していきます。
謎解きも同じで、ホラーゲームやリアル脱出ゲーム系には謎解きがつきものですが、あれも恐怖心を低下させてしまうリスクのある要素となります。
しかし逆に、大脳皮質を活かした恐怖というのもあります。
観終わったり読み終わったあとにあれやこれやと考察しているうちに、意外な要素が繋がってゾッとする、といった体験はモキュメンタリーホラーの醍醐味でしょう。
わからないと、知りたくなる、理解したくなる、はっきりさせたくなる。
それによって新しい恐怖が生まれる。
それこそがホラーとミステリィの相性が良い要因であると考えられ、分離フレームが低下しよりお手軽にリアルめな恐怖を味わえる点が、モキュメンタリーホラーの人気を支えているのだと考えられます。
モキュメンタリーホラーの人気は近年に限った話ではなく、怪談や都市伝説、いわゆる「洒落怖」などのネットロアはずっと根強い人気を誇っているのです。
引用・参考文献
Andrade, E. B., & Cohen, J. B., 2007, On the consumption of negative feelings. Journal of Consumer Research, 34(3), 283–300.
Apter, M. J., 1992, The Dangerous Edge: The Psychology of Excitement, The Free Press.
Apter, M. J., 2007, Danger: Our quest for excitement. Oxford: Oneworld.
Carroll, Noel., 1990, The Philosophy of Horror. 1st ed. New York: Routledge.(=2022, 高田敦史訳『ホラーの哲学:フィクションと感情をめぐるパラドックス』 フィルムアート社)
Solomon, R. L., 1980, The opponent-process theory of acquired motivation: The costs of pleasure and the benefits of pain. American Psychologist, 35(8), 691–712.
八坂隆広, 2025, 「「アートホラー」はもともと快い : ホラーのパラドクスを構成主義的情動理論で解決する」 『美学芸術学論集』 19, 58-87
吉岡一志, 2023, 「「学校の怪談」ブームの社会的背景:恐怖のパラドックスの心理学的理解に基づいて」 『山口県立大学学術情報:基盤教育紀要』 16, 97-106, 2023-03-31
Zillmann, D., 1971, Excitation transfer in communication-mediated aggressive behavior. Journal of Experimental Social Psychology, 7(4), 419–434.
Zuckerman, M., 1994, Behavioral expressions and biosocial bases of sensation seeking. Cambridge University Press.
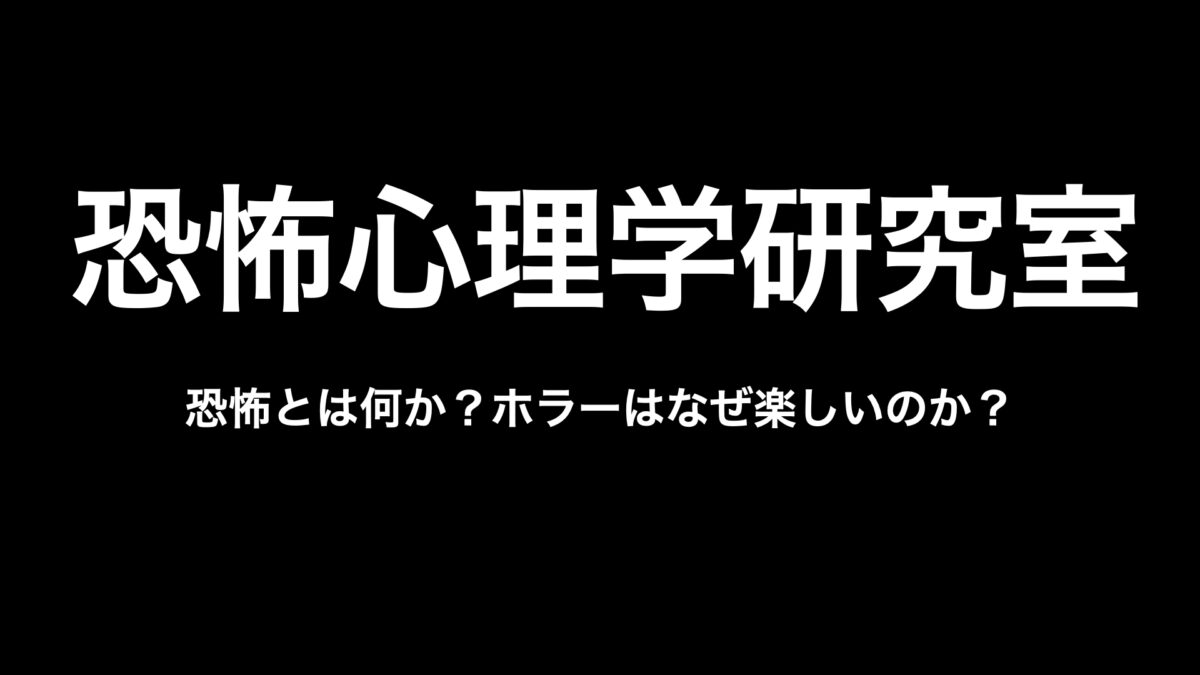
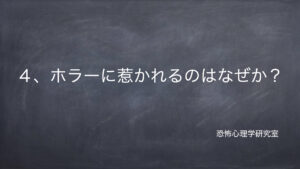
コメント