
作品の概要と感想(ネタバレあり)
タイトル:再生 角川ホラー文庫セレクション
編集:朝宮運河
出版社:KADOKAWA
発売日:2021年2月25日
角川ホラー文庫の中から、時代を超えて読み継がれる名作を厳選収録したベストセレクション。
収録作は以下の通り。
綾辻行人「再生」(『亀裂』『眼球綺譚』)
鈴木光司「夢の島クルーズ」(『仄暗い水の底から』)
井上雅彦「よけいなものが」(『怪奇幻想短編集 異形博覧会』)
福澤徹三「五月の陥穽」(『怪談歳時記 12か月の悪夢』)
今邑彩「鳥の巣」(『惨劇で祝う五つの記念日 かなわぬ想い』)
岩井志麻子「依って件の如し」(『ぼっけえ、きょうてえ』)
小池真理子「ゾフィーの手袋」(『異形のものたち』)
澤村伊智 「学校は死の匂い」(『などらきの首』)
ホラー小説家オールスターズなアンソロジー。
ホラー小説の入門にも最適な1作です。
濱口真央のイラストによる表紙もとても好き。
初読みの作家もいれば既読の作品もありましたが、選りすぐられているだけあり、改めて読んでもその完成度の高さを痛感します。
また、色々な作家の異なる作風の中で読むと、新しい個性も感じることができました。
本作を全部読み終わってまず思ったのは、ホラーと言っても幅広いな、という点です。
当たり前過ぎる感想ではありますが、このような全部異なる作家によるアンソロジーだと、その印象が際立ちます。
また、ホラーと短編というのは相性が良い、という点も再認識。
個人的に、どちらか選べと言われたら短編より長編派なのですが、ホラーで長編というのは、緊張感や恐怖感を持続させるのが難しい印象があります。
その点、古来伝わる怪談なども短編集のようなものですし、恐怖は短くても十分に表現できます。
むしろ、短いほど洗練されて恐怖感が際立つことも少なくなりません。
このブログ、「『恐怖』心理学研究所」と銘打っており、「恐怖」という感情についても考察していこうと思いながらまだできていないのですが、恐怖について改めて考える上でも、『再生 角川ホラーセレクション』は非常に示唆的な作品でした。
個々の作品の簡単な感想と考察(ネタバレあり)
アンソロジーなのであまり内容を考察したり多くを語るつもりはありませんが、個々の感想を少しだけ。
綾辻行人「再生」
これはもう、何も言えません。
ホラーやミステリィ小説にハマり始めた中学生頃、一番触れていた作家が綾辻行人なので、もはや客観的な評価が不可能です。
という個人語りはさておいても、「再生」に漂う幻想的かつじめじめした雰囲気は、まさに綾辻行人の真骨頂。
本格ミステリィは言うまでもありませんが、怪奇幻想、そして異形を描かせたら右に出る者はいないと思っています。
その幻想性が、時代が変わっても古さを感じさせない神秘性を保っています。
色褪せない完成度の高さで、表題作に選ばれたのも嬉しい1作。
好き。
鈴木光司「夢の島クルーズ」
『リング』を生み出したホラーの名手、鈴木光司。
こちらも既読作品でしたが、内容はすっかり忘れてしまっていました。
表題作が映画化された『仄暗い水の底から』は、もはや懐かしい。
この作品の特徴は、とにかく主人公の榎吉正幸が、不可解な現象に直接的には一切触れないところでしょう。
「ヨットの下にしがみついた子どもの死体を見た」と話し、極端なほどに怯えるヨットの持ち主・牛島。
結局、それが真実だったのか、榎吉が推理したように靴を見たことによる牛島の幻覚だったのか、はっきりしません。
その曖昧性が、榎吉の、つまりは読者の想像力をかき立てます。
「曖昧な状態に恐怖を感じる」というのは様々な作品の考察で書いてきましたが、「夢の島クルーズ」はそれを地でいく作品です。
ヨットからテトラポッドまで泳ぐ間の、こちらまで伝わってくるかのようなぞわぞわ感は、圧倒的な表現力の賜物。
最後まで榎吉には何も起こらなかったからこそ、岸に辿り着いたのに安心よりも不安感を残す余韻が生じたのだと思います。
どこかでちょっとでも子どもの死体が出てきたら、逆にここまでの作品にはなっていなかったはず。
もはやお手本のような素晴らしさでした。
すぐそこに陸が、街が見えているのに孤立している、という状況作りも秀逸。
井上雅彦「よけいなものが」
これまた短編小説のお手本のような作品でした。
シンプルイズベスト。
発想一つで、小説や文字による表現の無限の可能性を感じます。
単発で読むと物足りなさも感じるかもしれませんが、このアンソロジーに含まれているからこそ異彩を放ち、輝いていました。
とても印象に残る1作。
福澤徹三「五月の陥穽」
ホラーとギャグは紙一重。
真面目にホラーをやってギャグになってしまっている、というのはよくあることですが、「五月の陥穽」はまさにその逆で、真面目にギャグをやってホラーになっている作品です。
いや、もう、馬鹿。
ほんと馬鹿。
ビルの屋上から落ちてビルとビルの間に挟まって、抜け出せないまま死亡し、誰にも見つからずにミイラ化。
そんなことあります?
あるんです。
と、思わせるだけの筆力でした。
主人公の石黒が、「いやいやこんなのあり得ないでしょ」と読者と同じ目線で状況を捉えている点が、絶妙なリアリティを保っていたように思いました。
「いや、あり得ないけど、もし本当にこんな状況になったらどうしよう」と読者に一瞬でも想像させるだけで勝っています。
こんな馬鹿な死に方をしたくない。
そんな思いを抱きながら死んでいくのはかなりの恐怖なんだな、ということも痛感しました。
今邑彩「鳥の巣」
何となくいきなりトリッキーな作品が続いた印象の中で、とてもストレートなホラーで攻めてきた作品。
この並びだからこそ、スタンダードさが際立っていました。
とはいえ、先の読めない展開はオリジナリティに溢れ、不穏そのもの。
実は主人公は死んでいた、という展開は珍しいものではありませんが、「これは話している相手である浜野和子がおかしくなっているのか?それともやっぱり主人公の佳織が死んでいるのか?」という、人怖系かオカルト系か判断がつかない不安定さが、独特の雰囲気を生み出していました。
シンプルでありながら、恐怖症の対象としても少なくはない鳥の怖さまで織り込まれていたところが面白い。
岩井志麻子「依って件の如し」
もう圧倒的。
世界観と文章力が圧巻です。
個人的に、想像力が乏しいため時代小説がそこそこ苦手なのですが、それでも読み進めてしまう技巧と展開はさすがです。
これもまた、結局恐ろしいのは人間なのか?怪物なのか?怨念なのか?
すべてが入り乱れた、ホラーというより怪談と呼ぶに相応しいような1作。
解釈も感じるものも恐怖を抱く部分も、読む人それぞれ異なるでしょう。
恒川光太郎『夜市』もそうでしたが、想像力の乏しい人間を、異なる時代や国、ファンタジーなどの世界に引き込む文章力は、本当に尊敬します。
タイトルのつけ方も、天才か?
時代背景が古いというだけで、不思議な恐怖感がありますよね。
まだまだ未知だらけの世界だったからでしょうか。
小池真理子「ゾフィーの手袋」
悲しみの漂う作品。
ホラーというより、夏目漱石あたりを彷彿とさせるような、文学への近さを感じさせる1作でした。
ホラーとしてのポイントは、ゾフィーの霊の目的がまったくわからないところでしょう。
夫・城之内明が死んでから現れるようになった理由もわからなければ、何を伝えたいのかもわからない。
別に、主人公に何かを伝えたいわけではないのかもしれない。
ただ城之内明が死んだことを悲しんでいただけで、主人公は後ろめたさから勝手に翻弄されていただけなのかもしれません。
この作品の特徴は、カッコで括られた台詞がほとんど出てこないところです。
それがまた、不思議な物語調のリズムを生み出しているように感じました。
澤村伊智 「学校は死の匂い」
最後に控えしは、澤村伊智。
現代のホラー小説界を牽引する1人と表現しても過言ではないでしょう。
テーマも、古典中の古典である「学校の怪談」。
しかし、それを独自の切り口で展開させる巧みさは、さすがの一言。
小学生にしては大人びているのでは、という点が若干引っ掛かりましたが、同じ行動を繰り返す霊の謎を解き明かしていくプロセスは、ミステリィ作品のようでもありました。
人怖系でもありながら、「両手で首が折れた頭を支えている」という霊の行動や、最後には担任の天野と教育実習の佐伯がともに死を迎えるという衝撃的なラストなど、細部まで技巧が行き届いており、様々な恐怖ポイントが織り込まれていました。
ラストまでは心霊ミステリィ的な側面の方が強く、ラストシーンによって一気にホラー作品になっていたような印象です。
追記
恐怖心理学研究室
感想部分で「『恐怖』という感情についても考察していこうと思いながらまだできていない」と書きましたが、始めてみました。

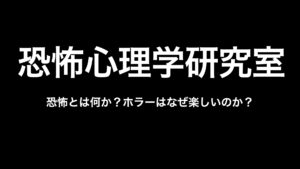

コメント