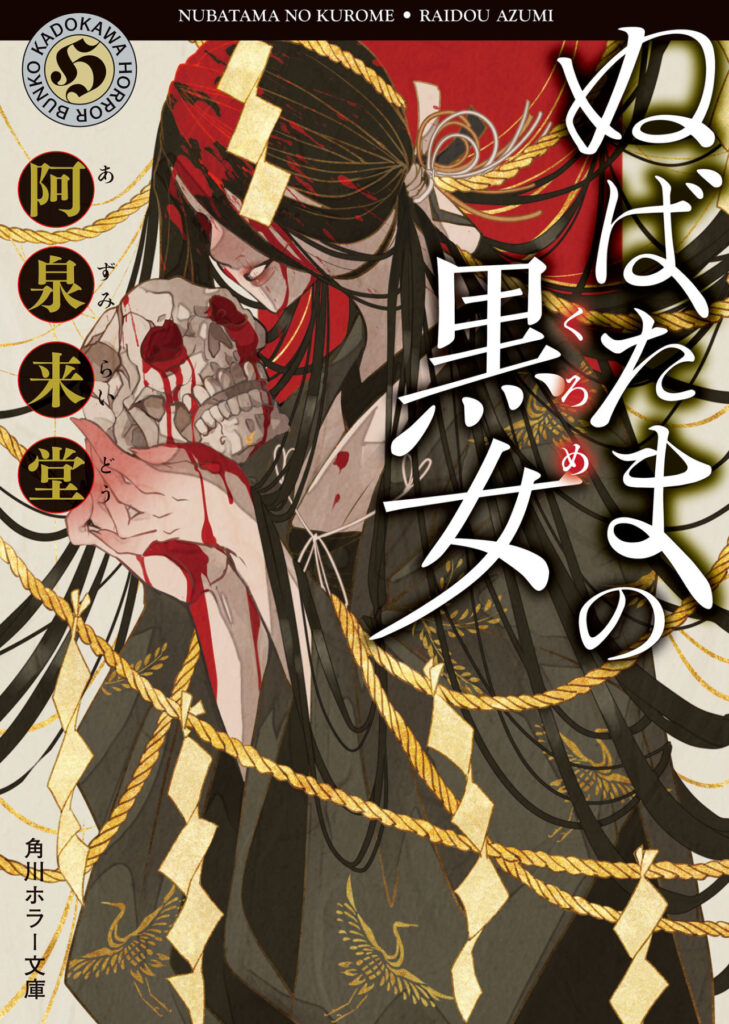
作品の概要と感想(ネタバレあり)
タイトル:ぬばたまの黒女
著者:阿泉来堂
出版社:KADOKAWA
発売日:2021年6月15日
生まれ故郷の村が近隣の町に吸収合併されると知り、12年ぶりに道東地方の寒村、皆方村を訪れた井邑陽介。
妊娠中で情緒不安定の妻から逃げるように里帰りした陽介は、かつての同窓生から、村の精神的シンボルだった神社一族が火事で焼失し、憧れだった少女が亡くなっていたことを告げられる。
さらに焼け跡のそばに建立された新たな神社では全身の骨が折られた死体が発見されるという、壮絶な殺人事件が起こっていた。
深夜、陽介と友人たちは、得体のしれない亡霊が村内を徘徊する光景を目撃し、そして事件は起こった──。
第40回横溝正史ミステリ&ホラー大賞〈読者賞〉受賞作『ナキメサマ』に続く、著者の2作目にしてシリーズ第2弾。
以下、『ナキメサマ』の内容にも少し触れるので、念のためご注意ください。
デビュー作である『ナキメサマ』がとても好きで、まだ読めていませんがその後もかなりの勢いで作品を発表されている、個人的に好きで注目している作家のお一人、阿泉来堂。
『ナキメサマ』を読んだあと、シリーズもすでに全部買ってあるのですが、もったいぶってなかなか読めないという自分の悪い癖が発動していたので、ついに読み始めました。
結果、もはや自分のことなので予想通りでしたが、「もっと早く読めば良かった!」と思うほど、とても好きな作品で楽しめました。
やや過剰なまでに派手に暴れる怪異、そこに織り込まれたミステリィ要素。
怪異ホラー+ミステリィとして完成度の高かった『ナキメサマ』の続編かつ2作目としてかなりのプレッシャーがあったのではないかと推察されますが、しっかりと期待を上回ってきたのはさすがの一言。
ちなみに「ぬばたま」というのはヒオウギという植物の黒くて光沢のある種子のことで、和歌などでは「黒」や「夜」をイメージさせる言葉を導く枕詞となるようです。
おそらくこの作品からシリーズ化が意識されたと思われますが、ホラー作家・那々木悠志郎のキャラも前作に比べてだいぶ深掘りされ、裏辺なる相棒(?)まで登場し、今後のシリーズへの布石もしっかりと埋め込まれていた印象です。
『ナキメサマ』の感想で、那々木のキャラについて「思ったよりキャラが目立たない印象を受けました」と書いたのですが、これはあながち間違っていなかったようで、著者のX(Twitter)で「『ナキメサマ』は当初、那々木先生が中盤で死亡し、生還者がほぼゼロの救いようのない話だった」という初期設定が明かされていました。
相変わらず民俗学を背景とした地方の村で起こる怪異は、前作に負けず劣らずインパクトを残してくれるパワータイプ。
それでいてなお、人間の怖さの方が上と思わせる業の深い村の描写も相変わらずでたまりません。
リアリティ重視よりもエンタメ寄りで、公式に記載されている「ホラーエンタメド直球のどんでん返しホラー第2弾!」という謳い文句がまさにぴったりでした。
『ナキメサマ』の時点で感じていましたが、やや中二病じみたゲームっぽさ、特に『零』シリーズを強く感じる点が、個人的には大好きなポイントだと思っています。
これもおそらく印象としては間違っておらず、著者自身がゲーム好きで、X(Twitter)でも『零』シリーズや『SIREN』シリーズなどのファンであることが言及されていたので、少なからず受け継がれた遺伝子を感じます。
執筆の際にはまさに、『零』シリーズの主題歌のほとんどを手がける天野月子(天野月)の楽曲を流していたらしいですしね。
それもあってか、もしも那々木悠志郎シリーズをメディアミックスするとしたら、今のところ、映画化やアニメ化などよりもゲーム化が一番合っていそうな印象を受けます。
前作から引き続き、ライトで読みやすい文体ですが、惨劇はかなり容赦がなく、それもまた好きなポイントの一つ。
特に、それほど主人公と親しい登場人物が出てこなかった前作に対して、故郷の友人たちが登場し、それがほぼほぼ全滅というのは、なかなかの救いのなさでした。
ミステリィ要素に関しては、すごく苦心したんだろうな、という印象を受けました。
少し強引にねじ込んだ感が否めない部分もありますが、妻=霧絵というのは最後まで気がつけなかったので、お見事。
ただ、『ナキメサマ』同様、叙述トリックとしてはぎりぎりアンフェアでは……?と思ってしまったのもまた正直なところ。
一人称視点なのに「妻」と「霧絵」を呼び分けているのは、叙述トリックメインであれば少し不満を抱いてしまいそうです。
ですが、個人的にはこのシリーズはホラーメインであり、そこにミステリィ要素が組み込まれているととらえています。
ホラー要素のあるミステリィではなく、ミステリィ要素のあるホラー。
それを踏まえると、前作で上がったハードルに正面から挑んだ本作の構成も、十分満足できるものでした。
実際、「妻=霧絵」を理解した上で再読してみても、上手く通る表現が徹底されています。
一つだけ偉そうなことを述べておくと、全体にミステリィ要素を組み込んだがゆえに、登場人物のキャラや動きがパズルの駒のように感じてしまう部分もあった点だけ、少し惜しく感じました。
どんでん返しや「全員が過去に罪を抱えている」という設定が先行していたため、けっこう唐突に感じてしまった言動や過去もちらほら。
そのあたりの細部にとらわれない、著者のホラーに特化した作品も読んでみたい気持ちもあります。
しかしとにかく、個人的には好きなシリーズであることは間違いないので、続きも楽しみ。
考察:登場人物の背景と、細かい点をいくつか(ネタバレあり)
井邑陽介の心理
上述した通り、『ナキメサマ』よりもミステリィ要素のパズル感が強く、それにキャラの設定や言動が引っ張られている部分も大きいため、前作よりもキャラの心理を考察するという感じではないのですが、せっかくなので軽く。
陽介の心理的な特徴は、とにかく「問題に直面することを避けたり後回しがち」に尽きるでしょう。
父親に対してもそうでしたし、那々木の言った通り、さっさと真実を話していれば本作の惨劇は避けられたのでは……とはやはり思ってしまいます。
妻=霧絵というのを踏まえると少し納得はできますが、妊娠している妻に負担をかけさせないために詳しくは説明しない、というのも疑問です。
さすがに「殺人事件に巻き込まれていて」とは言わないにしても、ほぼ何も説明しないというのは、それはそれで心配させそうですけどね。
とはいえ、思春期に家族がばらばらになり、自分が殺したも同然と感じるほどに父親の死にトラウマや罪悪感を抱いていたわけなので、問題と向き合ったり自分が何かを選択するということに対して、慎重になったり回避的になるのも仕方ない側面もあります。
しかし、そもそもお父さんの死が、本作で一番不自然に感じてしまったポイントでもありました。
終盤、父親の愛情を思い出す感動的なシーンが描かれましたが、いやでも、たとえ陽介が本当に自立して「もういい、お父さんの支えは必要ない」と思っていたのだとしても、自殺してそれを息子に発見させるというのは、いかがなものでしょうか。
100歩譲って自殺までは仕方なかったにしても、わざわざ呼びつけて息子に発見させようとしたというのを考えると、あの感動もちょっと薄れてしまうような……。
いずれにせよ、トータルとしてはバッドエンドだけれど、主人公にとっては一人勝ちなハッピーエンドと言っても過言ではない構図は前作と同じで、そんな後味の悪いところも好きです。
宮本一樹の心理
本作の主犯と言えるであろう、宮本一樹。
その動機は、霧絵に対する想いや、陽介に対するコンプレックスが主なものでした。
この点も、ここまで暴走して豹変するには少し弱かったというか、飛躍しているような印象もあります。
ただ、今回の件だけではなく、父親(実の父親ではありませんでしたが)も殺害していたようなので、もともとそういった自己中心的で残酷な素因はあったのでしょう。
しかし、那々木から「霧絵の気持ちを無視している」と指摘されて動揺されていた点からは、前作の主人公・挟間征次ほどの妄想性は窺えません。
ある程度、現実的な視点を持ちながら故郷である村全体および村人全員を犠牲にする選択をしたわけなので、ある意味狭間政次よりもタチは悪いと言えます。
ちなみに、那々木が指摘した「宮本が犯人である証拠」も、ちょっと弱かったような気も。
雫子の怨霊を前に「動くな」と言ったというのと、「(霧絵は)この村にはいない」という表現だけだったので、これならまだ誤魔化せたようにも思います。
といったあたりはまぁまぁ、あまり細かく突っ込むポイントではないですね。
細かい点
夏目が驚愕していたのはなぜか?
本作唯一の良心、と言っても過言ではなさそうな、商店の店主・夏目清彦。
彼が途中、驚愕の表情を浮かべてラムネを置いて去っていったシーンがありましたが、あれは何に驚いていたのでしょう?
この点が正直、いまいちわかっていないのですが、あの直前の陽介たちの会話をしばらく聞いていたのだとすると、「三門神社の火事は本当に事故なのか?大人たちの仕業で村ぐるみで隠し事をしているのではないか?だから霧絵が怨霊となって現れたのでは?」という推測を聞き、隠していた真実がバレそうだということに反応したのですかね?
ただ、彼は霧絵が生きているということは知っていたはずなので、怨霊が雫子であることに気づいた、ということなのかな?
もし何か他の説明をお持ちの方、いらっしゃいましたらぜひ教えてください。
那々木が陽介に視線を向けた意味
作中で2回、那々木が陽介に思わせぶりな視線を向けました。
おそらく2回目の方がわかりやすく、これは「別人(夏目美香)の遺骨を霧絵のものだと思わせるのを手伝ってくれ」という意図でしょう。
しかし、あれだけ凶悪に暴れておきながら、あっさりと別人の遺骨に騙されちゃう雫子、ちょっとお茶目で憎めません。
それを踏まえると、1回目のアイコンタクトも、同じ前提に基づいたものだと推察されます。
1回目は、村長の忠宣たちの前で、三門家および村の過去を暴いたシーンでした。
この時点では、那々木はすでに陽介の妻が霧絵であることに気づいていただろうと思われます。
そのため、陽介にとっては過酷な過去が明らかになるから、というのが一つでしょうか。
もう一つは、それを暴けばまた宮本が雫子を発動させるはず。
そうなったときに宮本を追い詰めたい。
そのためには、霧絵が実は生きているということを明かしてほしくない。
といったあたりかな、と思います。
こうやって振り返ってみると、ミステリィとして捉えると那々木が探偵ポジションになりますが、けっこう真相を見抜く能力がエスパー的にも感じられます。
このあたりは単純に物語の進行上の都合で「ただ抜群に勘が良いだけ」なのか、あるいは何か特殊な能力があるのか?
その点は、次作『忌木のマジナイ 作家・那々木悠志郎、最初の事件』で那々木の過去が描かれるようなので、それを踏まえてから改めて考えてみたいと思います。
追記
『忌木のマジナイ 作家・那々木悠志郎、最初の事件』(2025/03/24)
続編『忌木のマジナイ 作家・那々木悠志郎、最初の事件』の感想をアップしました。
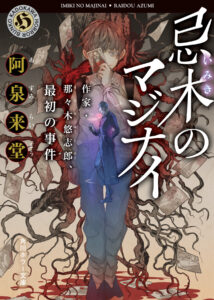
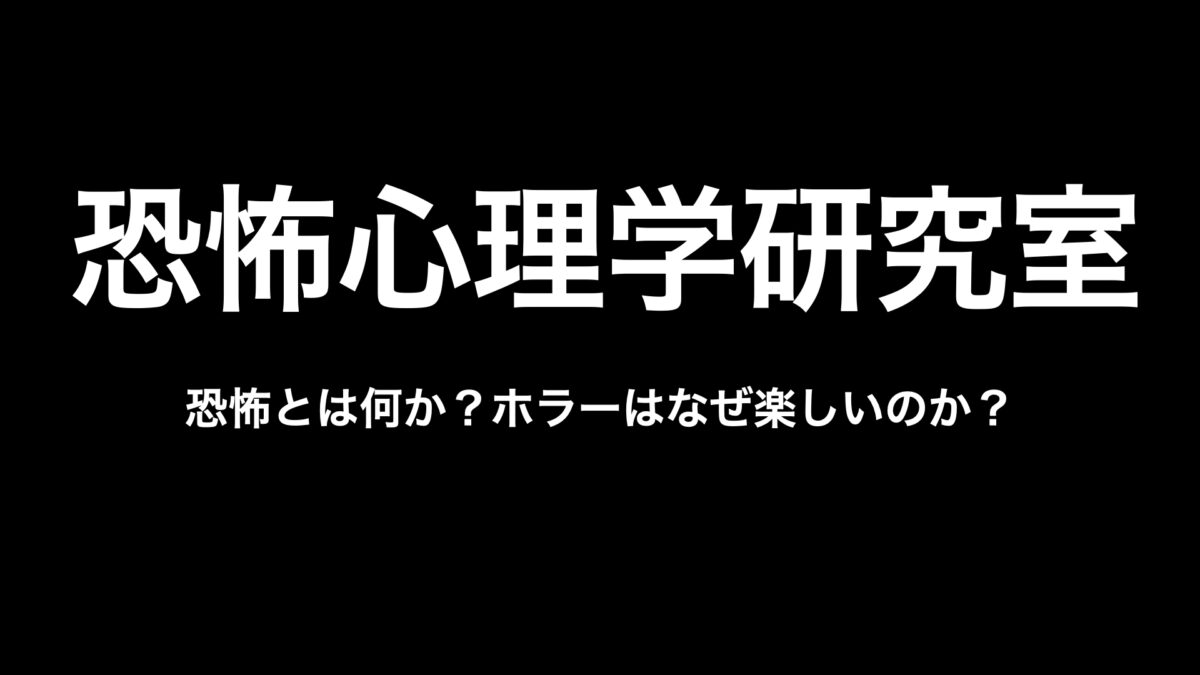
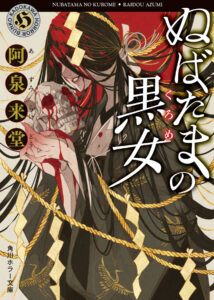
コメント