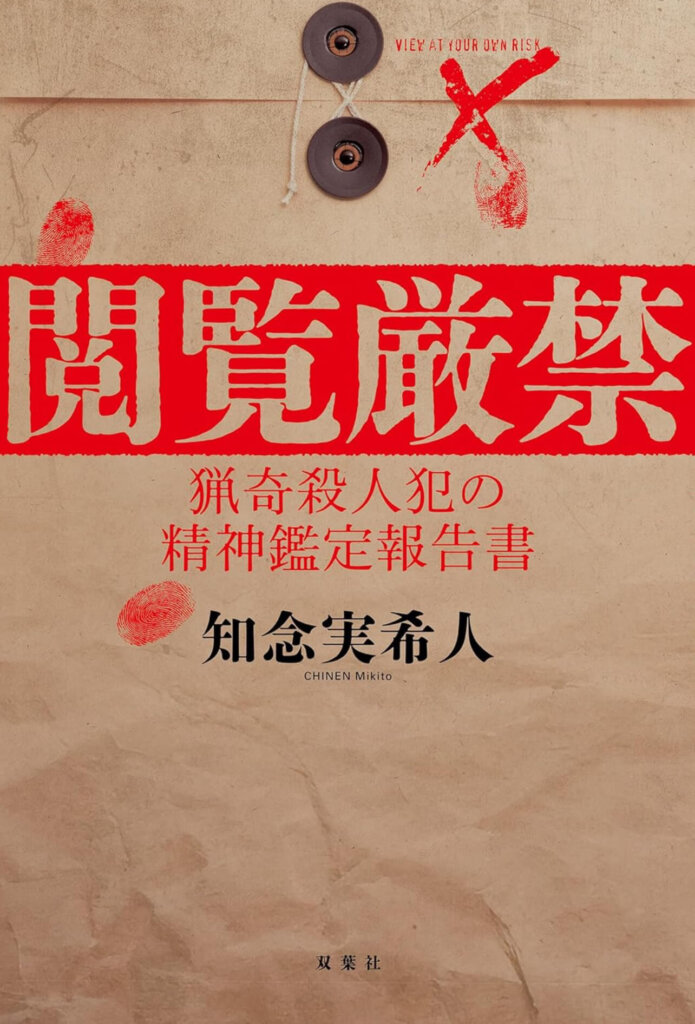
作品の概要と感想(ネタバレあり)
タイトル:閲覧厳禁 猟奇殺人犯の精神鑑定報告書
著者:知念実希人
出版社:双葉社
発売日:2025年9月18日
東京郊外で起きた大量殺人事件の記録には不審な点がいくつもあり、それは恐ろしい秘密の手がかりだった。
犯人である八重樫信也の精神鑑定を担当した医師・上原香澄のインタビューから徐々に明らかになる事件の真相。
犯行時の八重樫は「何」に怯え、一体「何」に襲いかかったのか。
ずっと八重樫を見ていたという「ドウメキ」の正体とは──?
「スマホ本」ホラーである『スワイプ厳禁 変死した大学生のスマホ』(以下『スワイプ厳禁』)と対をなす1作。
オフィシャルには「対をなす」という書き方ですが、時系列的には『スワイプ厳禁』の方が先なので、『スワイプ厳禁』を先に読んだ方がわかりやすいでしょう。
本記事には、『スワイプ厳禁 変死した大学生のスマホ』のネタバレも含まれるのでご注意ください。
『スワイプ厳禁 変死した大学生のスマホ』については、以下の記事をご参照ください。
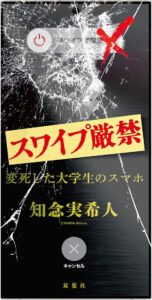
さて、先に申し上げておきますと、本作は残念ながら、自分にはあまり合いませんでした。
最後までのめり込めず。
なので以下、ネガティブが多めになっていると思いますのでご注意ください。
合わなかった理由も挙げていきますが、先に良かった点から。
まずはとにかく、新たな試みで発想も面白かったです。
スマホ本でワンコイン、そしてスマホの画面のみで展開されていく『スワイプ厳禁』から2作セットという構成。
すでに売れっ子作家と言って差し支えないであろう知念実希人ですが、常にチャレンジングな姿勢が感じられて頭が下がります。
このあたりはインタビューなどを読むと、デビュー当初はなかなか売れなかったり担当編集者に恵まれなかったことなども影響しているようですが、しっかりと売れる作品を量産しており尊敬の念。
外的な点では、プロモーション戦略も非常に巧みでした。
「ワンコインのスマホ本」「著者初のモキュメンタリ―ホラー」といったキャッチ―な要素溢れる『スワイプ厳禁』で話題を集めて、内容としても大きな謎を残し、これまたインパクトのある『閲覧厳禁 猟奇殺人犯の精神鑑定報告書』(以下『閲覧厳禁』)というタイトルの作品を1ヶ月後に刊行。
『閲覧厳禁』は発売前に重版がかかっていたようなので、初版予定部数がどれだけだったのかはわかりませんが、昨今の出版不況を鑑みればそれだけでも大成功と言えるでしょう。
内容も、著者には珍しくオカルト?としか思えない展開から、しっかりと謎解きがなされて人怖で説明がつく形になっていた点もさすがでした。
『スワイプ厳禁』の感想では「オカルトも絡めないと無理では?」といったようなテンションで書きましたが、しっかりとひっくり返されました。
強引さはあるとはいえ、作中の説明ではしっかりと理屈が通っています。
作中での説明は粗めですが、実際にあり得そう、と思わせるような監視社会の恐怖を絡めた設定は好きでした。
一方、以下が合わなかったポイントになります。
まずは何より、文章があまりに説明的だったり、フォントによる強調によって醒めてしまった点が一番大きいです。
この点、モキュメンタリーと謳われていたことが致命的でした。
小説はリアルさがすべてではありませんが、モキュメンタリーに関しては一定程度のリアルさが命だと思っているので、「こんな言い方しなくない?」という違和感のオンパレードは『スワイプ厳禁』から引き続き気になってしまいました。
写真がすべてイラストなのも同様。
また、これは他の方の感想でも散見されましたが、フォントの強調も「ここ!ここが怖いところ!」と押しつけられているようで、だいぶ没入を妨げるポイントとなってしまいました。
このあたりは好みでしかありませんが、これもモキュメンタリ―なのであれば淡々としていた方が個人的には怖く感じます。
そのあたりはやはり背筋『近畿地方のある場所について』の上手さが抜群でした。
あとは、予想よりモキュメンタリ―ではなかったところですかね。
これも勝手な期待ではありましたが、「精神鑑定書の内容を追うことで真相が明かされていく」といった内容をイメージしていたのですが、まさかの全編インタビュー、プラスいくつかの資料での補足。
楽しみにしていた精神鑑定要素はほとんどなく、インパクトのあるタイトルで期待値を上げすぎたな、という印象です。
ラストも個人的には合いませんでした。
読者も巻き込まれる系はモキュメンタリーの定番、というかもはやそれしか落としどころがないようにも思うのですが、近年のモキュメンタリーブームもあり、多く読んでいるとやや食傷気味。
その中でもあまりにもストレートな「あなたも共犯ですよ」感を、ページの使い方やフォントでこれでもかと強調されてしまったので、うーん。
「作品を読み進めたから登場人物が死んだ」という発想は面白いですが、シュレディンガーの猫な気もしますし、「一般の感性、つまりあなたの感想を知りたい」というのも含めてメタすぎに感じる点は醒めポイントになってしまいました。
等々、とにかく終始説明口調が気になってしまい没入できなかったのが一番大きくはあるのですが、このあたりは自分がそもそもターゲット層ではなかったのだろうな、と思います。
行間が広かったりしてサクサク読み進めやすく、おそらく読書やホラーにそこまで慣れていない層がメインのターゲット層でしょう。
ラストも言い方を変えれば「王道」です。
だいたいぼんやりと謎を残して終わることが中、ここまではっきりと「お前が犯人だ」みたいに読者にぶつけてくるのは、逆に斬新とすら言えるかもしれません。
その意味ではがっつりのホラーというよりは雨穴作品などに近く、知念実希人のネームバリューや人気を活かして、これまであまりホラーに触れてこなかった層にしっかりとアプローチされていると思うので、読書やホラーの間口を広げている本作の存在意義は非常に大きいと感じます。
逆に言うと、普段からホラーを好んでいたりモキュメンタリーに触れている層には、あまり刺さらなかったり物足りなく感じてしまうのではないかと思いました。
個人的には、同著者のバイオホラー『ヨモツイクサ』の方が好みでした。
ただ、読書好き、ホラー好きだからこそ、こういったライト寄りで裾野を広げてくれる作品には感謝しないといけません。
考察:出来事の整理とタイトルの意味(ネタバレあり)
出来事の整理
感想のところでも述べた通り説明口調すぎて感じられてしまった本作ですが、それはつまり、説明が丁寧ということでもあります。
なので、こういったモキュメンタリ―系統のホラーには珍しく、作中で謎の多くは明らかにされており、考察の余地はあまりありません。
結果としては、ホラーというより著者の得意とするミステリィ作品に限りなく近かった印象です。
話が壮大なので「細かい部分はどうなってるんだ……?」とは思ってしまいますが、そこはあえて詰めていくところではないでしょう。
なのでひとまず大まかに出来事だけ整理しておくと、黒幕だったのが精神科医の宇賀神春子。
彼女は以前、美ヶ原ニュータウンにある丸山精神病院の閉鎖病棟の地下で、四六時中他人の監視の目に晒された人間の心理を研究する人体実験に参加していました。
日本中のカメラ映像から特定の個人を検出できるシステム「ドウメキ」を悪用し、宇賀神は「監視する側の心理」を研究していました。
「ドウメキ」はもともと、日本がアメリカから支援を受けて、日本中の映像を統合し管理するシステムとして開発されていたもののようです。
監視されておかしくなっていく者の映像をダークウェブで販売し、それを閲覧する者たちを「ドウメキの瞳」と名づけ、参加型のスナッフビデオを楽しむ彼らを研究対象としていました。
ちなみに「ドウメキ」システムの正式名称は、作中のイラストによれば(ちょうどページの真ん中で若干見づらいですが)「Domestic unlimited-surveillance mechanism by image」のようです。
「映像による国内無制限監視メカニズム」といった感じでしょうか。
頭文字から「Do u mech i = ドウメキ」と名づけたと考えられます。
メインのスーパーコンピュータ、いわゆるスパコンは、宇賀神が院長を務める精神神経総合研究所附属病院内にあったようです。
映像の中継地点の一つ(おそらく尻尾切り用にいくつかあったのでしょう)に選ばれていたのが出版社の柳葉出版で、そこの管理者であり「ドウメキの瞳」の1人であったのが乾社長でした。
そこに勤めていた八重樫信也はドウメキの都市伝説にのめり込み、ニュータウンを訪れたことでターゲットとなってしまい、最後には追い詰められて大量殺人を犯し、精神鑑定中に自殺。
彼がドウメキの都市伝説を調べる過程で調査協力を依頼したのが、『スワイプ厳禁』の一色和馬でした。
被鑑定人を死なせてしまった精神鑑定医・上原香澄は、独自に調査。
その過程で乾社長を尋ねたことで「ドウメキの秘密に気がついているのでは」と疑いを持たれてしまい、憐れ次のターゲットに。
「ドウメキの瞳」の過激派はターゲットに危害を加えたり直接干渉したりしているようで、缶コーヒーやカッターの刃などを使って上原先生を精神的に追い詰めていきます。
それでも持ち前の聡明さで真相に近づき、一か八かで柳葉出版およびそこにあったスパコンの破壊に成功した上原でしたが、詰めが甘く、宇賀神の餌食となってしまいました。
タイトル考察
さて、そんなストーリーでしたが、読み終わって『閲覧厳禁 猟奇殺人犯の精神鑑定報告書』というタイトルを見ると、いまいちしっくり来ません。
このタイトルの意味を考えてみましょう。
タイトルのインパクトと吸引力自体は抜群です。
禁止されると逆に気になってしまう心理を「カリギュラ効果」と言いますが、そんな心理も逆手に取って興味を惹く巧いタイトル。
ちなみに、同じようなモキュメンタリーで有名な作品に長江俊和の『出版禁止』から始まる「禁止シリーズ」があるので、ついつい「スワイプ禁止」「閲覧禁止」と呼んでしまいそうになりますが、「厳禁」です。
それはさておき、まず「閲覧厳禁」の部分。
「あなたが読んだ(監視を続けた)から上原は殺人を犯すことになったのだ」的なロジックが本作の肝なので、こちらはわかります。
微妙にわからないのが「猟奇殺人犯の精神鑑定報告書」の部分です。
こちらを検討してみましょう。
まず「猟奇殺人犯」とは誰を指しているのでしょうか。
最初は八重樫であるようにミスリードされていましたが、最終的に本作で精神鑑定を受けていたのは上原であることが判明しました。
では、上原が猟奇殺人犯なのか。
これは微妙です。
普通に考えれば、八重樫も上原も猟奇殺人犯とは呼べません。
猟奇殺人というのは、殺し自体が愉しみや目的となっていたり快楽殺人であったり、バラバラ殺人やカニバリズムのように遺体を損壊するような殺人を指します。
八重樫も上原も、大量殺人ではありますが猟奇殺人とは言えません。
読者に悪を押しつけてくる構成からは「読者=猟奇殺人犯」と読み取ることも可能ですが、そうすると「猟奇殺人の精神鑑定報告書」は意味が通らなくなってしまいます。
そうなると、一番不自然さがなくなるのは「宇賀神=猟奇殺人犯」でしょうか。
研究目的で容赦なく人体実験を続け、何の非もない人々を死に至らしめ、その映像をダークウェブで販売しているというのは、なるほど猟奇殺人犯と呼べそうです。
その場合「猟奇殺人犯の精神鑑定報告書」は、「猟奇殺人犯の精神鑑定結果の報告書」ではなく、「猟奇殺人犯による精神鑑定報告書」となります。
ただ、宇賀神が自分で自分を猟奇殺人犯と言うのも違和感はあるような。
可能性としては、上原が猟奇殺人犯扱いされているというのはあるかもしれません。
もはや宇賀神の匙加減でどうにでも真実は歪められそうなので、上原は精神疾患の猟奇殺人犯扱いされて、闇に葬り去られてしまうのかも。
もしかすると、そもそもが「猟奇殺人犯」に対して深読みしすぎで「大量殺人を犯した上原は猟奇殺人犯」ぐらいの意味合いで使われているのかもしれませんが……。
さらには「精神鑑定報告書」という表現も違和感があります。
これは初めてタイトルを見たときには最初から気になっていたのですが、通常使われるのは「精神鑑定書」です。
そこをあえて区別したものと考えると、あくまでも「精神鑑定で得た内容の報告書」という意味になります。
本作中では正式な精神鑑定書の文章は一切出てきません。
「精神鑑定書」としてしまうと、自分が最初にイメージしていたようなきっちり整えられた鑑定書の内容で展開しないといけなくなってしまうので、「報告書」にしたのかな、と想像しました。
しかし『スワイプ厳禁』でもタイトルに対する違和感を抱いてしまったので、この2作はインパクト重視のタイトルであり、あまり細かく考えてはいけないのかもしれません。
心理学的・精神医学的なリアリティあれこれ
もはや言うまでもありませんが、著者の知念実希人は医師でもあり、きちんとした医学的知識に基づいた作品作りが魅力です。
内科医なので精神医学は専門ではありませんが、それでもしっかり調べたであろう上で裏づけされた本作の設定も、エンタメとして非常に魅力的でした。
なのでちまちまリアリティ云々を検討するのは蛇足でしかないでしょうが、せっかくなので小ネタ的に自分の専門的な視点から見てみます。
まず、本作で八重樫に行われていた精神鑑定ですが、妄想に基づいた犯行の可能性があるので、自傷・他害の恐れが考えられます。
そのため、精神鑑定においてはなるべく被鑑定人が落ち着いて話せる環境を整えることが大事にはなりますが、自傷を防ぐための最大限の対策が取られるはずです。
そんな環境下で、上原が不用意にボールペンを渡してしまったのは相当な落ち度となるでしょう。
このような責任や管理が大変なので、入院させての鑑定はそれほど多くありません。
よほどの事情がない限り、拘置所で実施されることがほとんどです。
録音することもあまりありません。
本作のように鑑定医が女性で被疑者が男性、しかも暴れたりする可能性のある場合、男性の鑑定助手が同席することもあります。
本作で上原に行われていた精神鑑定はきちんとしたものではなかったので(宇賀神がいくらでも鑑定結果を捻じ曲げられる、まともに鑑定する気はなかった)、そのリアリティを細かく検討することは意味がないのでやめましょう。
実際の精神鑑定は、精神科医が単独で行うものではなく、自分のような臨床心理士も心理検査等を行います。
本作には辻なる人物が助手として登場していたので、彼(彼女?)がそのような立場だったと思われます。
精神科医1人で行う方もいますが、これだけ大きな事件であれば様々な検査等が必要になるでしょう。
宇賀神だけではおそらく闇に葬るのは難しいので、検察にも「ドウメキの瞳」がいるのでしょう。
ただ、上原には弁護士もついているはずなので、その弁護士をどうするのかが問題になりそうです。
基本的に私選弁護士は被疑者が自由に選任できるので、「ドウメキの瞳」である弁護士を送り込むというのは難しいです。
ガンザー症候群(拘禁反応)は、実際に死刑囚や勾留されている被告人に見られることが少なくありません。
通常は閉鎖空間で起こるものですが、社会内においても常に監視されているという意識が拘禁反応を引き起こす、という本作の発想はとても面白いものでした。
途中で出てきたスタンフォード大学の監獄実験は、実際に行われた実験です。
この実験をもとにした『es[エス]』という映画があったりかなり有名なので、本作を読む以前にも知っていた方も少なくないかもしれません。
しかしこの実験の信頼性は、今では疑問視されています。
看守役へ攻撃的行動をするように積極的な指示があったり、被験者の一人が「わざと発狂したフリをした」と告発したり、そもそも被験者が実験者の期待を汲み取って応えようとする要求特性が働いていたという指摘がなされていたり。
研究デザインもだいぶ杜撰ではあるので、完全に否定されているほどではありませんが、現代では信頼性は低い実験として位置づけられています。
その点も有名なので著者もご存知だっただでしょうし、踏まえてそこは割り切ってエンタメとして採用したのでしょうが、監獄実験の結果だけが切り取られて独り歩きするのはあまり好ましくないので念のため。
登場人物の心理面を見ると、全体的に飛躍している感は否めません。
特に八重樫は、追い詰められた上に罠を仕掛けられていたとはいえ、あそこまでの凶行に走るのはやや突飛に感じられますし、真実の糸口を見つけていたにもかかわらずそれを上原に託して自分は自殺するというのも不自然には感じられてしまいました。
このあたりは話の展開上仕方なく、登場人物の内面や背景を深掘りする作品ではないとわかってはいますが、精神鑑定というテーマを扱っていながら、八重樫だけではなく上原の行動原理も宇賀神の動機も浅かったところが、個人的には残念でした。
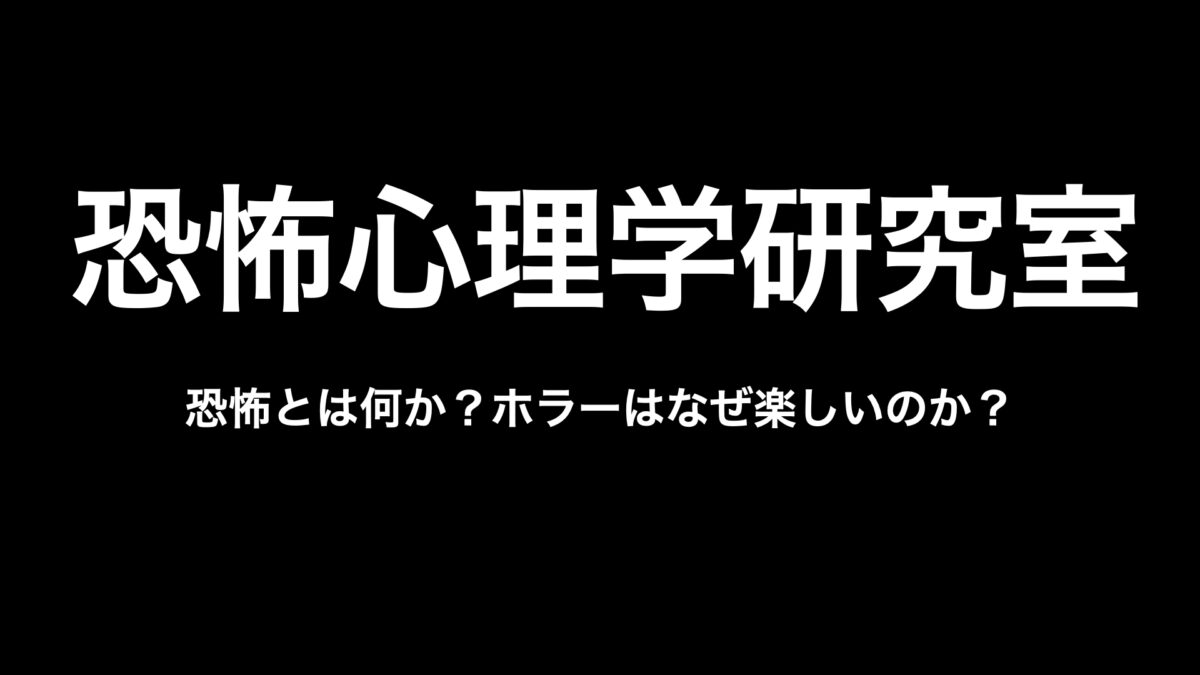
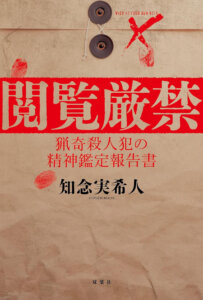
コメント