
作品の概要と感想(ネタバレあり)

行方不明になったオカルト雑誌の編集者。
彼が消息を絶つ直前まで調べていたのは、幼女失踪、中学生の集団ヒステリー、心霊スポットでの動画配信騒動など、過去の未解決事件と怪現象。
彼はなぜ消息を絶ったのか?
いまどこにいるのか?
同僚の編集部員は、女性記者とともに彼の行方を探すうちに、恐るべき事実に気がついた。
すべての謎は「近畿地方のある場所」へとつながっていたのだった──。
2025年製作、日本の作品。
もはや説明するまでもないですが、近年のホラー小説の中でも大ヒットした背筋による小説の映画化。
監督はブームよりはるか以前からモキュメンタリーホラーを数多く手掛けてきた白石晃士監督。
さて。
今、非常に言葉を選んでいるのですが。
まず、いきなり私事ですが、この映画を観に行ったのは2025年8月13日です。
公開が8月8日なので、そこそこ公開直後に観に行きました。
そして、ブログへの感想をどうしたものか、と悩むこと2週間以上。
さすがに8月中には書いておこう……と思いつつ、本日は8月31日。
夏休みの宿題のようになってしまいました。
ここまででおそらくお察しいただけたことかと思いますが、人気作品、人気監督なので声を大にしては言いづらいので小声で言いますが、
個人的にはとっても合いませんでした!!!!!
そのため、ネガティブだらけになってしまいそうなので感想を書くかどうか迷いつつも、せっかく観たものは記録として残しておきたいですし、そもそもブログは自分のホームという認識で、書き残しておこうと思います。
ネガティブな感想も価値があると思っているので。
とはいえ、TwitterなどSNSに流すのはやめておきますが。
というわけで、以下、さほど内容に触れない上にネガティブ多めなのでご注意ください。
また、あまり触れないかとは思いますが、原作のネタバレに触れる部分もあるかもしれません。
原作の感想については以下の記事をご参照ください。
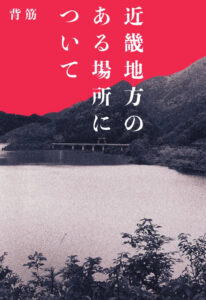
観終わって感想としては、
思った以上に白石監督だな。
でした。
白石作品はそもそもまだそれほど多くは観られていないですし、嫌いではないですが、大ファンというわけでもありません。
モキュメンタリーへの信頼度は非常に高いですが、展開や個性の癖が強いのも知っていたので、個人的にはそもそも本作を観に行く前から、自分にはあまり合わないだろうなと思っていました。
原作がとても好きなこともあり。
そんな覚悟をして観に行ったにもかかわらず、予想を上回る白石監督度の高さでした。
それが良い悪いではなく、実際に絶賛の声も多くありますし、話題にもなり、興行収入も良いようなので、大成功と言えるでしょう。
もはや『もののけ姫』の実写化かと錯覚するほどの終盤の怒涛の展開における白石節には、完全に置いていかれつつも感心すらしました。
なぜ自分には合わなかったかなぁと考えると、やはり原作のリアルさが大好きだからかと思います。
実際にありそうな記事、ネット掲示板の記録、テープの文字起こしなど、多岐にわたる媒体のテキストが徐々に繋がっていく。
まさにモキュメンタリーなリアルさが、原作の魅力でした。
そのため、そもそも映像化することに無理があるとは思っていました。
テキストの集合体でしか成り立たない作品だったので。
そのまま映像化したとしても地味でしかありませんし、映像化するにあたっては大きく改変するしかありません。
なので、そもそも映像化すること自体に否定的なので、あまり多くを語るべき立場ではない、とは理解しています。
絶賛の声の多くは白石監督ファンのように見受けられるので、それは非常に納得です。
背筋および原作のファン、かつ白石ファンというのは多いと思うので、新たな化学反応を起こす組み合わせとしては大成功でしょう。
ただ、原作ファンで白石監督はそれほど……という人にとっては、同じように残念に思った方が多いのでは、と勝手に思います。
そのあたりはそれぞれの好みですし、あまり愚痴愚痴言いたいわけでもないので控えておきましょう。
少し視点を変えると、個人的に大事なポイントは原作者が納得しているかどうか、です。
以前書いた『変な家』の感想では、原作者の雨穴があまり肯定的に感じていなさそうなところをマイナスとして捉えました。
その場合、たとえ興行成績が優れていたとしても、個人的には評価できません。
では『近畿地方のある場所について』はどうかというと、表面的に見える範囲では、著者の背筋は肯定的に捉えてるように見えます。
『このホラーがすごい! 2025年版』には、背筋と白石監督の対談が掲載されていました。
その中では、背筋がもともと白石監督ファンであることが述べられた上で、以下のような発言がありました。
途中からはもう、いい意味で白石監督のこの作品に対する解釈が、私のイメージを追い越していったように感じられた瞬間があって、それ以降は何も言わないようにしていたんです。
『このホラーがすごい! 2025年版』(宝島社)
僕としては原作との最低限の整合性さえ取れていれば、映画は映画で白石監督らしく仕上げていただければ、それが最高だと思っていましたから。だから、十稿目以降くらいの脚本からは、あえて薄めで読み流すくらいにしていたんです。
これらの発言からはもう白石監督らしさで好きにしてほしいという気持ちも窺えるので、そうであれば何も言うことはありません。
むしろ、自分の作品を自分がもともとファンである監督に、その監督のテイストで映画化してもらえたとしたら、それはすごく感慨深くて嬉しいだろうなぁと思います。
なので内容についてはこれ以上あれこれ言わないとして、基本的に背筋は常にメタ的・俯瞰的な視点で頭が良いなと思っているのですが、『近畿地方のある場所について』のプロデュース手法も時間の経過に合わせて非常にクレバーだなと思いました。
具体的には、モキュメンタリーから離れていっている点です。
『近畿地方のある場所について』がなぜヒットしたかといえば、そのリアルさが大きな要因であったことは間違いないでしょう。
これは創作なのか?
実話なのではないか?
と、少しでも思わせた時点ですでに優れた作品であることは間違いありません。
もちろんその内容や文章のリアルさが大事であることは間違いありませんが、同じぐらい重要だったのは、当時は背筋が無名だったことでしょう。
これが有名な作家が書いた作品であれば、どこかフィクション感が漂っていたはずです。
これは、無名の作家が使える1回限りの手法とも言えます。
つまり、そんな1回しか使えない手法で大成功したのが『近畿地方のある場所について』でした。
三津田信三のようにモキュメンタリー(ご本人の表現を借りれば「メタフィクション」)を何作も作り続けている作家もいますが、それは並大抵の才能ではありません。
背筋もおそらくその難しさを理解しており、スタンダードなモキュメンタリーから離れる方向に舵を切っています。
『穢れた聖地巡礼について』はフィクション色を強めつつメタ的な視点が光る作品ですし、『口に関するアンケート』はまた新しい試みで仕掛けを施した作品。
そして何より、『近畿地方のある場所について』文庫版における単行本からの大幅な変更です。
文庫版はまだ読んでいる途中なのですが、冒頭の時点で大きな違いが見られます。
単行本は「背筋と申します」と始まるのですが、文庫版は小澤雄也が「私」となっていました。
この時点で、フィクション小説色が強まっています。
つまり『近畿地方のある場所について』ですら、モキュメンタリーから離れた方向に舵を切っているのです。
もともと背筋本人は『近畿地方のある場所について』についても「自分でモキュメンタリーとは言っていない」といったようなことを述べていた記憶なので、モキュメンタリーに強いこだわりがあるわけではないのでしょう。
とはいえ、初期はまだ方向性に迷っている様子が窺えました。
Twitterを始めたときは、作品(『近畿地方のある場所について』)のリアルさが失われることを懸念するようなポストもありましたし、その頃は対談イベントにも梨のように覆面をして登場していました。
しかし途中から顔出しをするようになり、おそらくそのあたりからご自身の方向性がある程度定まったのだと考えられます。
それはモキュメンタリーにこだわらない方向性でしょう。
上述した通り2作目以降の作風からも明らかですし、活躍の場を小説以外にまで広げていることも同じく。
なので、ご自身が表に出て活躍の場を広げた時点で、『近畿地方のある場所について』のリアルさやモキュメンタリー性にはこだわらなくなっている、というよりモキュメンタリーとして推し続けるのは無理であることをしっかりと理解している、と感じています。
そうであれば、『近畿地方のある場所について』の映画に原作のリアルさを求めるのもまた間違っているのかな、とも思いました。
そもそもテキスト群でしか成り立たないのが原作なので、その映像化の許可を出した時点で、その覚悟は十分できていたのだろうと考えられます。
というわけで、話が広がりましたが、個人的には内容が合わず原作好きとしては残念さはありつつも、これはこれで派生系の一つとしてはありなんだろうな、と思いました。
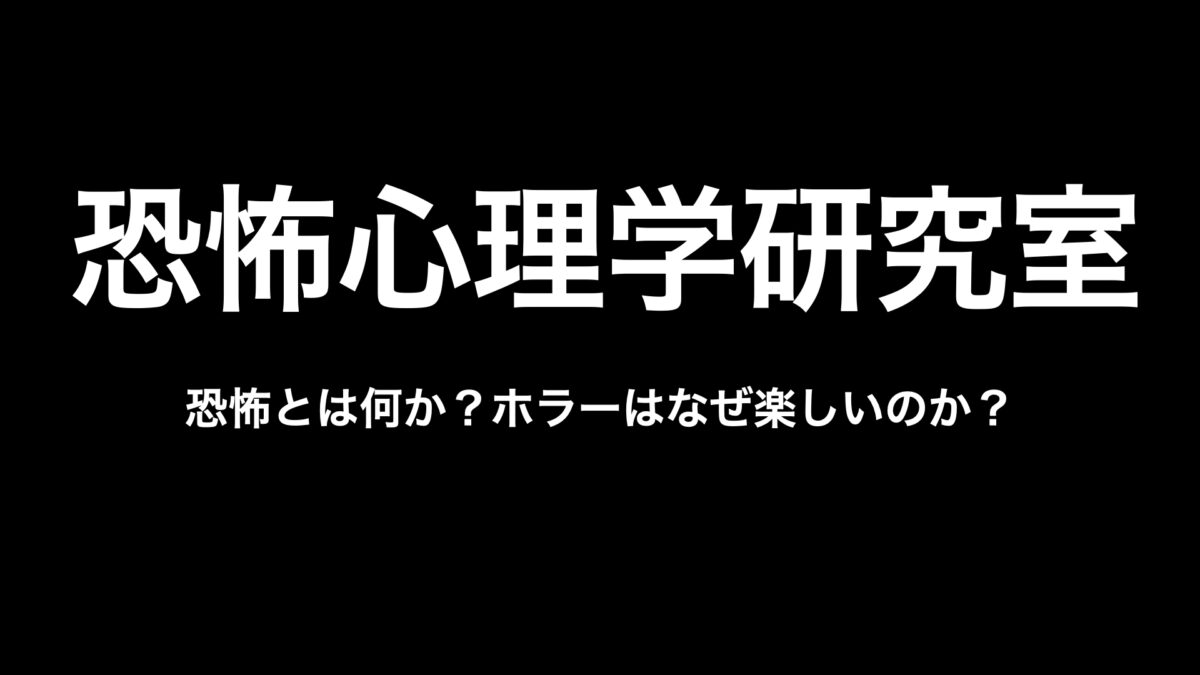

コメント