
作品の概要と感想(ネタバレあり)

極寒の地・長野県に住むスポーツインストラクターの清沢賢二は、愛する妻と幼い娘たちのために念願の一軒家を購入する。
“まほうの家”と謳われたその住宅の地下には、巨大な暖房設備があり、家全体を温めてくれるという理想のマイホームを手に入れ、充実を噛みしめながら新居生活をスタートさせた清沢一家。
だが、その温かい幸せは、ある不可解な出来事をきっかけに身の毛立つ恐怖へと転じていく──。
2023年製作、日本の作品。
本記事には、神津凛子による原作の小説『スイート・マイホーム』のネタバレも含まれるのでご注意ください。
小説『スイート・マイホーム』については、以下の記事をご参照ください。
個人的に原作の小説はとても好きなので、嬉しい映画化。
しかし、原作の完成度も高く、映画は齊藤工が監督を務め、基本的に原作に忠実で丁寧な作品でしたが、いまいち話題になりきらないまま過ぎ去ってしまった印象も(という自分も、映画館まで行けなかったですが)。
余談ですが、俳優などだと「斎藤工」表記ですが、監督のときには本名の「齊藤工」表記を用いているようです。
話題になりきらなかった要因としては、タイトルも内容も少々地味な点でしょうか。
タイトルはこれ以上ないほど本作には適切なタイトルだと思いますが、タイトルだけ聞くと何となく平和なヒューマンドラマ的なイメージが浮かんでしまい、個性的な吸引力という意味では弱め。
内容も、派手さよりもじわじわ日常が侵食される系なので、インパクトには欠けてしまいます。
あとは、予告はけっこうホラー押しな感じでしたが、あくまでもメインはミステリィなので、がっつりホラー路線を期待して観ると肩透かしになってしまいそう。
基本的に小説の映画化にはネガティブな印象を抱いてしまうことも多いですが、本作は上述した通り基本的に原作に忠実な展開でリスペクトが感じられ、楽しめました。
ただ、原作の魅力は登場人物それぞれが抱える過去や闇、そして微細な心情の描写だと思っているので、そもそも論的には映像化には向いていない作品である感も否めません。
この点は、齊藤工監督のインタビューでも「これを映画にするというのは果たして現実的なのだろうか」と悩み続けていたことが述べられており、その中での工夫はしっかりと感じられました。
まず、あえて細かい心情や背景は省略されており、ミステリィ要素に重きが置かれていた印象です。
その中でも、オカルトかと思わせておいて実はヒトコワだった、という原作の構図もしっかりと踏襲。
一方で、諸々の設定の簡略化や省略により、展開や行動が唐突な感もやや否めません。
特に、他人の家に忍び込んで家族と暮らす妄想に浸るという、犯人である本田のだいぶ非現実的で突飛な犯行が本作の特徴です。
その動機が、原作では幼少期の体験まで遡って徐々に狂気が形成されてきた過程が描かれ、非現実的ながらも説得力を持たせていましたが、本作ではただ婚約者と生まれてくるはずだった子どもの死だけに還元されているので、少し飛躍を感じます。
他にも、主人公の賢二の兄・聡がサチを守った際にも、小説では賢二が母親にかけた電話をきっかけに聡が異変を察し、賢二の家に来たという流れでしたが、映画では特にきっかけもなく不意に賢二宅に来ていたので、やや超能力者っぽくなってしまっていました。
しかし、統合失調症のリアルさは別として(そもそも統合失調症という病名すら映画では出てきませんでしたが)、窪塚洋介の演技は抜群でした。
その他、登場人物全員、演技は素晴らしかったです。
特に賢二役の窪田正孝は、モデルのようなイケメンという小説での描写からイメージしていた賢二像とは違いましたが、不倫の後ろめたさもあってかあまり妻の目を見て話さないところなど、細かい点がとても上手でした。
些細ですが、警察の柏原が常に単独行動していたのは、何だか違和感。
原作ではちゃんと2人組でした。
演出上シンプルにするためにカットしたのでしょうし問題はありませんが、最近は一般的にも刑事はペアで捜査するというのが浸透していると思うので、柏原が原作よりもつかめないキャラクターになっていたことも相まって、何だかちょっと怪しく見えてしまいました(そう見せようとしていたのかもですが)。
あとは何より、“まほうの家”が映像で見られたのはとても嬉しかったです。
停電したらとんでもないことになってしまいそうだなと思いましたが、神津凛子自身が似た構造の家を実際に建てたそうなので、実際はもう少し現実的な形でしょうが、実在するようです。
ちなみに、原作および映画でも舞台は長野県でしたが、映画の撮影は仙台で行われたようでした。
地下室への入り口狭すぎやろ、地下室暗すぎやろ、75度まで設定できるのはやばすぎやろ、などなどツッコミどころもありましたが、そのあたりはあえての演出重視でしょう。
そんなわけで、小説の映画化の中では完成度も高く、映画ならではの良さもありましたが、単体で見ると少々物足りなさも感じてしまった1作。
ただここは難しいですよね。
原作既読の層と未読の層と、思い切ってどちらかだけに特化するのもありだとは思いますが、基本的にはどちらにも観てもらうことを想定して作ると思うので、どこを拾ってどこを切り、映像化ならではのポイントをどこに置くか、というのはとても難しいでしょう。
いずれにせよ、映画しか観ていない方はぜひ原作も読んでみていただくと、それぞれの登場人物の行動原理や背景が、よりわかりやすくなると思います。
考察:原作との比較と、映画のラストシーン(ネタバレあり)

原作との比較
基本的に原作に忠実だった本作。
細かいところまで書くとキリがありませんが、映画内では省略されていたポイントで大きなものは、以下あたりでしょうか。
- 賢二の兄・聡は統合失調症(映画でもたぶんそうですが、明言されず)
- 賢二は過去に学校のうさぎを殺し、聡がそれを隠してくれていたが、賢二は自分が殺したことを忘れていた
- 賢二の同僚・上林も清沢邸に遊びに来て、「お化け」を目撃する
一方、省略というよりも変更と言えるような点は以下でした。
- 本田の過去
- 甘利のキャラクターと役割(何とか本田を止めようとしていた)、および殺され方(家で自殺に見せかけられていたのが、屋外に)
- 清沢邸が原作では平屋でしたが映画では二階建て
- 最終決戦の舞台(?)が原作では地下室でしたが映画では屋根裏
- ラストシーン
特に大きいのはやはり、感想部分でも触れましたが本田の過去でしょう。
原作では、大工の父を亡くしたあたりから理想の家と家族を夢見るようになり、父の建てた家を見に行っていたところで性被害体験。
婚約者の死も、婚約者が浮気をしていたので事故に見せかけて本田が殺害したのでした(妊娠もしていなかった)。
また、清沢家の前にも理想の家族に同一化しようとしましたが、トラブルになったことがありました。
このあたりの細かいプロセスが、映画では「事故で婚約者を失い、その後妊娠していた子どもも死産してしまい、そのショックから3人家族にこだわるようになり、理想の3人家族に同一化するようになった」と簡略化されていました。
著者である神津凛子のインタビュー(映画ではなく小説に関するもの)では、執筆にあたって本田について「その人物は賢二たちに恐怖を与えたわけですが、行動の裏にはその人物なりの狂気に陥る理由や悲しみがあるんじゃないかと思ったんです。それがなければ、話が成立しない。ただの異常者、ただのおかしな犯罪みたいになってしまう。それは書きたくないので、本人に喋らせてみようと思ったんですよ」と述べられていました。
この点が映画では、動機は描かれつつもただの異常者寄りになってしまっていたように感じますが、時間制限もある映像での表現という枠組みでは仕方なかったとも言えます。
ただこの点については、齊藤工監督のインタビューで「モンスター化したという輪郭だけで描くのは何か違うなと思ったので、そこについては映画を見てくださる方それぞれに、該当するキャラクターの表情を捉えていただけたら──と願っていて」と述べられていました。
この言葉からは、原作における背景だけに限らず、観た人それぞれの解釈や勝手な想像があって良いのだろうと感じます。
また、ラストシーンも、ひとみがユキの目を潰してしまうという点は同じでしたが、細かくは違いが見られました。
この点は次で考えてみたいと思います。
映画におけるラストシーンの解釈
映画のラストシーンは、小説とは似て非なるものでした。
小説ではリビング、映画では屋根裏と場所が違うのもありますが、そもそも妻のひとみの様子が異なります。
最後の「これでもう見なくて済むよ。ね?」というひとみのセリフは同じですが、その前に、小説では賢二の呼びかけに一切応えなかったひとみが、映画では謝罪する賢二に対して「これからも、まだまだ邪魔が入ると思うの。私たち家族を壊そうとする人が」というセリフが入ります。
この思想は、本田を彷彿とさせるものです。
小説でもユキの目を潰した理由は明確にはわかりませんでしたが、事件等のショックで精神に異常を来し、恐怖や自身の醜い部分を映し出す対象(=赤ちゃんの瞳)に耐えきれなくなった、と個人的には解釈しました。
しかし映画版での上述したセリフを踏まえると、まるで本田が乗り移ったかのようにも見えます。
齊藤工監督のインタビューでは、おそらく屋根裏部屋について「映像の色彩を含めて『母親』をイメージさせるようなものにしている」「神津先生が生み出された物語を、女性キャストの方が体現し、それを撮影監督の芦澤明子さんがカメラで捉えて下さる。映画『スイート・マイホーム』は、このような一連の女性性を伝え渡す物語だと思っています。なので、紆余曲折の中、必然的に”あの色”になりました」とも述べられていました。
他のインタビューでも、原作を読んだときの感想として「これは男性が、女性性や母性に感じる“怯え”に似ている感覚。そんな、聖域のような部分を突き付けられる読書体験でした」と話しており、女性性や母性といったものが大きなイメージとして存在していたことが窺えます。
包み込むことが母性の機能ですが、それは「家」という空間にも当てはめられるでしょう。
母性の包み込む機能は、プラスに働けば優しく包み込み受容するものとなり、マイナスに働けば呑み込み死に至らしめるものとなります。
他人の家族を自分のものとして呑み込もうとする本田の呪いのようなものが、家全体に広がり、ひとみもその影響を受けたのではないかと思わせるのが、映画のラストでした。
その意味では、母性の負の側面の伝染としても捉えられますが、小説よりもオカルト的な毛色も強く感じられます。
また、別の解釈としては、ひとみが自分のネガティブな側面に耐えきれなくなり、それを消すために、自分の醜い内面を映し出すユキの瞳を潰したとも考えられます。
ただ、それは小説における「純粋なこの目でじっと見つめられるとね、(中略)私の醜い部分や汚れた部分を見透かされているような気分になる時があるの」というセリフを読んだ上での解釈であり、映画ではこのセリフはカットされていました。
一方で、映画オリジナルのセリフとしては「まだあれが見えるの。じゃああれは、あの家にじゃなくて、ユキの中にいるってことでしょう?」というものがありました。
聡の死に際して「ユキを連れて行ってくれたらよかったのに」というセリフは同じですが、小説では「私に取り憑いているのかしら」「私に取り憑いたお化けに殺されたんだもの、私のせいよ」というセリフがあり、「ひとみ自身が取り憑かれている」と考えている小説版に対して「ユキの中に恐ろしいものがいる」と考えているのが映画版で、ひとみの認識が異なっています。
それを踏まえると、映画版では、自分の醜い部分を投影して消そうとしたというよりは、単純に障害となるもの、見たくないもの、恐ろしいものを排除しようとした、と考える方がしっくりきます。
小説でも映画でも、度重なる恐怖体験によってやや精神に異常を来していたのは間違いないと思いますが、映画版では「見たくない恐ろしい存在から目を背けようとする」という心理に本田の影響が重なって、ユキの目を潰す、という行動に至ったのではないかと感じます。
目を背けるというのは、実家に帰省するのを避けたり不倫をしたりと小説(映画でも)の賢二に特徴的な傾向でした。
それが映画版では、ひとみにも強く現れていたのではないかと思います。
ただ、小説でも映画でも、だいぶクズ男な賢二に対して、ひとみはほぼ何も文句など言いません。
おそらくネガティブな感情はすべて自分の中に溜め込んでいたのではないか、と考えられます。
それはそれで、正面から向き合うことを避けているという意味で、一種の現実から目を逸らす傾向でもあります。
思えば、賢二の母親も父親の死(賢二による殺害)を隠していました。
それは果たして正しかったのか?というのは小説版の感想でも書きましたが、これもまた、現実逃避とも言えるでしょう。
そう考えると、本作に登場する大人たちは、現実から目を逸らしがちな傾向が窺えます。
他人の家族に「自分の理想の家族」を求めた本田はもちろん、言うまでもなく。
一方、その対比として、冒頭やラストを含め、子どもが顔を覆った手の指の隙間から覗くシーンが印象的です。
現実から目を逸らす大人に対して、怖いもの見たさや好奇心から現実を見つめる子ども。
大人が目を逸らしたい現実も純粋に見つめ、映し出す子どもの瞳。
ユキを殺すことに意味があったのではなく、その瞳を潰すことに意味があったので、子どもの目を潰すという衝撃的なシーンが、しっかりと映画でも再現されていたのは安心しました。
統合失調症の患者さんもまた、驚くほどの純粋さや繊細さを持ち合わせていることが少なくありません。
本作で聡だけは、病気による妄想の世界と戦い苦悩しながらも、唯一と言えるほどしっかりと現実を見つめようとしていた大人であったと言えるでしょう。
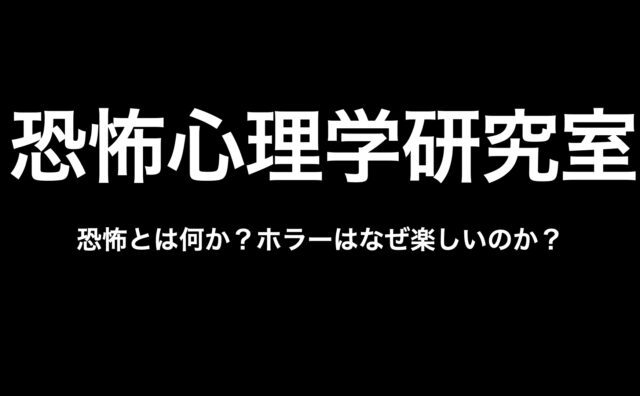







コメント