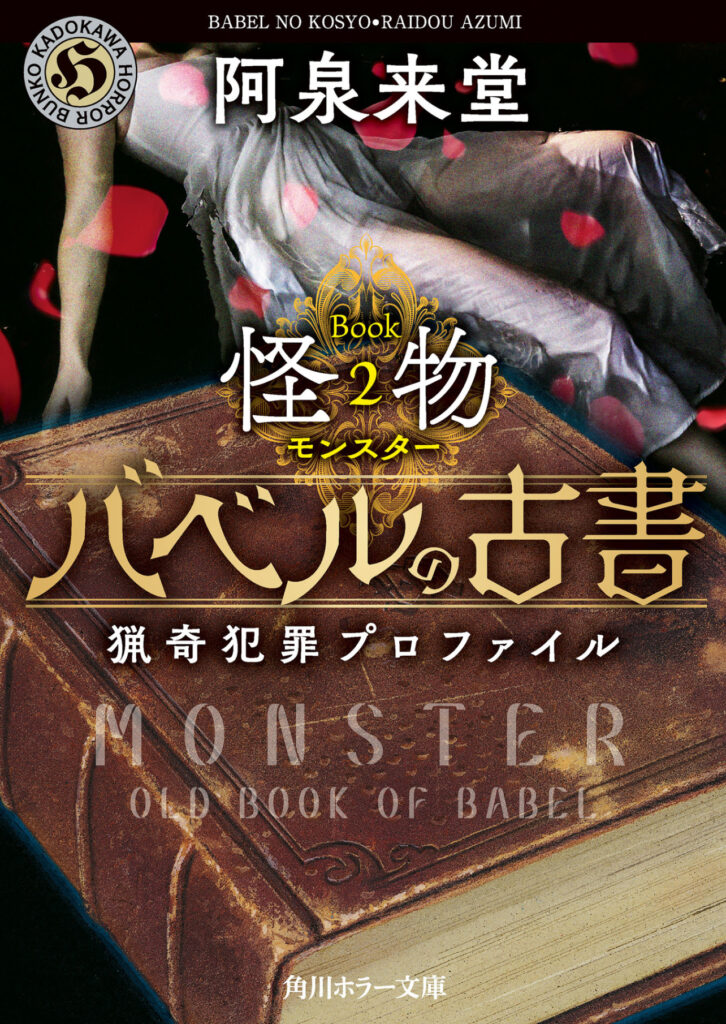
作品の概要と感想とちょっとだけ考察(ネタバレあり)
タイトル:バベルの古書 猟奇犯罪プロファイル Book2《怪物》
著者:阿泉来堂
出版社:KADOKAWA
発売日:2023年10月24日
先のグレゴール・キラー事件から2か月。
その功績を認められ、刑事課強行犯係特別事案対策班(通称 「別班」)に配属された加地谷と浅羽が新たに捜査に当たるのは、帰宅途中に殺害された女性の遺体が、まるできれいに清められたかのように安置された「エンゼルケア殺人事件」。
再び道警本部捜査支援分析室の天野伶佳らとともに捜査を進めるうちに浮かび上がってきたのは、十五年前に発生した少女殺人事件と、死亡した少女の遺族である一人の青年の存在。
そして、数年おきに発生している女性の不審死事案だった──。
『バベルの古書 猟奇犯罪プロファイル Book1《変身》』と同時発売された作品。
KADOKAWAの公式サイトでも「下巻」「後編」と表現されているので、2作セットで捉えて間違いなさそうです。
以下、『Book1《変身》』の内容にも触れるのでご注意ください。
先に全体的な話をすると、やはりこの2作でようやく序章、という感覚。
古書が関係していそうだね、というのが作中でも明確に示されますが、その謎はまだまったくと言っていいほどわかりません。
2作とも個々の事件は解決していますが、そもそもの原因となっていそうな古書を巡る全体の謎は、今後のシリーズ前提でしょう。
シリーズ前提、かつ最初の2作は同時発売というのは、著者も出版社もなかなかの気合いを感じます。
本作は『フランケンシュタイン』で「怪物」がテーマとなっていますが、前作の『変身』と同じく、テーマとなっている作品の内容自体はそれほど関係ありません。
見立て殺人だったり構成が類似しているというわけではなく、あくまでも「変身」「怪物」をキーワードとした事件が起こる、という構図。
このあたりは、当然ながらバベルの古書が影響していると考えられます。
所持者に何らかの影響があるのだろう、としか今のところわかりません。
ここにオカルト的な、「スーパーナチュラル」要素が含まれていると思うので、つまりは言ってしまえば何でもありなわけで、その背景はシリーズを追っていくしかありません。
そのため、個々の事件についても、あまり現実的に検討するべきではないでしょう。
猟奇殺人プロファイル、と銘打たれてはいますが、リアルな心理学的観点がベースになっているというよりは、あくまでもエンタメ路線です。
それもあってか、おそらくベースとなる古書がまずありきで、その上でそれぞれのテーマやキーワードに沿った猟奇殺人を考えているのかな、と想像されるので、個々の事件には若干強引さも否めません。
前作の犯人・美間坂の動機もいまいちはっきりしませんでしたし、本作も動機の面ではやや強引だったり説明不足感も。
少しわかりづらく、かつ読者によって解釈が異なる余地は残されているかなとも思いますが、個人的には本作は、加地谷の解釈と一致しています。
つまり、青柳このみの魂(?)が久間琴絵に乗り移っていた、という解釈です。
解離性同一性障害は、そう都合良く別人格が出来上がるものではありません。
解離性同一性障害説が出てきたときは「そういう便利な使い方はやめてほしい……!」と思ってしまいましたが、結果オカルトに落ち着いてくれて一安心(?)。
ちょっとややこしいので整理しておくと、もともと青柳このみには残虐な傾向があったようです。
小動物を殺していたというのは、ややテンプレ的な殺人を犯すサイコパスのイメージでしょうか。
しかし、初の殺人として琴絵を殺そうとしましたが失敗、抵抗に遭って自分が死んでしまいます。
琴絵を殺そうとした動機は、「本当の自分を見てもらいたかったお兄ちゃん」こと義兄・青柳史也との関係において、琴絵が邪魔だったからです。
「本当の自分」というのは、そういった破壊衝動・殺人衝動がある自分、ということなのでしょう。
このみは死んでしまいましたが、魂(?)は一緒に溺れつつも助かった琴絵の体内に入り込むことに成功。
普段は眠ったような状態で表には出てきませんでしたが、数年に一度?目覚めては殺人を繰り返していました。
その動機は「このみの魂が琴絵の中に入っていることをわかってもらうため」「本当の自分を理解してもらいたい」といったものだったようです。
この動機が若干飛躍を感じなくもありませんが、いずれにせよ、その殺人の後始末を史也に任せていました。
罪悪感に駆られた史也は、せめてもの償いに被害者を綺麗に安置し、「エンゼルケア殺人事件」の完成です。
それとは別に、このみは、史也が仲良くしている西条茜の身体に乗り移ろうと画策。
史也が茜の家に訪れたのは、このみが残した「あの子は連れていくね」という手紙が理由でした。
しかし、茜の家に先回りして到着できたのはいいものの、西条直昭が殴られ倒れているのに動揺し、茜に警察を呼ばせ、自分は警察と顔を合わせるわけにはいかないので撤退。
ここで茜から目を離したのは良くなかったですが、仕方なかったですかね。
さらにややこしいのが、茜にも解離性同一性障害疑惑があった点です。
解離性同一性障害だったのか、はたまた茜にも義兄・佑真の魂が乗り移っていたのか。
書き方的には解離性同一性障害っぽかったですが、やはり現実的に見ると無理があり、そういうフィクションとはいえ使い方はしてほしくないなぁ……とついつい思ってしまうので、ここは佑真が乗り移っていたとしておきましょう。
というのはまぁどちらでも成り立つのですが、いずれにせよ、直昭を殴ったのは佑真の魂(あるいは人格)であったと考えられます。
佑真の手紙にも「だから今回だって、俺は自分が正しいと思うことをしたんだ」とありましたし、茜の手錠が強引に引きちぎられていたことがそれを裏付けます。
青柳史也が行ったのだとしたら、この2点の説明がつきません。
以上が事件の流れでしたが、猟奇殺人、というほどに猟奇的な事件ではなかったような。
不可解な事件ではありましたが、事件としてのインパクトは、はやり『Book1《変身》』の方が強かったです。
そんな事件を解決したのは前作から引き続き、加地谷悟朗、浅羽賢介、天野伶佳の3人組に、新キャラ御陵伽耶乃が加わりました。
この4人が今後のメインメンバーとなりそうです。
まさかのボクっ娘・御陵伽耶乃はかなり個性強めで、アニメやラノベ、あるいはテキスト形式のアドベンチャーゲームのキャラのよう。
4人の掛け合いのシーンにもけっこうなページが割かれているので、キャラ小説的な側面も窺えます。
良くも悪くも、この4人が好きかどうかによって、この作品の評価にも影響しそうです。
個人的には、前作の感想でも述べましたが加地谷がいちいち暴力的かつ喧嘩腰すぎるのと、浅羽がいちいちチャラすぎるのと、伽耶乃がちょっと狙いすぎでは?感が否めず、ハマりきれていないというのが正直なところ。
4人の間でいちいち揉めているのも、それどころじゃないのでは……?と思ってしまったり。
ここは完全に好みですね。
今後はそれぞれのキャラも深掘りされていくのだろうと思うので、そこに期待。
ちなみに、伽耶乃のプロファイリングは、現代のプロファイリングとしてリアルな描かれ方ではありません。
プロファイリングは、そこはしっかりと作中でも伽耶乃が言及していましたが、基本的にデータと統計の結晶です。
伽耶乃が行っていた「無秩序型」という分類や「事件現場を見て、犯人像を推察する」というのは、初期のFBI式のプロファイリング。
これは、結局は経験やセンスが問われる職人技に近く、かつ、必ずしも客観的に正しいとは言えない(あるいは安定しない)ことが明らかになっています。
参考文献も2000年(翻訳ではなく原著は1992年)の『FBI心理分析官 異常殺人者たちの素顔に迫る衝撃の手記』などだったので、流行った書籍ですがちょっと古いイメージかな、と思います。
もちろん、伽耶乃はあえてそのようなエンタメ重視の設定にしているのだろう、というのはわかっています。
作中でも言及されていましたが、日本の都道府県で初めてプロファイリングを導入したのは北海道警察でした。
犯罪者プロファイリングには大きく2つ、上述した事例から分類するFBI式と、統計重視のリバプール式とがありますが、日本が導入したのはリバプール式です。
というわけで、そのあたりも含めて、本作はエンタメ作品と割り切るのが良いでしょう。
念のため、色々言っていますが好きなシリーズです。
そして、作家の方々の独特な文体や癖を探すのも好きなのですが、このシリーズ2作でかなり思ったのは、阿泉来堂の口癖(文癖?)は「独り言つ」ですね。
今後は、たびたび言及されていた加地谷の「猟奇的な事件を求める」という傾向がどうなるのかが一つの焦点でしょうか。
闇堕ちしてしまうのか、はたまた乗り切るのか。
加地谷の家族関係も気になりますし、というか結局あの買ってきた花は奥さんに渡せたのでしょうか。
「人として怪物と戦う」という表現がありましたが、本作の「怪物」以外にも、「怪物と闘う者は、その過程で自分自身も怪物になることがないよう、気をつけねばならない」というフリードリッヒ・ニーチェの『ツァラトゥストラはかく語りき』の言葉も意識されていそうな気がします。
これに続くのが、有名な「深淵をのぞきこむとき、その深淵もこちらを見つめているのだ」です。
そして何を隠そう、「怪物と闘う者は〜見つめているのだ」の文章を冒頭に引用しているのが、『FBI心理分析官 異常殺人者たちの素顔に迫る衝撃の手記』なのです。
そもそもバベルの古書の謎が気になりますし、那々木悠志郎シリーズに登場する人宝教との関係もあったりしても面白そうだなぁ……などと妄想。
何にしてもシリーズを読み進めないとまだまだ何もわかりませんし、この記事を書いている2025年4月現在では『Book3《肖像》』が出ているので、読んでからまた考えてみたいと思います。
追記
『バベルの古書 猟奇犯罪プロファイル Book3《肖像》』(2025/04/12)
続編『バベルの古書 猟奇犯罪プロファイル Book3《肖像》』の感想をアップしました。
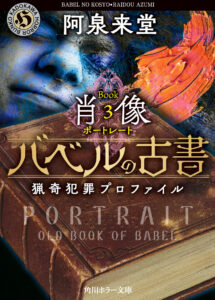
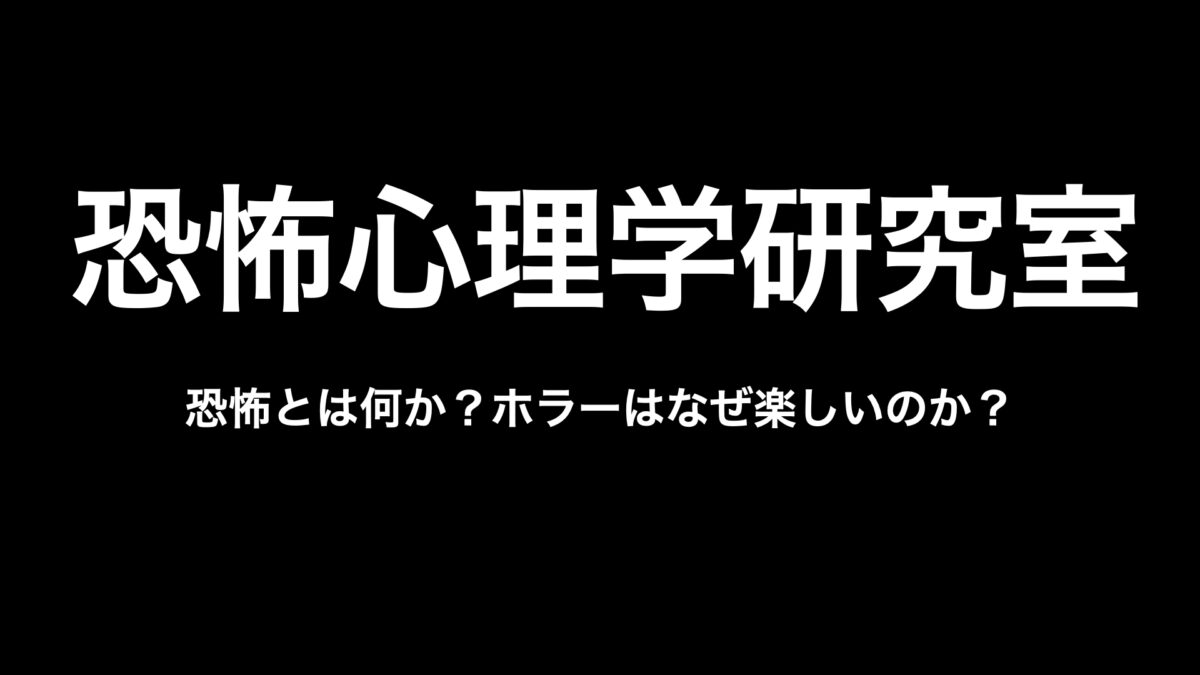
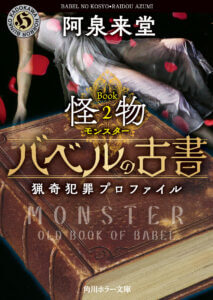
コメント