
作品の概要と感想(映画のネタバレあり、小説のネタバレなし)

ある大学生・雅也のもとに届いた一通の手紙。
それは世間を震撼させた稀代の連続殺人鬼・榛村からだった。
「罪は認めるが、最後の事件は冤罪だ。犯人が他にいることを証明してほしい」。
過去に地元のパン屋で店主をしていた頃には信頼を寄せていた榛村の願いを聞き入れ、事件を独自に調べ始めた雅也。
しかし、そこには想像を超える残酷な事件の真相があった──。
2022年製作、日本の作品。
観たかった作品、ついについに観てきました。
ベースとなる櫛木理宇による原作小説『死刑にいたる病』の考察については、以下の記事をご参照ください。
『キャラクター』と並んで、近年熱い日本のシリアルキラー作品。
基本的には原作の設定を踏襲しながら、映画用にうまくアレンジされて、展開や背景は(もちろん時間の都合があるので)だいぶ端折りながら、コンパクトにまとめられていました。
その分、映像による演出面がとても凝っていて、丁寧な描写でシリアルキラー・榛村大和の恐ろしさを浮かび上がらせていった原作に対して、映画はややリアリティを犠牲にしてでも、よりエンタテインメント性を重視して作られていた印象です。
グロさは、個人的には思っていたより全然でしたが、この点は自分の感覚がややおかしいのは自覚しているので、一般的にはけっこうグロいという感想が飛び交っている通りなのだと理解。
どこに重点を置くかによって当然感想は変わるかと思いますが、『死刑にいたる病』の映画化作品として、個人的にはとても楽しめるものでした。
小説の特徴は、榛村大和との直接の対話を通してよりも、関わりのあった周囲の人たちからのエピソードによって、榛村の人物像が少しずつ浮かび上がってくる点にあったと思っています。
人間は誰しも、人や状況によって見せる顔が異なりますが、榛村ほど人によって多様な印象を抱かせる人もなかなかいないでしょう。
小説の感想では「話を聞きに行ったみんながしっかりエピソードを思い出してくれるのが、少し都合の良い展開」といったことも書きましたが、それもそれだけ、良くも悪くも人の印象に強く残る人物だったと捉えることもできます。
しかし、この過程を忠実に映像化すると、とても地味になることは確実です。
映画版ではその過程を最小限まで省き、拘置所の面会室における直接の対話による榛村の柔らかさと、事件にまつわる回想シーンの猟奇性の対比を際立たせていました。
そして、徐々に対話をしている榛村の柔らかさが表面的なものに見えてきて、ハイライトのない黒目に吸い込まれていくような、不気味さや恐ろしさが強調されていく。
その意味では、阿部サダヲありきの演出だったとも言えます。
そのバランスの崩し方はやや過剰でもあり、ところどころ突っ込みたくなるような演出やシーンも見られますが、白石監督自身「自分の作品のなかでもエンタメに徹している」と述べているようで、あえてそのような方向に振り切ったのだと考えられます。
白石監督による「死刑囚との面会を通して真実を探っていく」という構図は、映画『凶悪』に通ずるものがありますが、『凶悪』の方が絶望やダークさは圧倒的でした。
『凶悪』と対比すると『死刑にいたる病』のエンタテインメント性は明らかで、日本映画史に残る印象的なシリアルキラーとして榛村大和を描こうとしていたように感じられました。
そのバランス調整により、榛村大和のシリアルキラー像と筧井雅也の心理描写は、原作とは大きく異なるものになっていました。
原作では、それぞれの生育環境や心理描写が複雑に絡み合いながら展開していくので、映画単体で見たときには、どうしても細かい動機や行動は不明瞭さが目立ってしまうのではないかと感じました。
それはもちろん映画における限界として仕方ない点ですが、原作未読で「結局何でこんなことしてたの?」というのがわかりづらかった方は、ぜひ原作も読んでいただけたらと思います。
後半の考察部分では、心理学的な視点も使いながら、小説との違いや比較を通して、映画における描かれ方を考察していきたいと思います。
考察:原作小説との比較を中心に(映画と小説のネタバレあり)

小説と映画の設定の違いあれこれ
まずは考察のベースにもなるので、小説と映画で設定が異なる点、およびその理由の推察を整理していきます。
榛村大和、筧井雅也、加納灯里については、後ほど別に触れます。
①金山一樹
榛村大和の過去の獲物にして、冤罪を主張した根津かおるの事件にも深く関わっていた金山一樹。
金山一樹と加納灯里が、映画版において原作から大きく変化したトップを争う2人でしょう。
映画版の金山一樹は、とにかく怪しい。
見た目から言動から、岩田剛典とは思えないぐらいめちゃくちゃ不審者です。
小説では短髪と描写されていましたが、映画版では顔を隠すほどの長髪。
これはおそらく、父親から「男らしくない」と言われて虐待を受けていたのをわかりやすく体現していたのが一つ。
聞き込みの過程で「髪の長い男」として気づきやすい、確認しやすいのが一つ。
そしてもう一つ、とにかく「怪しいキャラ」として演出されていたのは確実です。
小説では、榛村大和の冤罪の主張に対して、依頼を受けた筧井雅也は、最初は半信半疑のまま調査を進めていきます。
雅也視点で進むため、読者も「実際どうなんだろう」「何がどうなっていくんだろう」と先がまったくわからないまま話が進んでいきます。
映画では、「本当に冤罪なのでは?」と思わせる演出が強調されており、わかりやすくミスリードさせる「明らかに怪しい存在」として金山一樹が使われていた印象です。
映画序盤で、犬を連れていた山の持ち主(?)の女性が「最近でもお参りに来る女性がいる」といったようなことを言っていましたが、最初はその人物と金山一樹を結びつけさせず、あとから判明することで、怪しさが一気に際立つ効果にもなっていました。
「俺が殺したんだ」と呟き、逃げる雅也を長髪を振り乱して追いかける姿はもう、確信犯でしかないですよね。
②佐村弁護士
榛村大和の弁護人、佐村弁護士。
だいたいが小説よりやばい方向に傾いている登場人物の中で、唯一まともな方向に傾いていた人物です。
そのせいで、特に見せ場もないただの弁護士になってしまっていました。
小説『死刑にいたる病』における衝撃のラストシーンは、佐村弁護士すら榛村大和の支配下にあった、というものでした。
祖父から続く弁護士事務所の3代目としてコンプレックスや焦りを抱えていた佐村弁護士。
そのため彼は功を焦り、榛村のために尽力し、一介の大学生である筧井雅也に事件の資料を郵送して、聞き込みのために事務所名義の名刺まで作って渡していました。
その点を、小説の考察では「現実でやったらえらいこっちゃ」と指摘しました。
その指摘を踏まえて(違う)、映画における彼は「事務所でしか資料は見ちゃ駄目」「勝手に名刺作って使ってるでしょ?知ってるんだからね。駄目駄目」と、かなり常識的な反応を示します。
しかし、雅也を1人にして資料を見せたのが甘かった。
1人になった雅也は、事件資料を速攻スマホで撮影して、まさかの自宅で印刷して壁に貼るという暴挙に出ます。
たぶん、普通に違法行為。
ちなみに、被害者たちの写真を部屋の壁に貼るという、このシーンがなぜ必要だったのか。
常識的に見れば「いや、何やってんの?」としか思えない、狂気すら感じる雅也の行動で、これは専門的知識に関係なく観客一同、同感でしょう。
それをあえて入れ込んだのは意味があるはずで、それは何だろうかというと、やはり視覚的な演出効果です。
被害者の写真を並べることで、「24人の人間を殺した」という言葉だけを聞くよりも、「これだけの人間が実際に榛村大和によって殺害されたのだ」という実感が湧きやすく、猟奇性が際立ちます。
客観的に見れば雅也がだいぶやばい奴なだけですが、映画の中でも印象的なシーンで、とても効果的だったと思います。
そのためには、雅也が事件資料を手に入れる必要があった。
資料をそのまま郵送するというのは、さすがにまずいという判断があったのでしょうか。
代わりに、事務所の中だけで見せるけどあっさり盗撮されてしまう、というただのお間抜け弁護士になってしまった佐村弁護士。
事件資料を大学生に渡すという弁護士としてあるまじき行為に至るか、あるいは勝手に資料を盗撮されるという間抜けな弁護士となるか、いずれにしても佐村弁護士にとっては究極の選択。
さらには、ラストの見せ場も完全に加納灯里に持っていかれてしまい、大きな見せ場もなく踏んだり蹴ったり(?)な佐村弁護士でした。
③筧井雅也の家庭環境
雅也の鬱屈したパーソナリティ形成に大きな影響を与えていた家庭環境。
それも、だいぶ簡素化されたものになっていました。
まず何より、おばあちゃん、亡くなってました。
雅也の教育の主導を握っていた、父と祖母。
養子だったこともあってか、立場の弱かった母。
中学生までは優等生でしたが、高校に入学してから「落ちこぼれ」になったことで、父の失望を感じ取り、家に寄りつかなくなっていた雅也。
小説の雅也は、何度も実家に足を運ぼうかと迷いながら、結局逃げ帰り、終盤でようやく勇気を振り絞って母を訪ねて実家に足を踏み入れます。
一方、映画の雅也は、それはそれは頻繁にあっさりと実家で過ごしていました。
とはいえもちろん平和な家庭ではなく、父との確執も描かれますが、小説ほど複雑ではなく、「ただFラン大学が気に入らないんだろ」程度に端折られます。
ただ、さすがにあまりあっさりと普通に実家に出入りし過ぎていると、榛村大和に傾倒していく雅也の心理状態からはかけ離れてしまうため、「祖母が亡くなった」という実家に戻らざるを得ない状況に設定したのだと思います。
小説では、実際にはほぼ登場せず、「口うるさく支配的」と表現され厳格なイメージがあった雅也父ですが、映画ではだいぶぬぼーっとしたホラーな存在に。
「喪中だぞ……はしゃぐなっ」はちょっと笑ってしまいました。
以上が、省略された点は除き、大きい部分での変更点でした。
映画版・榛村大和のシリアルキラー像
さて、映画における、阿部サダヲ……じゃなくて榛村大和。
彼はもう、犯罪心理学的には「よくわかんないやばいモンスター」と化していました。
小説において榛村大和は、典型的な秩序型の快楽殺人によるシリアルキラーとして描かれていました。
その主たる動機は、自らの欲求を満たすためです。
また、自身の嗜好とは異なる根津かおるの殺害を行ったのは、自身の逮捕後、さらにはおそらく死後まで金山一樹を支配するため。
筧井雅也にそれを冤罪と主張して調べさせたのは、彼を思い通りにコントロールする快感を得るためのゲームでした。
映画『ザ・シェフ 悪魔のレシピ』の考察などでも引用していますが、連続殺人犯のタイプを分類したホームズとデバーガーという研究者による「連続殺人犯の4類型」は、以下の通りです。
- 幻覚型(visionary):妄想性の精神疾患に罹患しており、幻覚妄想に基づいて殺人を行う
- 使命型(mission):偏った信念によって、特定のカテゴリーに属する者を殺害する
- 快楽型(hedonistic):拷問したり殺害することで、サディスティックな快楽や性的快楽を得る
- パワーコントロール型(power/control):他人の生死を自分がコントロールできるという、力と支配の感覚を得るために殺人を行う
これによれば、小説の榛村は「快楽型」あるいは拷問による支配の快楽という意味では「パワーコントロール型」に該当します。
しかし、映画では、性的な興奮を得ていたという描写はほとんどなく、欲求を満たすためというのは間違いありませんが、その根本はあまりはっきりと描かれていませんでした。
相手をコントロールすることに愉悦を覚えるという点では、「パワーコントロール型」に該当する側面が強くなっています。
榛村のモデルの1人になっていると思われる実在のシリアルキラー、テッド・バンディも、ホームズは「パワーコントロール型」に分類しています。
しかし、そのパワーコントロールのもとになっているのはやはり性的欲求と考えられており、支配と性欲が結びついたという観点では、「快楽型」の1類型とも見られています。
ただ、振り返ってみれば小説でも、根津かおるの事件以外では、強姦や性的暴行といった表現が直接的に描かれているケースは、少年に対する1件のみであったはずで、詳細は曖昧です。
性的な関心を有していた対象が被害者となっていたことは示唆されていますが、立件された事件は「9件の殺人及び死体遺棄、死体損壊罪」と表記されていました。
強姦まで含まれれば「強制性交等罪」となるはずで、実はもともと直接的な性的暴行は行っていなかったのかもしれませんが、基本的に死体は処分していたので、証拠が集まらなかっただけかもしれません。
ただ、通常、シリアルキラーはほぼ同じ内容でこだわりのあるような犯行を繰り返すことが多いので、1件強姦があったということは、他も同様の快楽殺人であったと考えるのが自然です。
ただ、映画ではその点がより一層、薄まっていた印象です。
せいぜい「好みのタイプ」という表現程度で、少なくともはっきり描かれていたのは、拷問をして相手をいたぶることを楽しんでいた、というシーンのみでした。
性的快楽がないのに好みのタイプの対象に拷問・殺害を繰り返すというのは、犯罪心理学的には説明がつきづらい存在となってしまいます。
そのような動機が薄くなると人間味が失われ、「ただ痛めつけて殺したいから殺す」という「純粋な悪」となります。
唯一心当たるとすれば、支配欲程度。
悪役としては抜群ですが、フィクション性も高い存在に昇華されています。
複雑な生育歴も、映画ではほとんどカットされていました。
特に実母の新井実葉子に関しては、せいぜい名前が出てくる程度。
過去に関しては、関係者から言葉でさらっと語られるのと、中学生時代に小学生女児を暴行した事件ぐらいでしょうか。
ポジティブなエピソードが除外されることにより、「生粋の狂人」感が強められています。
小説の中では、榛村大和を良く言う人もいれば、悪く言う人もいる。
そういう対比の中で、徐々に人を魅了する側面と、その裏の冷酷さのコントラストが明らかになってくる。
そういう構図だったのが、映画では過去を排したことで、突然変異のモンスターのような存在となっています。
相手の支配やコントロールに関しても、「相手が求めていることを敏感に嗅ぎ取り、言葉巧みにコントロールする」というよりも、「もはや魔法のように相手を思いのままに操っている」印象を受けました。
ただ、時間の都合もあったでしょうが、これらも意図された点なのだろうとも感じます。
小説では典型的なシリアルキラー像であったのに対して、映画では殺人のための殺人を行い、どんな相手でも思い通りに操れるような、超常的な存在になっていました。
冤罪主張による雅也への依頼に関しても、コントロール感による愉悦を感じるために行っている感じでもなく、動機や目的はいまいち不明で、「ただそのように他者を操ることができる存在」として描かれていたように感じました。
その意味では、一番エンタテインメント性に振り切られたキャラクタになっていたと言えるでしょう。
映画における榛村大和は、「シリアルキラー・榛村大和」よりも、「一般的にイメージされるサイコパスっぽさ」を増幅させて「やばいモンスター殺人鬼・阿部サダヲ」に特化したと表現しても、決して過言ではないように思いますがいかがでしょうか。
榛村大和を阿部サダヲが演じたというより、榛村大和と阿部サダヲを掛け合わせて新たなモンスターを生み出したようなイメージです。
それらの「イメージ映像」として、冒頭の花びらのように爪を撒くシーン、面会室のアクリル板の反射をうまく利用して榛村と雅也の姿を重ね合わせるシーンなどが、とても象徴的に機能していました。
さらに言えば、だからこそ「え、これは、ありなのか……?」と観客を若干戸惑わせながらも、若き日の榛村大和もお肌つるつる謎の髪型にしてまで阿部サダヲにこだわったのだと思います(戸惑いましたよね?)。
ただ、専門家の端くれとしてあえて水を差すようなことを言わせていただくと、本作を通して「やっぱりサイコパスって怖い」という、それこそ「サイコパス=モンスター」といったような偏ったイメージが助長されないといいな、と思います。
少し余談としては、小説では曖昧だった榛村の犯行手口が明らかになりました。
お店に来た客や近隣で見かけたターゲットに対して、用意周到に準備して拉致する。
榛村の二面性や猟奇性が強調されると同時に、警察が完全に無能判定を下されることとなりました。
映画版・筧井大和に何が起こったのか
阿部サダヲのインパクトに持っていかれがちですが、筧井雅也を演じた岡田健史の演技は素晴らしく、今後躍進されていきそうです。
最初は観ているこちらが心配になるほど目を逸らしておどおど喋っていたのが、徐々に相手の目を見てはっきり喋るようになり、最後には狂気すら孕んだ目で睨みつけるようにまっすぐ視線を向ける、という雅也の変化を、しっかりと表現していました。
小説では、就活面接など色々なシーンを利用したり、雅也の心理描写や、加納灯里だけでなく周囲の人間からの「前と変わったね」という言葉などによって描写されていた雅也の変化は、映画で表現するのが一番難しい点の一つだったのではないかと思います。
それはさておき、筧井雅也の人物像は、上述した色々な設定の変化により、一番影響を受けたものと考えます。
それにより、雅也の内面で起きていたことは、小説とはまるで異なるものになっていました。
上述した通り、小説ではほとんど実家を忌避していた雅也は、映画では確執はありながらもそれなりに頻繁に顔を出しています。
榛村大和の話になりますが、小説では「雅也は実家に帰ったり母親(衿子)に連絡を取らないと思っていた」という榛村の雅也に対する分析が、雅也の行動をコントロールしたり、榛村が実の父親だと勘違いさせる要因となっていました。
この点も、雅也の実家との距離感が変化したことによって、「相手の心理や行動パターンを掌握した上でコントロールする」という、相手に合わせたマインド・コントロールに秀でている小説版・榛村の側面を薄れさせ、「魔法のように相手を操る」という映画版・榛村の超常性に繋がる要因となっています。
それによって必然的に、雅也が榛村にコントロールされる心理にも、変化が生じます。
小説版の考察にも詳しく書いていますが、
- 前提として、母親の影が薄く、父親と祖母が雅也の教育の主権を握っていた家庭環境
- 優等生だった雅也は、高校進学後に落ちこぼれる
- 父親に失望され見放され、自己肯定感も大きく低下
- しかし、「本当の自分はこんなんじゃない」という歪んだ自己愛を抱え続ける
- 榛村に自分を必要とされ、承認欲求を満たされて頑張る
- 実の父親と勘違いした(させられた)ことなども重なり、徐々に榛村に傾倒し同一化していく
- それにより、もともと潜在的に有していた攻撃性や自己愛が発現し、他者を殺害しようとした
というのが、小説における雅也の大まかな心理過程です。
これが映画だと、
- とりあえず自己肯定感は低くてコンプレックスは抱えていそう
- 榛村に必要とされ、承認欲求を満たされて頑張る
- 榛村の緻密な計算によるコントロールではなく、家族間の会話が奇跡的な噛み合い方をして、榛村が父親だと勘違いする
- 榛村に魔法のように操られ、他者を殺害しようとする
といった流れになっていました。
細かい部分はさておき、重大なポイントは、「もともと雅也が抱えていた危険性が榛村に刺激されて発現した」のが小説であるのに対し、「榛村に操られて他者を殺そうとした」あるいは「連続殺人犯である榛村の息子であると思い同一化したことで殺人を犯そうとした」のが映画です。
「結局殺せなかったので、自分はあなたの息子ではないとわかった」という、とても物議を醸しそうな発言が、それを象徴しています。
「実はもともと自身が大きな危険性を抱えており、それをうまく操られた」というのでなく、ただただモンスター榛村に操られて影響を受けて終わった。
それが映画における雅也の悲しい現実です。
あと、何もかも未遂で終わった小説とは異なり、あそこまで殴りかかって首まで絞めるという行動の実行に至った映画版・雅也は、殺人未遂あるいは暴行・傷害で捕まるのも時間の問題でしょう。
あんなにあからさまに口元に殴られた痣がありながら、中学校関係者にも塾関係者にも虐待の対応をしてもらえなかったのはかわいそう。
映画版・加納灯里の大躍進
さて、映画版で一番謎が多いのがラストであり、それはつまり、加納灯里の存在でしょう。
彼女に何が起こったのか。
元も子もない結論としては、はっきりわかりません。
ただ、榛村大和の魔法にかかった、という解釈なのだと思います。
上述した通り、細かい部分の調整により人物像は変化している榛村や雅也ですが、「榛村が雅也を操り、その魅力的な仮面に騙され感化されていく」という大筋は、映画も小説を踏襲しています。
では、どこに映画版のオリジナル要素を置くか。
そこで白羽の矢が立ったのが、加納灯里でした。
小説版でも、加納灯里も榛村が狙っていた元獲物であり、現在の「遊び」のターゲットにされていて、雅也と交際に至ったのも榛村の影響によるものだった、という、佐村弁護士と並んでラストに不穏さを残し、榛村の影響力を示す被害者として描かれていました。
しかし、映画版・加納灯里はその比ではありません。
まず、殺人未遂で帰ってきた雅也をアパート前で待ち受けると、事情も聞かずに出血ぺろりんちょで、小説未読の観客はもちろん、原作予習済みの観客まで度肝を抜かれます。
その後は、ぺろりんちょについては何も触れずに、雅也すら突っ込んでくれず、観客をやきもきさせたままラストシーンへ。
榛村の手紙が出てくるところは原作予習者の想定内ですが、「爪、剥がしたくなる?」「好きな人の一部を持っていたいの、私はわかるな」というサイコパス風発言で、すべてを掻っ攫います。
これもあくまでエンタテインメント的演出の一つであり、小説を読んだ人にも驚きを与えたいというのと、インパクトを残す終わらせ方としての選択でしょう。
かといって、小説の世界観をぶち壊すものではなく、気に入る気に入らないは当然あるにしても「原作ファンからは総批判」にはならない、さらには映画版・榛村の特徴である超常性を際立たせるという、とても巧みな演出だと感じました。
結局どういうことなのか?の答えはないのでしょうが、映画の雅也は、自身が抱えていた危険性によって殺人の衝動が感化されたわけでもなく、ただ榛村の魔法のような影響によって殺人衝動に至っていたことを考えると、灯里も同じように影響を受け、それに呑み込まれかけていると考えるのが一番妥当でしょうか。
あるいは、原題を活かして、あえて「病」のようなものとして捉えたか。
いずれにしても、原作から一番大躍進したキャラクタであることは間違いありません。
あのあと、雅也が無事であったことを祈ります。
おまけ:拘置所小ネタあれこれ
最後に少しだけ、作中に出てくる拘置所に関する小ネタの解説・ご紹介です。
小説では固有名詞までは描かれていなかった榛村と雅也の面会場所ですが、映画では東京拘置所としてはっきりと描かれていました。
雅也が降り立ったのは小菅(こすげ)駅でしたが、実際に東京拘置所の最寄駅です。
その後、拘置所に向かいながら外観が映りますが、あれは本物の東京拘置所です。
東京拘置所は、2000年前後に改築工事がなされており、かなり綺麗で大きく近代的な、けれど無機質さや威圧感のある建物。
さすがに、内部の様子は実際のものではありませんでした。
受付や待合室、廊下も、似せてはいますがすべてセットです。
面会室も、当然ながら本物ではありませんが、雰囲気は似ています(面会室はどこも似ていますが)。
何もない小部屋がアクリル板で区切られており、パイプ椅子が置かれているのみ。
もちろん実際はあんなに暗いことはなく、逆に、白い壁で家具など何もないので、蛍光灯だけでも必要以上に明るく感じます。
あの暗さは、演出的な意味合いはもちろん、心象風景の投影でしょう。
榛村が入ってくる側のドアに、小窓がついているのに気づかれたでしょうか。
榛村が入室する前に、それがちらっと開きます。
あれは、本当に面会する相手で良いかどうか確認するためのものです。
拘置所の面会は、弁護士以外は1日1件など限りがあります。
そのため、雅也も書いていた面会の申込用紙の内容が収容者にも伝えられて、面会をするかどうか確認が取られます。
しかし、センセーショナルな事件などでは、親族の名前や連絡先を騙って突撃しようとするジャーナリストなどもいないとも限りません。
そのため、面会直前にも、一応相手を直接確認させているのです。
面会室は、アクリル板で仕切られており、収容者と面会者が直接触れ合ったり物を渡すことはできません。
他のドラマや映画でも面会シーンはよく出てくるので、アクリル板に小さく穴が開いているのを見たことがある人も多いと思います。
あれは声を通すための穴ですが、『死刑にいたる病』では、その穴が見当たりません。
これはビジュアル面を重視した結果でしょうか?
答えは否で、以下のシーンがわかりやすいですが、アクリル板の下部に、横に伸びる銀色の部分が見えると思います。

ここに声を通す小さな穴がたくさん開いており、東京拘置所の面会室は実際、こういった形になっています。
ちなみに、この形であれ、普通にアクリル板に穴が開いている形であれ、声はだいぶ通りにくいため、それなりに声を張らないと聞き取りづらくなります。
現実は、映画序盤の雅也のようにぼそぼそと喋ると、「え?」と思い切り耳を近づけないと聞こえないでしょう(それでも聞こえないかも)。
さて、死刑判決が確定した死刑囚はどこで過ごすでしょうか。
答えは、刑務所と思われることも多いですが、拘置所です。
ものすごく雑に言いますが、
- 警察に逮捕されたときに勾留(家に帰してもらえず身柄を拘束)されるのが警察署にある留置場
- 警察の取り調べが終わり、起訴されて裁判を控えている人が勾留されるのが拘置所(この段階で身柄の解放が許可されるのが保釈)
- 実刑判決を受けて、懲役刑になった人が収監されるのが刑務所
です。
刑務所は、あくまで懲役刑の刑罰として、身柄を拘禁されて自由を奪われ、刑務作業などを行う人が行く場所です。
死刑囚は、死ぬことが刑罰であるため、それまでの期間、刑務作業などは行いません。
身柄は拘束され続けますが、個室が与えられ、枠組みの中では比較的自由に過ごせます(それを自由と呼べるかはさておき)。
刑場(死刑を執行する場所)は主要な拘置所にあるので、死刑囚がいる場所は拘置所となります。
もちろん、東京拘置所にも刑場があります。
以上が、主に東京拘置所に関する小ネタでした。
映画『死刑にいたる病』では、拘置所や面会室は比較的リアル寄りに再現されていた一方、本筋とあまり関係ないからか、裁判や法廷の描写はだいぶ実際の雰囲気からは離れ、簡易的でした。
東京地方裁判所の法廷に関しては、「キムタクが如く」とも呼ばれる『JUDGE EYES:死神の遺言』というゲームが、実は完全再現と呼べるほどの忠実さです。
興味がある方は、ぜひプレイしてみてください。
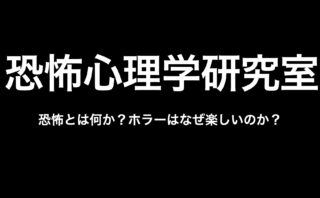







コメント