
作品の概要と感想(ネタバレあり)
タイトル:コクーン
著者:葉真中顕
出版社:光文社
発売日:2019年4月11日(単行本:2016年10月17日)
1995年3月20日、カルト教団「シンラ智慧の会」通称「シンラ」の教祖、天堂光翅の命を受け、白装束に身を包んだ6人の信者が、丸の内で無差別乱射事件を起こす。
その宗教は、1958年に1人の女性が呪われた子を産む決意をした日に始まる。
たとえ今、生きる意味が見出せないとしても、もしかしたらこの子は、私に生きる意味を与えてくれるかもしれないと──。
一気に読んでしまい、個人的に大好きな作品となりました。
文章もとても読みやすく、有名な著者ですが初めての作品だったので、これから他も読んでいきたい。
『コクーン』は短編集としても読めますが、すべてが繋がっているので、一つの長編作品として捉えました。
「オウム真理教」をモチーフ、というよりモデルとした「シンラ智慧の会」を軸として扱っているだけに、内容は暗め重め。
ただし、直接的にシンラ智慧の会の内部や事件を描いているわけではなく、シンラを取り巻く様々な人たちの心理が丁寧に描かれています。
それが逆に、シンラはあらゆる人々に影響を与えたんだなということを浮き彫りにしています。
上述した通り、大きくは4つのエピソードから成っていますが、それぞれのエピソードが時に重要に、時にさり気なくリンクする構成。
同じ著者の異なる作品で世界観や登場人物がリンクするというのは個人的に好きなのですが、その感覚を味わえる作品でした。
「蝶夢」も含めたそれぞれのストーリーが一つにまとまっていく構成は、見事としか言いようがありません。
この作品の刊行後、オウム真理教の死刑囚たちは、2018年に死刑が執行されています。
いわば現実のパラレルワールドとして描かれた『コクーン』では、教祖の天堂光翅こと卯藤新は拘置所内で(おそらく)病死しました。
「蝶夢Ⅴ」では、死が間近に迫った卯堂カナ(卯藤新の母親)の視点で、「コクーン」というタイトルの意味が明かされます。
無数にあるパラレルな世界=繭の中では、シンラが事件を起こさなくとも、よりひどい事件(=オウム真理教)が起こっていた。
それにより、卯藤カナは救済や命の意味を感じていました。
この点、個人的にはやはり違和感というか、自己中心性を感じてしまいました。
しかし、被害者や被害者家族はもちろん、加害者家族もまた、強い苦しみや悩みを抱いています。
加害者を産んだ母親であればなおさらです。
そんな彼女が、ホームレスにまでなった人生の最期に、救済や自らの命の意味、そして息子の命の意味を求めたことは、自然であるとも言えるでしょう。
著者自身、インタビューで「このラストは読者によっていろいろな受け止め方があると思います。身勝手な救済じゃないかととらえる人もいるかもしれない。それは予想しています。でもフィクションだからこそ、現実では許されない形の救済も描くことができるはず。そうすることで初めて見えてくる世界もあると思います」と述べている通り、あえて描かれたこのシーンは、人それぞれの捉え方があるべきシーンなのだと思います。
追加された掌編では、“沼”と名乗り、天堂光翅こと卯藤新ことマンザイのあとを継ぐように、第2章「シークレット・ベース」の主人公である三枝宏道が布教をしている様子が描かれており、不穏さを残す後味の悪いラストです。
これは、シンラ智慧の会や天堂光翅が消えても、カルトがなお新しく現れてくる危険性を示唆するものです。
後味は悪いですが非常に現実的であり、実際、オウム真理教もその後続団体をいまだ公安は注視していますし、新たなカルトは次々と誕生しています。
ちょうどカルトが話題になっている昨今ですが、カルトは誰にとっても他人事ではない、大きな問題の一つなのです。
考察:オウム真理教との繋がりと、カルトの恐ろしさ(ネタバレあり)
オウム真理教との繋がり
『コクーン』に出てくるシンラ智慧の会はオウム真理教をモデルとしていることは、誰がどう読んでも明白ですし、著者のインタビューでも明言されています。
犯行日もまったく同じ1995年3月20日。
オウム真理教は、改称前は「オウム神仙の会」という名称でした。
シンラ智慧の会は、こちらにインスパイアされた名称でしょうか。
シンラというと、ゲーム『ファイナルファンタジーⅦ』の神羅カンパニーが浮かんできてしまうのはさておいて。
「森羅万象」でも使われる「シンラ」ですが、「無数に並び連なること」という意味の他に「天地の間に存在する諸々のもの」といった意味があります。
このあたり、もちろん実在の宗教などをベースにはしているのですが、名称や教義の設定など、とても綿密に練られており、いかにもあり得そうな印象を受けました。
名称に関しては、「天地の間に存在する諸々のもの」というのがいかにもしっくり来ますが、後述する無数のパラレルワールド=繭というのが「無数に並び連なること」という意味合いと解釈すると、非常に優れたネーミングです。
さて、シンラ智慧の会の教祖・天堂光翅こと卯藤新については、幼少期が少し描かれていました。
「マンザイ」というあだ名で登場し、のちに卯藤新であることが明らかになりますが、その事実は最初はわからないようになっています。
第2章「シークレット・ベース」の主人公である三枝宏道視点では、マンザイは明るく友達思いなキャラとして描かれていました。
一方で、“沼”と呼ばれる地域に住む者として自身や母親を馬鹿にされることには、悔しさを感じてもいました。
このキャラクタや生育環境は、オウム真理教の教祖・麻原彰晃こと松本智津夫とは大きく異なります。
純粋に見える卯藤新がおかしくなっていったのは、三枝宏道の母親の新しい恋人である「ベムラー」が話すスピリチュアルなトンデモ理論の影響が大きかったと考えられます。
また、誰が殺害したのかは明らかにされていませんが、マンザイがベムラーを殺害したのであれば、その体験も影響しているかもしれません。
ただ、彼が天堂光翅となり、テロへと向かっていく過程は、本作ではあえて描かれていません。
一方、第4章の「パラダイス・ロスト」に登場するパティシエである「僕」。
彼の生い立ちこそ、松本智津夫に一致するものです。
具体的には、以下の要素。
- 熊本県出身
- 9人きょうだいの第7子として生まれた
- 片方の目は見えず、片方だけ視力を有している
- 全盲ではなかったが、貧しい家庭であったために盲学校に入れられる
- 卒業後は一時期、全盲の兄が営む鍼灸院を手伝う
これらは完全に一致しており、「僕」は明らかに松本智津夫に重ねて描かれています。
しかし、「『コクーン』の世界」では、彼は松本智津夫と同じ道は歩みませんでした。
その分岐点は、他の登場人物と同じく、黄金の蝶に導かれたところなのでしょう。
あの分岐でお菓子と出会い、彼はパティシエの道を歩み始めます。
夢で見たのは、彼にとっては「あり得たかもしれない世界」であり、我々にとっての「現実」です。
黄金の蝶は、バタフライ・エフェクトを体現する存在でしょうか。
しかし、世界は巨大な「システム」でしかない。
そのため、たとえ「僕」がテロを起こすカルト宗教(=オウム真理教)を設立しなかったとしても、卯藤新が天堂光翅となり、シンラ智慧の会を立ち上げ、結局は1995年3月20日にテロを起こしました。
きっと、また別の世界線においても、別の人物による何かしらの事件が起こっているのでしょう。
カルトの恐ろしさ
『コクーン』の全4章、そして各章の間に挟まれる蝶夢は、どれもがそれぞれ重い内容を含んでいます。
しかし、中でも個人的に一番重々しく感じたのが、第4章の「パラダイス・ロスト」でした。
これは、カルトによって日常が壊されてしまう恐怖を、とてもリアルに描いています。
「自分はカルトには引っかからない」と過信している人ほど危ないということは、すでにカルトやマインド・コントロールの研究でも明らかにされています。
マインド・コントロールされやすい要因として、依存的なパーソナリティなどが挙げられていますが、他にも条件が整えば、誰もが引っかかってしまう可能性を孕んでいます。
特に、所属感や精神的に不安定なとき、たとえば卒業から就職までの間や、近しい人の死や喪失体験、自分や家族が病気になるなどの状況下では、誰しもリスクが高まります。
「僕」の妻である繭子は、シンラ智慧の会にのめり込んでいってしまいました。
結婚、そして出産を経て、この世に生まれた意味を「あなたと、この子と、家族になるためだったのね」とまで言い、幸せの絶頂にあった繭子がシンラにのめり込んでいったのは、一見違和感があります。
しかし、繭子の生育環境は過酷なものでした。
繭子は母親からお湯をかけられるなどの虐待を受けていましたが、それを「自分が悪い」と自分のせいにして正当化しようとする心理は、被虐待児に多々見られます。
慢性的に虐待のある環境下で育つと、「怒られないように」というのが最優先になり、自分の都合よりも、相手の顔を窺うことが優先されるようになります。
それは、生きるための手段なのです。
そんな繭子は、根底には、他者に対する疑念や、「何で自分だけ」という社会への恨み、そして自己否定感などを抱えていました。
「僕」と出会い、娘の瑠璃を産んで幸せを感じ、上述した台詞を発したのは、その瞬間は本心であったはずです。
しかし、根底が不安定なものであり、依存的な傾向を有していた繭子は、その時々の感情に流されやすく、些細なきっかけで揺らぎやすい危険性をもともと持ち合わせていたと推察されます。
お互い自信がないので踏み出せず、しかし両想いとわかった途端、いきなり同棲して激しく愛し合うなど、「僕」と繭子にはやや極端な傾向も見られます。
繭子だけでなく、同じように親からは見捨てられたような生育環境で育った「僕」も根底には不安定さを抱えていたことが推察され、その2人が一緒になったことで、極端な密着と、しかし根底の不安定さが混在していたと考えられます。
ただし、「僕」は黄金の蝶に導かれて洋菓子と出会い、師匠の浅野さんに出会えたことで、かなり安定したパーソナリティを築いていた印象です。
もちろん幼少期の環境ですべてが規定されるわけではないので、このエピソードは、その後の出会いや環境がいかに重要かを物語っています。
一方の繭子は、「僕」以外にはあまり恵まれた環境にはなかったのでしょう。
曖昧な世界に対して、明確な「答え」を提示された繭子は、一気にシンラにのめり込んでいってしまいました。
また、繭子は、オーガニック商品を扱う店に出入りするようになったのが、シンラに呑み込まれるきっかけでした。
これは非常にリアルなプロセスであり、「カルトです」と近づいてくるカルトはありません。
そのほとんどが取っかかりとしては他の団体を装っており、それはオーガニック商品を扱う店であったり、ヨガや瞑想を行う団体であったり、様々な問題を取り扱う研究会であったり、スポーツチームであったり、インカレサークルであったりするのです。
それらを通して、彼らは体系化された最新の勧誘技術を駆使して信頼を得て、徐々に取り込んでいきます。
誰しもが取り込まれ得る。
それは、自分はもちろんですが、身近な存在が突如のめり込んでいってしまう可能性もあるということです。
カルトであるほど、排他性が強くなります。
つまり、外部との接触を断たせようとするのです。
そのため、家族との縁を切らせて、それこそ〈繭〉のような、閉鎖された環境で過ごすことを半ば強制します。
たとえば、映画『サクラメント 死の楽園』で描かれていたコミュニティも、また同じです。
そのために、シンラのように「出家することは、家族の魂を高めることにも繋がる」といったような戯言でたぶらかします。
それを信じてしまうと、たとえ家族から反対されても、「真実の視点」で見れば「自分が出家することで家族も幸せになる」と思い込んでしまい、何とか思い留まらせようとする家族との議論は平行線となってしまいます。
信仰に対して「説得」しようとすることは、無意味であるどころか、相手を意固地にさせるような逆効果になってしまうのです。
繭子もまた、「僕」がどれほど説得しようと議論は噛み合わず、そのまま去っていってしまいました。
娘とともに残された「僕」の無念さや無力感は、察するに余りあるものがあります。
直接的なテロや犯罪行為に限らず、その存在自体が個人や家族を崩壊させ、人生を破壊してしまう。
それがカルトの恐ろしさです。
オウム真理教について
オウム真理教について詳述したいところですが、そうすると余裕で1冊の本になってしまうので、ここでは『コクーン』と関連する部分以外、細かくは割愛しました。
オウム真理教は『コクーン』でも少し触れられていた通り、1995年3月20日の地下鉄サリン事件以外にも、複数の殺人事件を含む多くの事件を起こしています。
信者が施設内で死亡し、それを隠蔽するために死体を処分したというのも、経緯や方法は多少違えど、現実にあった話です。
オウム真理教については多数書籍が出ていますが、松本智津夫を含む死刑囚11人の死刑執行後、近年出版されたものとして、江川紹子『「カルト」はすぐ隣に オウムに引き寄せられた若者たち』(岩波ジュニア新書)があり、オウム真理教の経緯や信者がはまり込んでいったプロセスについて、丁寧にまとめられています。
岩波ジュニア新書として、次世代に伝えることをメインに書かれた書籍ですが、大枠を理解するには大人にも十分すぎるほどの内容です。
興味があればご参照ください。
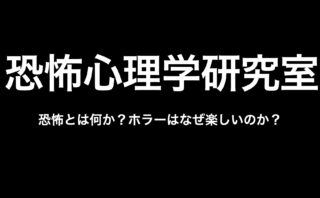






コメント