
作品の概要と感想とちょっとだけ考察(ネタバレあり)
タイトル:血の配達屋さん
著者:北見崇史
出版社:KADOKAWA
発売日:2022年10月24日
家出した母を連れ戻すため、大学生の私は北国の港町・独鈷路戸にやって来た。
赤錆に覆われ、動物の死骸が打ち捨てられた町は荒涼としている。
あてもなく歩くうち、丘の上の廃墟で母と老人たちが凄まじい腐臭の中、奇妙な儀式を行っているのを目撃する。
それがすべての始まりだった──。
何とも感想が難しい、血と錆と潮の香りに満ちた1作。
『血の配達屋さん』として第39回横溝正史ミステリ&ホラー大賞優秀賞を受賞。
その後、『出航』というタイトルで単行本として刊行されましたが、角川ホラー文庫化にあたり再び『血の配達屋さん』に戻されたようです。
個人的には『血の配達屋さん』の方が好きですし、文庫版の表紙のイラストも好き。
ただ、タイトルと表紙から漠然と想像していた雰囲気と実際の内容は、かなり異なるものでした。
小説の場合、内容とあまり関係のない表紙のデザインも少なくありませんが、本作の表紙は、主人公の母親である静子さんイメージなのでしょうか。
「根腐れ蜜柑」らしき本を持っているところからはそのように想像されますが、だいぶ若く、少女のようにも見えます。
内容に関しては、何ともおどろおどろしい、終始陰鬱な空気感のダークなスプラッタ。
猫好きな方は卒倒するかもしれませんが、あまりにぶっ飛んでいるので、むしろダメージは少なめかも。
北海道の寂れた町というロケーションがまた秀逸でした。
ちなみに、当然かもしれませんが、「独鈷路戸」という町名はオリジナルのようです。
さすがに実在していたら、苦情が来てもおかしくない扱いですね。
関係あるかわかりませんが、「独鈷」というインドの護身用仏具があるそうです。
序盤から化け物っぽい異形が出てきたりと、非現実感は強め。
ファンタジーというより、SFっぽさもあるでしょうか。
終盤の展開は確かに『出航』というタイトルの方が相応しい気がしますが、現実や常識を超えたトンデモ展開が繰り広げられていきました。
主人公視点で話が進んでいきますが、主人公のキャラが何とも掴みづらいというか、動じているのか動じていないのか、情緒に乏しく、すべてにおいて何だか他人事のような雰囲気。
それがあえて現代の若者らしさを反映させたものなのか、キャラの描写がいまいちうまくできていないのかはわかりません。
全体的に、登場人物たちの口調や容姿は個性的でしたが、あまり内面の書き分けはなされていなかったようにも感じました。
ちなみに、主人公の名前が一切出てきていなかったのは、終盤の「○○○」のセリフでようやく気がつきました。
色々とぶっ飛んでおり血みどろなはずなのに、文章が淡々としているからか、あるいは北海道の寂れた町という舞台のせいか、不思議と全体的に派手というよりは地味な印象。
それでいてそこそこ長く、思ったより現実離れした展開でもあったので、純粋にスプラッタを求めていた人など、展開が合わない人にはとことん合わなさそう。
本作は綾辻行人がプッシュしており、帯にも名前やコメントが使われていましたが、綾辻ファンが『殺人鬼』などのイメージを頭に浮かべたまま本作に手を出してしまうと、肩透かしになってしまうかもしれません。
しかし、そんな人物描写やトンデモ展開にもかかわらず、地に足ついた圧倒的な現実感が漂っていたのがとても印象的です。
主人公のキャラというか、地の文というかが独特で、そこでも好みは分かれるかもしれませんが、個人的には「あまり好きなタイプの作品ではないはずなのに、なぜかとても好き」と感じる作品でした。
ぶっ飛んでいるのに圧倒的な現実感があるのは、おそらく筆者の頭の中で圧倒的な現実感を持って構成されている世界観だからなのでしょう。
現実の町に当たり前のように溶け込む非現実。
血と錆や異形のモンスターという点が類似し、日常が気づけばいつの間にか非日常に変わっている描写は、ゲーム『サイレントヒル』を彷彿とさせる部分もありますが、『血の配達屋さん』は日常と非日常が入れ替わるのではなく、日常の中に非日常が溶け込み、それが日常と化していた印象です(伝われ)。
個人的に表紙やタイトルから勝手に抱いていたのは、ゴシック的なファンタジーでした。
ファンタジーはファンタジーでしたが、ゴシックとは方向性はだいぶ異なり、太古の支配者である異形など、ベースは完全にクトゥルフ神話でしょうか。
解説で「本作の根底にはある古典作品に対する尊崇の念があるのだ」と書かれていましたが、これはクトゥルフ神話を指しているのかな、と思っています。
とはいえ、ラヴクラフトなどあまり読めておらず、クトゥルフ神話に関しては軽く齧ったことがある程度のにわかなので、深入りするのはただの知ったかぶりにしかならないのは確実なため、避けておきます。
こういうときにさらっと語れるぐらいの知識と教養を身につけたい。
ここでは少しだけ、やや無理矢理ですが心理学的な視点から。
マクロ的に見ると壮大な物語ですが、小さく見れば主人公の家族の再生を描いた物語でもありました。
冒頭から母親が家出をするという、家族崩壊の危機から始まります。
それ以前の家族は、どうやら父親がいばり散らかしていた様子。
これまで色々な作品で触れてきましたが、母性はすべてを平等に包み込み呑み込む機能、父性は分断して規範などを示す機能を有します。
主人公の家では、父親の父性の負の側面が強く現れていました。
正しい方に導く理想的な父性ではなく、古い亭主関白的な、自己中心的に自分の価値観を押しつけ従わせようとする父性です。
それは、文字通り家族を分断させてしまいました。
それは母親の家出だけを指すわけではなく、それ以前から実質的に家族の心はバラバラでした。
母親の家出という崩壊の危機を経て、再び家族が集結し、そしてこれもまた文字通り家族が一体になるプロセスは、まさに主人公の家族の再生のプロセスでもありました。
肉の船に埋め込まれるというのは、まさに母性的な一体化です。
主人公の家族をまとめることができるのは、父親ではなくて母親なのでした。
主人公目線では、父親と妹の沙希が独鈷路戸まで母親を追いかけてきたのはかなり唐突に見えましたが、やはり実質的には母親の静子を中心にまとまっていた家族なのでしょう。
わざわざ北の僻地まで追いかけてきてしまうほどの存在だったのです。
母親の静子は、主人公が独鈷路戸まで尋ねてきたときも、さほど驚いた様子は見せていませんでした。
家族が追いかけてくるというのは、予想していたのかもしれません。
しかし、静子にとって主人公たち家族は自分の居場所ではありませんでした。
過去の性被害や、その先で出会った独鈷路戸や「根腐れ蜜柑」。
そこで自身の闇を解き放ってしまった静子には、もはや永遠に彷徨い続けるしかないと結論します。
自身の家族だけではなく、多くの者を取り込んだ肉の船で出航していった静子の姿は印象的です。
一方で、なぜ主人公だけ取り残されたのかは、疑問が残ります。
おそらく静子は、潜在的には自分を止めてほしい思いがあったのかな、と考えています。
それができ得るのは、理想的な不正を持たない役立たずの父親でも、まだまだ子どもで甘えの強い妹の沙希でもなく、唯一主人公だけだったのでしょう。
きっとそれは主人公も感じ取っており、だからこそ家族を取り込んだ肉船を追いかけようと準備を進めています。
家族を追いかけ、母の過ちを止めたときに、おそらく主人公の家族は本当の家族となるのでしょう。
終盤は世界を巻き込んだだいぶ壮大な物語となっていましたが、あくまでも描かれていた軸は主人公家族の再構築であったように感じました。
さらには、母親が行っていたのと同じことを息子が引き継ぐという、継承の物語でもありました。
とはいえ、頭で考えるよりも、圧倒的な独自の世界観を感じる系の作品として楽しんだ方が適切かもしれません。
だいぶ意味不明で難解さを感じながらも、不思議と感覚的に好きな作品でした。
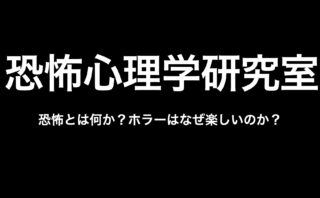






コメント