
作品の概要と感想(ネタバレあり)
タイトル:殺人勤務医
著者:大石圭
出版社:KADOKAWA
発売日:2002年3月8日
優秀な中絶専門医・古河は、柔らかな物腰と甘いマスクで人望も厚い。
しかし彼の価値観は、幼少期のある出来事により歪みきっていた。
彼は、死に値すると判断した人間を拉致して地下室の檻に閉じ込め、残忍な手段で次々と、淡々と殺していく──。
『呪怨』のノベライズのイメージが強かった大石圭。
昔なにか読んだかもしれませんが記憶にないので、初めての作品です。
個人的にはかなり好きな部類で、一気読み。
ホラーという感じではありませんが、一応角川ホラー文庫。
知らなかったのですが、大石圭、けっこう官能小説的な作品も書いているのですね。
その影響か『殺人勤務医』も、直接的な性描写は別として、拷問のシーンなども、性的な目的で拷問しているわけではないのに、妙に官能的に感じました。
主人公・古河の、中絶専門の医師としての表の顔と、法で裁かれないけれど他人に迷惑をかける人間を誘拐して監禁しては殺害する裏の顔。
どちらも同じトーンで淡々と描かれる点が特徴的です。
殺害シーンはそれなりに端折ることなく、拷問的な描写もけっこうしっかりと描かれています。
それでもグロいような、悪趣味すぎる感じにならないのは、古河のほとんど感情の感じられない淡々とした語り口によるものです。
中絶という、命の芽を摘む仕事を生業とする古河。
「表の顔」「裏の顔」と表現したのは勝手な解釈であり、彼にとっては表も裏もないのでしょう。
中絶、殺人、食事、愛情、音楽……すべてのシーンが同じトーンで描写される文体は、美しさすら感じられます。
現実感の乏しい、けれど非現実すぎて興醒めするわけでもない絶妙なバランスは、芸術的。
最後の犠牲者が母親であるのは予想がつきやすいですが、最後の最後、実は生まれた時から殺人者だったという設定も、とても綺麗にまとまっていました。
中絶に関する歴史も随所に挟まれ、安易な感想ですが、命とは何だろう、ということを考えずにはいられない作品でした。
考察:主人公・古河の心理(ネタバレあり)
サイコパスなのか?幼少期の環境が原因なのか?
あえて主人公・古河を心理学的に少し深掘りすると、まず、淡々と人を殺していますが、サイコパスではないと思われます。
共感性に乏しいのは確かですが、彼なりに感情や共感を示してはおり、決して搾取的でもありません。
むしろ、母親を前にしてついに感情的になったシーンからは、やはり幼少期の体験の影響の大きさを感じさせます。
現在何か問題が生じており、その人が幼少期に過酷な環境を経験していたとき、心理学的な観点からは、その幼少期の環境に原因(あるいは要因)を見出すことも少なくありません。
しかし、心理学を専門とする身としては逆に、安易に幼少期の環境だけに原因を帰属させることは避けたいと思っています。
もちろん影響はゼロではありませんが、人間は「原因→結果」という一直線に説明できるほど単純ではないからです。
「(複数の)要因」が相互作用的に影響し合っているものであり、「(一つの)原因」だけが影響している、ということはありません。
しかし、『殺人勤務医』の古河の場合、最後の犠牲者に母親を選んでいることからも、母親の存在にとらわれていたという要因が大きかったことは間違いありません。
産婦人科の医師になり、連続殺人犯になったことについて、古河は作品中でわざわざ「心理学者ならその原因を、僕の幼年時代に求めるかもしれない」と述べています。
そのため、考察するのは野暮かもしれませんが、古河を、フィクション作品のキャラクタではなくあえて一人の人間として考えてみたとき、この「そう見られるかもしれないのはわかってるよ」と言わんばかりに、先手を打つようにわざわざ言い訳する姿勢が、逆にこだわりを感じさせます。
しかし、わざわざ彼が作中でそう言っているのに、公式の紹介文で「しかし彼の価値観は、幼少期のある出来事により歪みきっていた……。」とあるのは、なかなか容赦なくて好きです。
古河の弟や妹になるかもしれなかった存在は、母が望まなかったために生まれることができなかった。
古河自身、虐待され、最終的には捨てられて、もしかしたらそのまま死んでいたかもしれません。
そんな彼が「生きるも死ぬも、運でしかない」というような考えを持ったとしても、安直ではありますが、不思議ではありません。
けれど彼は、やはり母親に愛されることを望んでいたのでしょう。
それが院長への恋愛感情のベースであり、もしかすると、医師として産婦人科を選び、中絶専門医になったことにも影響しているかもしれません。
自分は、望まれていなかったから捨てられたわけではないと確認したかった。
そのために、母を許すために居場所を捜したのに、結局、自分が疎まれていたことを確認することしかできなかった。
さらには、自分が生まれながらの殺人者であることを知っただけだった。
過激な中絶反対派の男性に襲われても、恐怖を感じなかった古河。
いつかは捕まり、死刑になることを予期しながら、殺人を繰り返す古河。
彼の生き方は、拡大自殺と呼べるような、自分の死を望んでいるようにも読み取れます。
「影」としての作品
この作品は、中絶専門医という面でも、連続殺人犯という面でも、いわゆる大多数の「普通の」人間とはかけ離れた世界・人物(古河)が描かれています。
法に裁かれない悪人を淡々と裁く彼に、爽快感を覚えた人もいるでしょう。
何の感情もなく、ただの独善的な価値観で殺人を繰り返す彼に、嫌悪感を抱いた人もいるでしょう。
それはいずれも、読者である「大多数の普通の人間である我々」の影が投影されています。
精神科医で心理学者であったC.G.ユングは、「生きられなかったもう1人の自分(諦めた夢を実現している自分、など)」「許容しがたい心理内容(大切なパートナーがいるのに浮気したい、など)」を「シャドウ(影)」と呼びました。
それは個人レベルでもありますが、社会・人類レベルでも存在します。
いわゆる「タブー」になっているものが、その一つです。
中絶についても、タブーとまではなっていませんが、あまり表立って気軽に話せるテーマではありません。
命とは何か。
命の選択。
合法的な殺人か、生命以前の存在であると定義しているから問題がないのか。
考え始めると、不安になります。
たとえ違法行為をしていなくても、制裁を加えたい相手がいる、という感情も同じです。
その欲求は、現代の過剰なバッシングにも反映されています。
対象を殺すことはできなくても、社会的な死を望んでいるとしか思えない執拗さも見られます。
しかし、そのような気持ちも、表立っては表現されず、何らかの理由によって正当化されます。
爽快感を感じる人も、嫌悪感を感じる人も、同じ欲求に反応しているのです。
その意味では、中絶専門医であり、(本人はそういうつもりではなくても)私的制裁を加えていた古河は、我々の影を引き受けてくれている存在と取ることもできます。
「彼はダークヒーローで、表立って言いづらいことを表現してくれている素晴らしい作品だ」という感想も、「こいつは自己中の最低な野郎で、ただの薄っぺらい胸糞悪い作品だ」という感想も、いずれかで片付けてしまう限り、影はさらに色濃くなるだけなのでしょう。
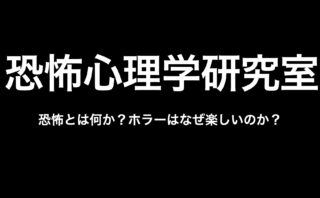






コメント