
作品の概要と感想(ネタバレあり)
タイトル:恐怖の日常
著者:村田基
出版社:アドレナライズ
発売日:2022年8月12日(ハヤカワ文庫:1989年2月1日)
ひどくむしゃくしゃする。
不輸快な感情が体の中を駆けめぐる。
全身に毒素が回り、内臓が焼けただれていくようだ。
吐き気がする。
もうがまんできない。
ぼくはどうなっていくのだろう。
これもみんな黒い雲のせいだ──。
古い作品ながら、珠玉の短編集。
ベースとなっているのは1989年のハヤカワ文庫JA(早川書房)。
電子書籍版の出版元である株式会社アドレナライズというのは初めて聞きましたが、どうやら電子専門の出版社であり、「入手困難な絶版本、過去の名作を発掘してリニューアル」してくれているようで、何ともありがたいことです。
著者の村田基は、残念ながら現在は小説は書かれていないようです(現在はライター?)。
読み方は「むらた もとい」で、漢字で検索すると同じ漢字で「むらた はじめ」と読むプロの釣り師の方が出てくるので、少々ややこしい。
最初は、このめちゃくちゃ陽気そうな写真が出てくる釣り師のおじさんがこんな小説も書いているのかと思いびっくりしましたが、別人でした。
それぞれの短編は、恐怖というよりは「世にも奇妙な物語」に近いような、不気味さや嫌悪感を喚起するような側面が強く感じました。
しかし、紛れもなくホラー小説。
タイトル通り「日常からのずれ」が生み出す日常から一歩逸脱したような恐怖感が広がっていますが、その想像力と筆力たるや恐ろしいもので、いつの間にか現実離れした異世界に、自然と連れ込まれてしまいました。
発想や展開は突飛すぎて、設定だけ聞いて冷静に考えればギャグに近いものも多いはずなのに、今いる世界が足元から崩れるような、得も言われぬ不安感が押し寄せてきます。
独特の世界観はとてもユニークで、すでに小説を書かれていないのは残念ですが、本作含めて5冊ほど出版されており、いずれも絶版ながら電子書籍化はされているようなので、のんびり追っていきたい。
以下、簡単にそれぞれの感想を。
山の家
果たしてどんな作風なんだろうな、と思いながら読み始めた1作目にして、パンチの効いた作品。
なぜそんな山の中に住んでいるのか?
ママと呼んでいるので主人公は幼いのかと思いきや、まさかの大学受験浪人生っぽい。
しかも食料が手に入りにくかったりと、謎にサバイバルな状況である様子。
戦後なのか?
いきなり漂う訳のわからなさと不穏さ。
そこにいきなり飛び込んでくる2人組。
戦後どころか戦争中らしい。
しかも内戦?
核戦争?
かくして、過去の現実を舞台に日常が描かれているわけではないことがだんだんわかってきて、そして明かされる真実。
カニバリズムは多くの作品で取り扱われていますが、その非道徳的行動に至るまでのプロセスと世界観があまりに独特。
カニバリズム、すなわち人間同士の共食いというのは生理的な嫌悪感や抵抗感を喚起するものですが、緊急事態(たとえば1972年のアンデス山脈の墜落事故)であればまだ抵抗感が薄まります。
本作の状況はその中間のような感じで、「生きるために仕方なかった」側面もありました。
それでもなぜこれだけの不快感が生じるのだろうかといえば、やはり主人公の心理メカニズムでしょう。
現実から目を逸らしひたすら自分の殻に閉じこもる子どもと、それを許容していた母親。
「嫌なものから目を背ける」「抑圧」などと言ってしまえば簡単ですが、「ママ」呼びも含めて20歳の主人公としてはあまりに幼稚な精神性、そして母の死を前にしながらも引き続き、さらに強固に自分の世界に閉じこもる姿は、哀れさすら漂います。
まるでループしているかのようなラストですが、むしろループしていた方が救いがあるのでは思えるほどで、母親が死んだ主人公の時は無情にも前へ前へと進んでいきます。
この心理的な防衛メカニズムがいつ崩壊を迎えるのか?
そんな未来をついつい想像してしまうのが、恐怖に繋がるポイントでした。
窓
おぉ、まさかのカウンセリングがテーマだ、と思いきやまたとんでもない話でした。
リアルなカウンセラーの対応としてどうかなぁ……とか考えながら読んでいたのが馬鹿らしく感じられるほど、展開は大きく飛躍。
この作品の後半あたりで、「常識の枠組みで考えてはいけない作品群なんだ」というのがすでにわかってきました。
開けちゃったら駄目なら、開けずに外に出せばいいじゃない。
「窓を突き破らせる」という仰天アイデアを「行動療法」「クライアントに合わせた療法」なんて呼ぶのはギャグでしかありません。
クライアントの彼がようやく突っ込んだと思ったら丈夫なガラスに戻されていたなんて、完全にコント。
しかし、そんな常識的なツッコミを超越する展開。
「窓」という日常にありふれたアイテムを再考する視点は、まさに常識や日常を揺るがす視点です。
考え始めると確かに窓というのは不思議なもので、視覚的には開けており向こう側との繋がりを感じさせながらも、外と内を区切る役目を果たしています。
窓の外の世界は今自分がいるこちら側と本当に繋がっている世界なのか?という不安を生じさせるのは、鏡に対する感覚にも似ています。
この作品は、まさに精神疾患の世界に近いものを感じました。
日常にある当たり前のもの、普通であれば気にならないことに違和感を抱く。
一度抱いてしまうとその違和感がどんどんと大きくなり、思考の多くを占めるようになって、生活にも支障を来すようになる。
狂気は常に日常と隣り合わせであるということを痛感するような作品でした。
白い少女
虫嫌いにとっては、なかなか試練な作品でした。
できるだけ具体的に想像しないように流し読み。
早々に奇形だという話が出て、どう考えても怪しいのはわかるのに、先がまったく読めません。
シロアリの話を経て、徐々に高まっていく不穏さ。
それらしい設定も用意されて、ホラーではよくあるキメラ的な存在というのがわかってからが本番でした。
もはや人間的ではなく虫の繁殖に堕してしまったような感覚が、何とも不快です。
美しい女性、しかしその正体は恐ろしい怪物。
そんな存在に呑み込まれた男性の話というのもまた昔話などで定番中の定番ですが、それの現代版というような印象を受けました。
大きくなあれ
催眠による暗示で際限なく大きくなってしまった人間の話。
これもまた、そんな設定だけ聞けば何とも笑える話でしかありません。
人間がただ大きくなるだけですが、それだけで不気味さや恐ろしさが漂うのが面白い。
巨人の恐ろしさといえば、近年で言えば漫画『進撃の巨人』などがありますが、あのような巨人とはまた違う、普通の人間がただ大きくなっただけ。
思い出したのは貴志祐介の『エンタテインメントの作り方』という、小説や物語の作り方を述べた本。
この中で、アイデアの発想について「もし○◯が××だったら」という考え方を紹介しており、貴志祐介のアイデアノートに書かれた一例として「もし人間も無制限に大きくなったら」という一文が挙げられていました。
そこでは、「老人は巨人だらけになり、介護が大変、お葬式は巨大な棺を囲むことになる、巨大化した老人の肉体は若者にとって恐怖だろう。そんな奇妙な社会は、どんな問題を抱えているのか?」といった方向性で発想が広げられていましたが、本作はまさに、そのアイデアを貴志祐介のようなマクロな社会的視点に広げたのではなく、ミクロに1人の人間が巨大化することの恐怖だけに絞って描いた作品と言えるでしょう。
最初に述べた通り、「人間が大きくなるだけ」の作品です。
その設定だけでも、ホラーにも笑いにも、社会的な作品にも、いかようにも広げようがあるわけで、人間の想像力は無限であることを改めて感じます。
同時に、自分の想像力がいかに常識に囚われ、狭くなっているのかも。
反乱
だから虫が嫌いだって言っているでしょう!
そんな自分にとってはもう、地獄のような作品でしたね。
ここまで読んできて、本当に日常から一歩ずらしたワンアイデアだけで発想を広げるのが得意なんだな、というのを感じました。
あぁ嫌だ嫌だ。
まったくもう。
葬られた薬
「山の家」でも垣間見られたミステリィ要素が強めの1作。
途中で何となく「真相がわかったぞ」と思わせておいて、さらにもう一段階の構えがあって最後にひっくり返されるのは、ミステリィとして完璧でありお見事です。
それでいて、根底はしっかりとホラー。
古来、愚かな人間が追い求めてきた不老不死。
それが結局は死に結びつくというのも珍しくはない構図ですが、科学的(っぽい)設定が秀逸でした。不老長寿の薬を葬り去る組織というのも面白かったですが、最後の最後に結局は死神という「科学っぽい設定」から「オカルト」に振り切ったのも面白い。
個人的には到底、不老長寿が幸せであるとは思えません。
絶対どこかで精神が崩壊して自殺するでしょう。
その意味では、不老長寿と死神はそもそもがセットなのかもしれません。
子宮の館
急に生々しいタイトルですが、内容はさらにどぎつい。
そしてさすがに笑ってしまいます。
平山夢明作品に近いような印象。
「窓」でもダイレクトにカウンセラーが登場していましたが、全体的に心理学的な要素が多く散りばめられているように感じました。
本作もまた特にその要素が強く、母胎回帰願望というのは、フロイトが提唱した精神分析的な概念。
めちゃくちゃ雑に言えば、「人間は完全な世界であり、安心、安全、万能が感じられた母胎に回帰したい願望がある」といったような考え方。
さすがに現代においてその概念を安直に用いる心理士はいないでしょうが、物語を見る視点としては面白さもあります。
そんな母胎回帰願望を叶えてくれる、ぶっ飛びすぎな風俗店(?)。
いわば究極の赤ちゃんプレイでしょうか。
そこに依存的になってしまうという展開もシニカルです。
終わり方は「これしかないよね」と納得せざるを得ません。
赤ちゃんとして生まれ変わるのがまだサービスの延長であり、赤ちゃんに永井の意識があるのだとしたら、最高に怖い。
屋上の老人たち
個人的には一番狂気を感じたのが本作でした。
「恐怖の日常」という観点で考えると、本作が突飛ながらも一番身近にあり得そうなリアルな薄気味悪さを感じました。
アクシデントを楽しむ老人たち。
だんだんエスカレートして、自分たちでアクシデントを起こすようになっていく。
周囲の評価を気にして、うまくいかずに追い詰められて自殺までしてしまう。
まさに現代のSNS的ではありませんか。
老人たちには強烈な嫌悪感を抱きながらも、誰もが心の奥に持ち得る暗い部分を無理矢理突きつけられたような居心地の悪さも感じました。
恐怖の日常
いわゆる毒親を描いたような作品。
今となっては新鮮さもなく、「あ、これで終わり?」と思ってしまう感覚も否めませんが、これが執筆されたのは1980年代後半。
「屋上の老人たち」もそうですが、先見の明があったとも言えますし、人間の本質的な部分を見つめていたからこそとも言えるでしょう。
ワンアイデアを膨らませ、日常から一歩だけ逸脱した世界を描いていたここまでの作品に対して、本作はまさに「日常にある恐怖」がそのまま描かれていました。
日常において一番怖いのはやはり人間なのだ、というと陳腐な感想になってしまいますが、現代においては「いるいるこういう親、いっぱいいるよね」と簡単に思えてしまうことこそが、恐怖の日常なのかもしれません。
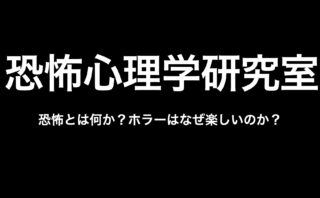






コメント